非正規雇用問題といえば、これまで政策的にも派遣労働者の扱いに焦点が当てられてきた。規制緩和や景気回復による2003年ごろからの派遣労働者急増と、リーマン・ショック以降の雇い止めによる大幅減などの特徴的な動きが、あたかも「非正規労働者=派遣労働者」であるかのような図式を生んだことも否めない。しかし、派遣労働者は雇用者全体の2~3%程度(総務省労働力調査)でしかないという認識は重要だ。
一方、契約期間という軸からみれば、非正規雇用者のほとんどすべては有期契約労働者(以下、有期労働者)である。したがって、有期労働者の扱いを考えることこそ、遅まきながら「非正規雇用問題の本丸」に着手することを意味する。
厚生労働省は去る9月、有期労働契約について研究会報告書を公表し、10月末から労働政策審議会での検討を開始した。しかしながら、同報告書は、明確な制度改正の方向を示すことができなかった。本稿では、有期雇用改革のあるべき姿を提示してみたい。
◆◆◆
有期雇用改革の論点は多岐にわたるが、欧州における有期労働規制体系を日本へ移入すべきかどうかが大きな焦点となっている。欧州の規制体系は1999年の欧州連合(EU)指令によりすべての加盟国が順守しなければならない規制と、各国独自の規制に分かれる。その体系は主に(1)規制の理念・根拠(2)有期契約締結にかかわる規制(入り口規制)(3)処遇の規制(4)有期契約終了に関する規制(出口規制)から成り立っている。
まず、規制の理念であるが、欧州では期間の定めのない労働契約(無期労働契約)が原則であることが規定されていることが多く、EU指令でも有期雇用の差別や乱用を防ぐことが目的とされている。有期契約締結の条件として一時的な需要増や季節労働など客観的な理由を要求する入り口規制は、EU指令では義務付けられていないが、南欧諸国を中心に歴史的に各国で行われてきた。
一方、出口規制についてはEU指令で、有期雇用の反復による乱用を禁止するため、最長継続期間の上限、更新回数の制限、更新を正当化する客観的事由提示のいずれかが必要になる。処遇についてもEU指令で客観的理由のない差別が禁止されている。
こうした欧州の規制体系に対して、日本では、実態としては正規雇用=無期雇用が基本という認識はあるものの、法体系で明文化されてきたわけではない。入り口規制、処遇の規制もなく、出口規制についても、反復乱用から有期雇用を保護する規制はない。雇い止めを巡る争いについては、裁判での判例を通じた「雇い止め法理」(一定条件の下で無期雇用と同様にみなして扱う「解雇権乱用法理の類推適用」)が形成されてきた。
日本の労働基準法では有期雇用の1回の契約期間における上限が原則3年と定められているが、これは乱用を防止する出口規制ではなく、拘束への規制である。つまり、日本で有期雇用の規制は民法の規定を含め、保護という観点からは拘束規制しかなく、大陸欧州と比べてももともとかなり弱い。経済協力開発機構(OECD)の雇用保護規制指数をみても、日本の有期雇用規制はむしろ米英などに近い水準だ。このため、正規(無期)雇用と有期雇用の規制度合いの乖離は比較的大きくなっている。
◆◆◆
しかしながら、有期雇用の保護強化という観点から欧州型規制を日本へそのまま移入することは問題点がある。なぜなら、第1に、制度全体を他の国に移入する場合、その制度自体がどんなに良い制度であったとしても、受け入れ国側の環境条件が大きく異なれば、移入された制度は実際には機能しないからである。
日本ではこれまで有期雇用の規制が弱かったことで、既に有期雇用(特に契約・勤続期間の長いグループ)の割合はかなり高まっている(図参照)。また、これまでも有期雇用の更新、継続は労使双方が合意すればむしろ望ましいと考え、有期雇用の長期継続が積極的に促進されてきた面がある。これまでの歴史的な経緯を考えると、入り口・出口規制や無期雇用原則の導入は必ずしも実効的な選択肢ではないだろう。
第2の理由は、EUの有期雇用の規制体系は非常に包括的な体系であり、個々の仕組み・要素が相互に補完性を持ち、一体となって全体の一貫性や整合性を保っていることである。全体への配慮のない、つまみ食い的な制度の移入は効果が無く、むしろ副作用が懸念される。
例えば、入り口規制の導入は難しくても、出口規制は導入すべきだという議論がある。確かに、いくつかの欧州諸国では入り口規制が緩和されているが、それでも出口規制が機能しているのは、無期雇用原則の下、無期雇用への転換義務化が実際に機能しているためである。出口規制だけ取り上げて日本に導入しようとしても、予防的な雇い止めが多発するだけであろう。
日本と同様に深刻な非正規雇用問題を抱える韓国では、07年7月から出口規制(最長2年、2年を超えた場合は無期とみなす)を導入したが、正規雇用への転換は必ずしも高まっていない。韓国の経験からも学ぶ必要がある。
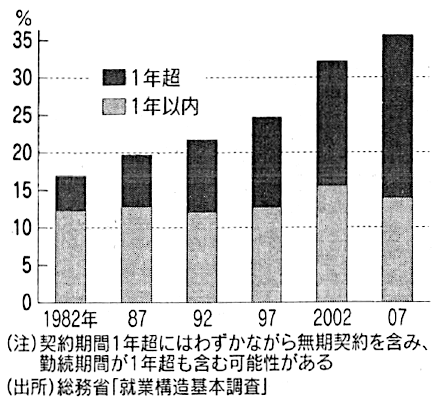
◆◆◆
それではどのような有期雇用改革が必要であろうか。大きな方向性としては、入り口・出口規制のような有期労働者の数を無理やり抑えこむ「量の規制」ではなく、有期雇用労働者の処遇改善・多様化に結び付くような「質の規制」を考えるべきである。
特に有期雇用の不安定さや雇い止め問題への対応としては、契約締結時点で更新可能性や更新回数を明示した有期雇用契約の多様なコース分けを徹底し、制度化することで、契約終了時の結果の予測可能性を向上させるべきだ。
また、正社員として採用するための試用期間を有期雇用契約として明確に位置付ける「テニュア(在職権)制度」を導入すべきである。現状の試用期間は期間の定めのない雇用契約の中で位置付けられているため、解雇権乱用法理が適用されるなど硬直的な仕組みとなっている。しかし、試用期間が有期雇用契約として設定されれば、企業側は正社員雇い入れリスクが低下し、結果的に正規雇用比率が高まる効果が期待できる。
さらに、雇用不安定への補償という観点からは、有期雇用の契約終了時に「契約終了手当」支払を義務付けることも検討すべきだ。例えば、フランスでは在職中に支払われた賃金の原則10%の支払が義務付けられている。日本でも戦前は「退職積立金及退職手当法」(1936年制定、その後廃止)で有期労働者に対しても、退職積立金に加えて、事業主の都合で解雇した場合、勤続期間に応じて特別手当=解雇手当を支払うことが義務付けられていた。契約終了手当の導入においてはこうした期間比例的な配慮も重要である。
今回の世界経済危機の中ではスペインを筆頭にいくつかの欧州諸国でも有期労働者にしわ寄せされる形で大幅な雇用調整が行われた。労働市場二極化の抜本的是正のため、欧州の経済学者から提案され注目を集めている改革案は、欧州で一般的な解雇手当などの雇用保護に有期雇用・無期雇用の違いでギャップを設けず、勤続年数のみにスムーズに比例する制度への転換である。つまり、有期雇用と無期雇用を一本化し、雇用保護を勤続年数に応じて連続的に強める仕組みである。
筆者はかねて、有期雇用と無期雇用の間に中間的な雇用形態や処理の仕組みを作ることで「間を埋め」、期間比例的な考えに基づき「連続性」を創出していくことを主張してきた。欧州での提案は、筆者の考え方を究極的に推し進めたものといえ、いずれ日本でも課題になるであろう。
有期雇用改革においては日本の実情に合った新たな包括的、整合的な制度設計が求められる。そのまま倣えばいい「お手本」がないだけに難しいが、若い世代の生きがいや希望を大きく左右する責任の重い仕事でもある。よりよい制度設計に向けて議論が喚起されることを期待したい。
2010年11月22日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


