円高や後発企業の成長で東アジアの企業間競争が激しさを増している。技術や競争力に関し、日本企業はどの程度キャッチアップされたのか。
こうした問題意識から、日本経済研究センターの「日中韓台企業の生産性と無形資産投資に関する研究会」は、一橋大学経済制度研究センター、日本大学中国・アジア研究センター(研究代表は乾友彦日大教授)およびソウル大学企業競争力研究センター(代表はリ・クゥンソウル大教授)と共同で、東アジア上場企業(EALC)データベース(http://www.jcer.or.jpでデータを公開予定)を更新。生産性や生産性上昇の原動力の1つである無形資産投資に関し、国際比較分析行った(座長は筆者)。
◆◆◆
同データベースは日本、中国、韓国、台湾の金融業を除く全上場企業を対象としたものである。企業レベルでの全要素生産性(TFP)の測定に必要な各年の実質総生産、中間財・労働・実質資本投入などのデータを収集。その上で、経済全体を33の産業に区分し、各産業内で生産物や中間投入・資本財の国際価格差を調整、日中韓台の企業についてTFP水準を比較した結果を収録している。各産業で99年の全対象企業のTFP水準平均値を求めこれをゼロとし、その水準との比較でTFPの動きを分析した。対象機関は、日本、韓国、台湾が1985-2005年、中国は99-05年である。
電機、自動車、金属など多くの産業で、日本企業のTFPは東アジアで最も高いが、その上昇率は停滞している。例えば自動車産業に関し、上場企業のTFP水準を売上高で加重平均した平均値で日中韓を比較した図1を見てみよう。05年時点でも日本企業のTFPは韓国企業より3割(つまり同量の生産性要素投入で3割多く生産できる)、中国企業より5割高いが、折れ線の傾きで示されるTFP上昇率は中韓企業よりも低く、格差は縮小しつつある。
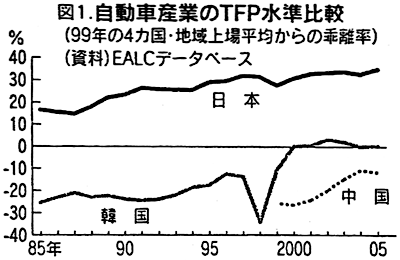
データベースからはこのように、東アジア各国・地域の産業別の動向も把握できる。中国企業のTFPを見ると、外資系企業との連携や競争が激しい電機や自動車などの機械産業では伸びが堅調だが、繊維、食品加工など労働集約的な産業や金属、化学など国有独占企業が支配する産業では比較的停滞している。こうした産業群の多くは販路が国内中心なだけに、内需主導の成長に移行しつつある中国にとり、懸念材料といえる。
台湾企業は、電機、化学、一般機械などでTFPの上昇が顕著で、化学や一般機械のTFPの水準は韓国企業と並び、日本企業にほぼ追いつきつつある。韓国では、90年代後半の通貨危機以降、TFPは伸び悩んだ。ただ、財閥系を中心にTFPが改善した一部の企業がマーケットシェアを拡大しつつある。このような新陳代謝機能の増進によってTFPの産業平均値が上昇している点は、上場企業間の生産性格差が小さく新陳代謝も停滞している日本と対照的であるといえよう。
◆◆◆
多くの産業で日本企業のTFP水準が他の東アジア企業より高いが、それは必ずしも日本が強い国際競争力を持つことと同義ではない。国際競争力は、TFPの高低だけでなく、賃金率などの生産コストにも左右されるからだ。TFP上昇が停滞する日本企業にとり、アジアで最も高い日本の賃金率の下で生産を続けることは次第に困難になり、これが生産の海外移転を促進したと考えられる。
なおTFP上昇が停滞し国内で生産された財やサービスの国際競争力が失われても、日本の輸出がなくなるわけではない。競争力の喪失や空洞化は、国内の賃金率や円の価値の低迷をもたらし、国内生産された財・サービスの競争力が回復されるまで、この過程が続くはずだからである。
米ドル換算の日本の1人当たり国内総生産(GDP)の順位は、90年代半ばまでは経済協力開発機構(OECD)加盟国中3位前後だったが、07年には19位、最近の円高を考慮しても10位以下に転落した。その最大の原因は、日本の製造業のTFPが低迷したためだと考えられる。
生産性の面で見た日本のもう1つの懸念材料は、情報技術(IT)産業を中心としたTFP上昇が堅調な産業のシェアが減少しつつある点だ。
産業構造と経済成長を考える上で「ボーモル効果」という視点がある。TFP上昇率は産業間で大きく異なる。このため、ITなど上昇率の高い産業が拡大すれば、マクロのTFP上昇も加速する。だが各産業の規模は需要構造で制約されている。例えば、IT産業では生産性の著しい上昇に伴いアウトプット(産出)価格も下落する。価格下落に対応し、内需がそれほど拡大せず、また国際分業によるこれらの産業への特化も起きない場合は、生産量が増えないため、生産性が上昇するにつれ生産要素の投入は次第に減っていく。つまり、生産性上昇率の高い産業は、経済全体に占めるシェアがいずれ縮小し、マクロ経済のTFP上昇は下落する危険がある。こうした一連のメカニズムを「ボーモル効果」という。
70年から2000年を見ると、日本でも労働投入の増加とTFPの上昇は基本的に負の相関関係にあった。つまり、TFP上昇が著しい産業ほど労働投入は減り、労働投入が増えたのは、社会保険・社会福祉(老人介護を含む)など上昇率が低い産業だった。だがこの時期には半導体や電子計算機など、ボーモル効果を乗り越えて、高いTFP上昇と労働投入の増加を両立させた産業が多くあった。
2000年以降、生産の海外移転などで、これらの産業の日本国内での労働投入は増えなくなり、ボーモル効果を乗り越える産業はほぼ消滅した(図2)。図の右上に位置する産業群が減ったのだ。
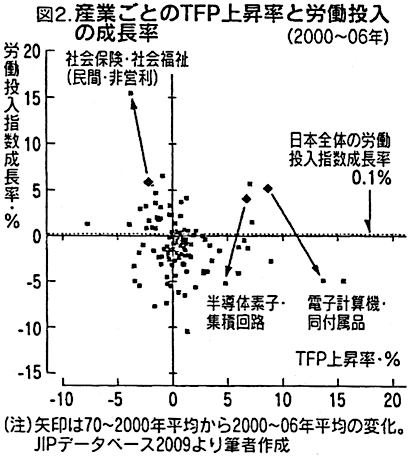
95年以降の米国で同様の分析をすると、IT財を生産する製造業は労働投入が大幅に減少したが、情報・通信、小売り、運輸、金融仲介などIT技術を多用する多くの非製造業では、高いTFP上昇と労働投入の増加を両立させた。金融危機の米国が過去の成長パターンを維持できる保証はないが、非製造業の技術革新が経済全体のTFPと賃金率をけん引する点は、日本も見習ってよいだろう。
◆◆◆
2000年代に入り、リストラを背景に日本企業のTFP上昇は回復しつつあった。また近年は正規労働者の雇用増や製造業を中心とする設備投資の加速など、長期的な成長を見据えた戦略を採用し始めていた。堅調な成長経路に乗ろうとする矢先に、日本経済に外需急減と円高を主因とした経済危機が襲った格好だ。
アジア諸国・地域にキャッチアップされつつある日本にとって、TFP上昇とシェア拡大を両立できる産業群を育成することは重要な課題である。先端的な製造業の国内回帰に加え、非製造業で、遅れているIT投資や組織改編、労働者の熟練蓄積などの無形資産投資を加速させる必要がある。また情報・通信、航空輸送、金融・保険など、生産性の伸びが高く高付加価値を期待できるサービス分野の内需を喚起したり、アジアのハブとしての日本の地位を高めてサービス輸出を促進したりすることで、ボーモル効果を回避する方向が望まれよう。
2009年5月8日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


