| 開催日 | 2011年1月18日 |
|---|---|
| スピーカー | 藤田 昌久 (RIETI所長・CRO) |
議事録
 (独)経済産業研究所(RIETI)は、1987年に通商産業省の一部局として設置された通商産業研究所を前身とし、2001年4月1日に非公務員型の独立行政法人として設立された。第1期(2001年~)は青木昌彦初代所長(スタンフォード大学)を中心に9つの研究クラスターで研究を始め、第2期(2006年~)は4つの基盤研究領域を定めて取り組んできた。そしてこの4月から始まる第3期には、中期目標「経済産業政策の重点的な視点に沿って、経済成長のグランドデザインを理論的・実証的に研究することをわれわれの使命として、1)「世界の成長を取り込む視点」、2)「新たな成長分野を切り拓く視点」、3)「社会の変化に対応し、持続的成長を支える経済社会制度を創る視点」の3つの重点的な視点を常に念頭に置いて研究を行う。昨年流行した言葉「整いました」を使って、ここでひとつ披露すると、RIETIの第3期とかけて、奈良・興福寺国宝の阿修羅三面像と解く。その心は、3つの視点から世界を究明するということだ。この3つの視点が、ヤマタノオロチの頭のように3つに分かれているわけではなく、統合されていることが重要である。頭脳は全体としてつながりつつ、それぞれの視点において特有の理論もある。すなわち、国際・空間経済学的な理論、イノベーションと生産性の理論、マクロ・金融・財政と組織・制度の理論があり、その中央にデータベースがあるというように私は理解している。第3期はこうした形で皆で研究を進めていきたい。
(独)経済産業研究所(RIETI)は、1987年に通商産業省の一部局として設置された通商産業研究所を前身とし、2001年4月1日に非公務員型の独立行政法人として設立された。第1期(2001年~)は青木昌彦初代所長(スタンフォード大学)を中心に9つの研究クラスターで研究を始め、第2期(2006年~)は4つの基盤研究領域を定めて取り組んできた。そしてこの4月から始まる第3期には、中期目標「経済産業政策の重点的な視点に沿って、経済成長のグランドデザインを理論的・実証的に研究することをわれわれの使命として、1)「世界の成長を取り込む視点」、2)「新たな成長分野を切り拓く視点」、3)「社会の変化に対応し、持続的成長を支える経済社会制度を創る視点」の3つの重点的な視点を常に念頭に置いて研究を行う。昨年流行した言葉「整いました」を使って、ここでひとつ披露すると、RIETIの第3期とかけて、奈良・興福寺国宝の阿修羅三面像と解く。その心は、3つの視点から世界を究明するということだ。この3つの視点が、ヤマタノオロチの頭のように3つに分かれているわけではなく、統合されていることが重要である。頭脳は全体としてつながりつつ、それぞれの視点において特有の理論もある。すなわち、国際・空間経済学的な理論、イノベーションと生産性の理論、マクロ・金融・財政と組織・制度の理論があり、その中央にデータベースがあるというように私は理解している。第3期はこうした形で皆で研究を進めていきたい。
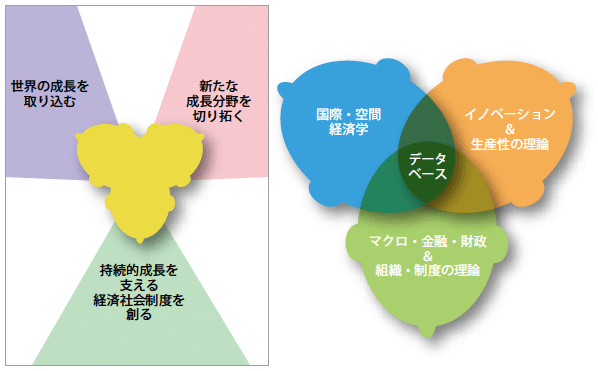
今日は、私が専門とする空間経済学の視点からグローバル化の進展と世界経済地図の大きな構造変化についてお話しし、それを背景として、今までの東アジアの経済成長と将来の世界経済・アジア経済の均衡発展に向けての再構築について意見を述べたい。さらに、知識創造社会における多様性と文化についてお話しし、それを基に、グローバル化と知の時代における日本再生について個人的な意見を述べたい。
空間経済学とは
地理的空間を対象とする経済学の分野には、従来、都市経済学・地域経済学・国際貿易理論の3つがあった。脱国境の時代になり、集積形成のミクロ理論を中心として一般化と革新をしたのが、新しい経済地理学(NewEconomicGeography)ないしは空間経済学(Spatial Economics)である。これがポーターのクラスター理論と違うところは、常に経済学の一般均衡理論・一般均衡動学的アプローチを行ったことである。
空間経済学の大きな発展の契機として、1990年に実際に始まったヨーロッパ連合(EU)統合がある。15の国の国境を取り払うことがEU統合のスタートであり、国境を取り払った後のヨーロッパの新しい経済地図を考えるためには、それまでの都市経済学、地域経済学、国際経済学を統合する必要があった。その後およそ10年間にわたり、多くの研究者を巻き込んで研究が進められた。そして1999年にPaul KrugmanとAnthony Venablesと私がその成果を1つの体系的な理論としてまとめたのが『The Spatial Economy』という本である。
昨年8月にスウェーデンのヨンショーピングで開催されたEuropean Regional Science Associationの50周年記念大会では、『The Spatial Economy』発表10年を記念したラウンドテーブルセッションが行われ、Jacques Thisseの司会の下、われわれ執筆者3人が空間経済学についてディスカッションをした。そこでの内容にも触れながらお話ししたい。
空間経済学の対象は世界経済地図のダイナミックな変遷である。輸送技術と情報通信技術の飛躍的な発展によって、人・物・金・情報を含めた広い意味での輸送費が大幅に低減されている。これが世界経済システム変革のエンジンとなり、脱国境というグローバル化と、局地経済圏の形成や都市・地域の重要性の増大というローカル化を同時に引き起こしている。
基本的な考え方として、いろいろな経済活動を1カ所に集めようとする集積力と、それを分散しようとする分散力という2つの力のせめぎ合いで自己組織化が起こり、安定的な空間構造ができる。それが、技術や状況の変化によって不安定化すると、新しい空間構造に移っていくのである。19世紀にヨーロッパを中心に産業革命が起こり、20世紀という自動車と石油の時代にはアメリカが発展、そして20世紀後半からは中国やインドも含めたアジアへと、成長地域が大きく移ってきている。こうした大きな変化をとらえることが空間経済学の基本的な狙いである。
東京に3000万人が集まれば地価が上がり、賃金も上がるので、その影響で自然と分散力が生まれる。では、なぜ東京に3000万人も集まるのか。ひとつには関東平野という自然的条件もあるが、内生的な集積力が非常に大きいのだ。従って空間経済学の理論的な中心は、内生的集積力をどう説明するかという点にある。
内生的集積力を生む背景要素として一番大きなものは、消費財や中間財をつくる活動と、人間そのものの多様性ないし差別化である。これらの要素に規模の経済や不可分性、また人間や企業の移動が加わることにより大きな地域レベルでの集積力とイノベーション力が生まれる。
集積の持つロックイン効果には正と負の両面がある。短期的には、どんどん東京に人が集まってきて成長するという大きな正の外部性があるが、長期的には外部性かつシステム全体の問題により、個人的に変革することが難しいという負の効果が働く。それが日本の現状である。こうした状況を克服するために新たな血と知の導入によって新たな外部性を構築していくことが、広い意味での経済産業政策になるのではないか。
多様性と集積力:文化産業を例として
集積力を増すには多様性が不可欠だ。なぜなら、いろいろな活動や人間に多様性・差異化があると、直接的な競争関係(特に価格競争)を避けることができ、全体としての補完性が増す。そうすると、1カ所に集まっても外部性を通じての生産性・集客力・創造性が増し、地域全体としての収穫が増すからだ。これを文化産業を例にご説明したい。
効用関数では、多様性(バラエティー)が増えれば効用がどんどん増す。もちろんバラエティーが無限に増えない理由は規模の経済が働くことである。その説明は省略するが、一例として、日本の「ギャル産業革命」が挙げられる。これは若い人のファッションを中心とした新しい産業・文化だが、ファッションといってもヨーロッパ型のハイファッションではない。ファストファッションといわれる、3万円もあれば頭の先から爪先までトータルで買えるような若い人を中心としたファッションである。このファッション革命の発祥地である渋谷の109は、今やギャルファッションの殿堂と呼ばれ、アジアを中心に世界中から年間900万人の買い物客が訪れている。120ある各店舗の広さは50m²程度だが、年間売上は一店舗平均約3億円でビル全体の売上は約400億円と、大きな百貨店にも相当する額である。
こうした集客力は圧倒的な多様性により生み出されている。各店舗ではオリジナル商品しか売っておらず、商品は月に半分以上というスピードでどんどん入れ替えられている。個々の店舗内でも、店舗間でも多様性があるために直接の競争関係が避けられて補完性が増している。
一番よく売れているCECIL McBEEは年間10億円の売上があるが、ここにはデザイナーは1人もいない。6人ほどいる店員が商品企画を行ってアパレル会社に製造を頼み、企画から1カ月以内には製品になるというスピードだそうだ。店員はモデルの役目も担っているが、もともとは客だった人が多く、客が売り子になってモデルもしている。重要なのは、客も店員も企画や営業をする人も一体となってオリジナル商品をつくり、それをどんどん入れ替えていくということである。
店舗間には直接的な競争関係はないが、間接的な競争はある。ビルの賃借料は、120店舗の平均的な売上3億円に相当するため非常に高額で、年間で3分の1近くの店舗が入れ替わる。このように圧倒的な集積でどんどん変化し、商品開発とクリエーションが同時に行われている。
これはアパレルの例だが、東京ではそれに関連したさまざまな産業が育っている。1つはファッションマガジンだ。コンビニで売られている雑誌の半分近くを占めるファッションマガジンは、モデルがテレビドラマで主演するなど、非常に広い裾野で相乗効果(シナジー)を発揮している。また、そうした効果は日本国内にとどまらず、たとえば雑誌「Ray」については、1993年に2人の中国人女性が主婦の友社から版権を買って、内容の半分を中国向けのオリジナル記事に変えた中国版「瑞麗(Rayli)」を出版している。地下鉄の駅などで1冊20元で販売され、月105万部売れているそうだ。このように、日本のファッションマガジンの現地版は、韓国やタイ、フィリピンも含め、アジア中で売られて国際的に大きな広がりを見せている。別の例を挙げると、アイドルグループAKB48にこれだけ爆発的な人気がある理由も多様性に関係がある。AKB48のメンバーそれぞれがフォーカスされた中での圧倒的な多様性のパワーを持っている。秋葉原にあるAKBの専用劇場のチケットは事前にウェブで当選した人のみに販売するというシステムだが、倍率は100倍ぐらいらしい。それもフォーカスされた多様性による新しいビジネスモデルで、これだけ圧倒的な集客力を持っている。
韓国では、自国マーケットが小さいために最初から国際的なマーケット戦略を取っている。だから少女時代というアイドルグループも日本語、英語、中国語をすべて話せる。これを空間経済学の視点で見ると、日本はホームマーケットが大きいために非常に力を持っているわけだが、韓国はマーケットが小さいために、逆に英語や日本語を話し、輸送費を下げて世界の市場に広く出ようとしている。一方、需要の大きいところに需要のシェア以上に集積がおきる自地域市場効果(HomeMarket Effects: ホームマーケットエフェクト)によって、ファッション産業、エンターテインメント産業、メディア、文化・観光産業が、日本であれば東京を中心に集まっている。これで魅力が増して多くの若者が来ると、東京がますます大きくなる1つの原動力になる。
空間経済学の基本的な考え方をまとめると、4つの重要性が挙げられる。まず、(1)立地・距離・輸送費などの空間的要素、次に(2)ホームマーケットエフェクトによる企業レベルでの規模の経済、さらに(3)多様性、そして(4)歴史のロックイン効果だ。
輸送費の低減とIT の発展の影響
それでは、空間経済学における輸送費の低減とはどういうことか。広い意味での人・物・金・情報の輸送費は非常に下がっている。ITの発展でみんながどこからでも携帯電話で話ができる世の中になったら、1カ所に集まる必要はないのではないか、それは都市や集積の死をもたらすのではないかとよく言われる。ただ、輸送費の低減の効果は単純なものではなく、逆U字型のものである。
輸送費を横軸、活動の集積度を縦軸に取ってグラフにすると、輸送費が非常に高いときは、1カ所でたくさんつくっても輸出できないので分散せざるを得ず、地産地消のような形になる。たとえば日本で戦後すぐ、復興のために日本中で鉄鋼が必要となったが、輸送網がずたずたに破れていたため、室蘭や釜石など日本各地で鉄鋼をつくっていた。しかし鉄鋼には規模の経済が重要なので、輸送網が整備されてくると、今度は東京や名古屋、大阪など大都市近辺でつくられることになった。その中でも八幡はレールに特化した。そのように、輸送費が安くなると、需要の大きい地域で集中的につくり、ほかの地域に輸出するようになる。集まりすぎると今度は高い賃金や地価を避けて分散することにもなるのだが、輸送費が十分に低下して初めて大きな集積ができるということである。
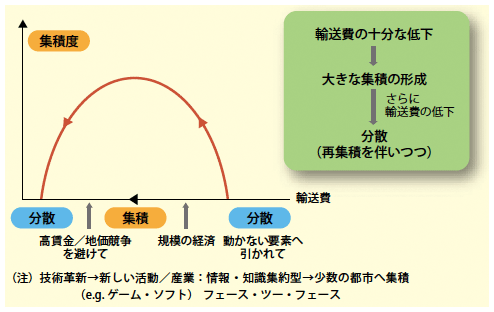
さらに輸送費が低下すると、再集積を伴いながら分散する。ただ、既存の集積が空になるわけではない。情報・知識集約型産業ではフェース・ツー・フェースのコミュニケーションが不可欠であるため、また都市に集まることになる。
もう1つ空間経済学で面白いのはストロー効果だ。マーケットの大きさはそれぞれの財が性質に応じて持つ固有距離によって決まっている。たとえば、あまり差別化の進んでいない財である普通の衣料品店や食料品店は大都市にもあるし、小さな間隔でたくさんのエリアに分かれている。それがファッション衣料品や高級レストランになると、より大きな商圏を持っている。さらにギャル産業や国際金融のように非常に差別化された財は、一度東京に集まるとなかなか他のところにはできず、日本全体が1つの商圏になる。ここで重要なのは、新幹線や飛行機などの輸送技術や情報通信技術の発達により輸送費が下がると、この固有距離はずっと大きくなるということだ。
ストロー効果で典型的なのは大阪である。1964年に東京・大阪間に新幹線が開通した際、大阪は産業構造を転換できなかったために本社活動の多くが東京に移ってしまった。東京・大阪間の往復に8時間かかる時は両方に本社が必要だったのだが、1日で往復できるとなると1カ所でよくなり、大きな方に集中するため、ストロー効果で大阪は大きな負の影響を受けた。これと同様に日本はストロー効果で中国などに製造業をすべて奪われるのではないかといわれている。輸送費が安くなったところで大きな集積を保つには、とにかく活動や集積の差別化を行わなければならない。いかに集積力を強くするかということは、いかに独自の差別化した活動を持っているかということである。
グローバル化と世界経済の成長
次に、グローバル化と世界経済の成長について空間経済学の視点から見ていきたい。世界経済システムの改革のエンジンは広い意味での輸送費の低減である。これによりグローバル化やローカル化が起き、世界経済全体が成長するとともに、世界経済地図に大きな構造変化が起こっている。
通商白書によると、1930年以降、長期的には輸送費はどんどん下がっている。ただ、下がってはいるがまだ高いということで、「Journal of Economic Literature」でAnderson とWincoopが「Trade costs, broadly defined, are large!」と言っている。中国でつくられた典型的なおもちゃがアメリカで実際に消費者の手に入るまでに、生産コストに対して平均170%値段が上がっている。つまり生産コストの1.7倍が広い意味での輸送費ということだ。これは平均で、たとえば天津の伊勢丹では青森リンゴ「世界一」が1個2100円で売られている。青森ではせいぜい300円だ。生鮮食料品ということもあるだろうが、7倍でも売れるのは、他の国や地域ではつくれない、非常に差別化が進んでいるということが大きい。もう1つ、中国の1人当たりGDPは日本の10分の1だが、格差社会なので富裕層がたくさんいるということも理由として挙げられる。このように、差別化された製品は世界の市場に供給でき、少々の輸送費は吸収させることができる。ただし、非常に差別化されていなければいけない。
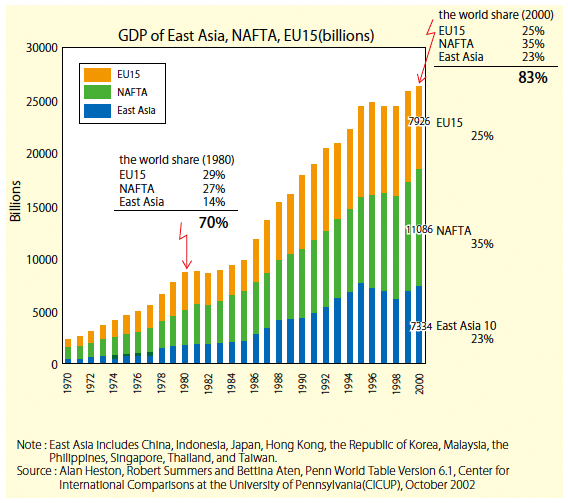
輸送費がある程度安くなると大きな集積ができるということが空間経済学の1つの命題だが、世界全体を見ると、どこに経済活動が集まっているのだろうか。東アジア、北米自由貿易協定(NAFTA)、EU15で見てみると、1980年には世界のGDPのうちEU15が29%、NAFTAが27%、東アジアが14%を占め、合計で70%だった。その後20年の間に情報通信革命による輸送費の低下により、EU15の割合は相対的にはやや小さくなったが、NAFTAは大きくなり、東アジアはほぼ倍になって、合計で83%になっている。つまり、世界の経済活動がこの大きな3つの地域にさらに集積しているということだ。集積だけでなく、世界GDPの成長率も年平均3%と歴史的にも非常に高く、輸出の成長率も5.7%である。特に2000年からの世界GDPの年平均成長率6.4%というのは完全にバブル的な成長だが、今後3%ぐらいを持続できればノーマルといえるだろう。
この高い成長は、非常に大きな2つの集積ができたことによって実現した。ヨーロッパはもともと大きな集積だが、どちらかといえば自給自足的な面が大きい。世界レベルでいうと、東アジアが世界の製造拠点として発展したことと、アメリカが最終的な金融拠点・世界最大の資産市場として発展したことが大きい。東アジアは世界の工場として物をつくって金を儲けるわけだが、その資金は東アジアでは使われずに資産市場に投資され、最終的にアメリカに流れたことが、アメリカの大きなバブルの原因になった。これにより、持続不可能なグローバル不均衡が生まれ、現在の状態になったのである。
東アジアにおける経済成長と地域経済システムの発展
東アジアが世界の工場・製造拠点になるまでのプロセスを見てみると、1990年代初めまではアジアは雁行形態(フライングギース)型の発展を遂げた。それがDe-facto Integrationとなり、多核的ネットワーク型経済システムを形成し、世界の製造拠点として発展した。たとえば1950~1960年には日本に繊維などの労働集約産業があったが、それが近くの韓国、台湾、香港、シンガポールに広がり、ASEAN諸国に広がり、1990年代にはさらに中国、インドに広がり、フライングギースではなく横並びのような形になってきた。一般的なプロセスとしては、輸送費の低減によって、確立した技術に基づく活動は安いコストを求めて分散する。しかし均等に分散するのではなく、再集積を伴いながら分散していく。その一方で日本が空になるわけではなく、知識創造活動は知識外部性が大きいので特定の大都市に集まる。そういう形でアジア全体が1990年代以降、主要都市・産業集積を中心として多核的なネットワークを形成し、補完的な関係を持つ経済圏に大きく発展したということだ。これが第2回セミナーで青木初代所長が説明したフライングギース・バージョン2.0である。
世界の工場である東アジアに製造業が集まっている。2008年の数字では、自動車の生産の38.9%を東アジア(うち日本16.4%、中国13.3%)が占め、NAFTAやEUよりもはるかにプロダクションシェアが大きい。同様に、化学繊維は67%(うち中国60%)、携帯電話は71%(うち中国51%、インド12.3%)、DVDレコーダー・プレーヤーは96%(うち中国71%)、パソコンは、デザインや研究・開発は別として99.8%(うち中国96%)を製造している。HDDは100%だが、中国よりタイの方がはるかに割合が大きく、マレーシアやシンガポールも20%以上を占めるので、中国一極集中というわけではない。デジタルカメラも100%で、日本も結構頑張っている。アジア、特に中国が世界の工場になったということが数字的にも表れている。
ただ、この集積の経済を背景にアジア全体が成長する一方で、非常に大きな格差が生まれている。たとえば1人当たりGDPはシンガポールが最も高く、ミャンマーと比べると100倍以上の格差となる。これは持続可能とは考えにくいので、いわゆるインクルーシブな地域成長、ボトムアップ型の地域協力が今から必要となる。
中国に注目すると、まずその特徴の1つは13億人という人口である。世界第5位の日本の人口の10倍の国がすぐそばにあるということだ。たとえば上海の人口が約2000万人で、南の浙江省と北の江蘇省を合わせると、日本と同じ約1億3000万人となる。それが10個分あるので労働力としても膨大であり、その賃金が上がって巨大な市場になっている。
もう1つの特徴は、都市化率がまだ50%程度ということで、非常に大きな可能性を持っている。経済の生産性の上昇は少なくとも最初は集積によって生まれ、都市化と同時に進行し、農業から製造業、サービス業に集積しながら転化していく。中国の都市化率も、あと20年もたてば75%程度になるだろう。
中国は1990年代半ばから急速に発展してきたが、若い人が出て行った所は取り残されるために格差が生じる。経済成長、集積、格差は、少なくとも最初に急速に発展するときは同時に進行する。実際に2006年の1人当たりGDPを地域別に見ると、上海と貴州省ではおよそ10倍の格差がある。この格差是正に向けて中国全体で努力しており、その方策の1つが、内陸部まで交通網を発展させる計画だ。日本の新幹線は東京・大阪間が1964年のオリンピックのときに開通してから45年近く経っている。現在の総延長は青森から鹿児島までおよそ2000kmだ。中国では今のところ上海周辺と北京周辺だけなのでまだ1000kmにも達していないと思うが、今年6月には北京と上海を結ぶ約1400kmが開通する。2020年までに2万kmの新幹線網を完成させる計画だが、計画を前倒しして、2万kmよりもさらに延びる形で進んでいる。東京駅の新幹線ホームには座る場所が全然ないが、北京駅の新幹線ホームは広い待合スペースに多くの椅子が並べられ空港かと思うほどだ。中国新幹線は当初の計画では日本のやまびこ号を買う予定だったが、中国では時速350kmを計画していたため、時速290km程度しか出ない日本の新幹線ではなく、ドイツのシーメンスから買って復製した。中国はそれだけの技術力を持っているということだ。車内では客室乗務員がお茶を配り、北京・天津間の150kmという短い区間でもあっという間に時速330kmに達する。
これは、後発国が最先端の技術を大規模に導入して先進国を跳び越すことができるという、開発経済学で言うリープフロッグ・ディベロップメントの典型的な例である。日本も戦後はこれをやったのだが、中国もそのうちほかの国にリープフロッグされる可能性もある。そのように大きく変化しながら世界は発展していくということである。
均衡発展に向けての世界と東アジア経済の再構築
現在、東アジア全体のGDPは既にアメリカを抜き、ユーロ圏をはるかにしのぐ。もちろんこれは中国の影響が大きく、国際通貨基金(IMF)の将来予測でも中国は急速に成長するとされているので、ゆくゆくは東アジア全体が世界で大きなGDPを占め、最大の市場になるということだ。
しかし、こうした予測には何の保証もなく、これからの発展のためには、東アジア域内においても、また世界全体においても経済を均衡型に大きく再構築しなければいけない。再構築するときに重要なのはグローバル化、脱国境で、その際に製造業に注目するのは当然である。また、世界がBrain Power Society、知識創造活動中心の社会になってきている。たとえば東京の中心的な活動は、ギャル産業革命やサービス業も含めて、狭い意味での製造業というよりも、もっと広い意味での知識創造である。この両方のバランスが図られなければいけない。つまり、現在世界的製造拠点である東アジアの将来を考える上では、新しい制度構築と知のルネサンスの両者を達成する必要があり、そのためには効率的な生産・交通ネットワークだけではなく、Brain-Power Networkを構築していかなければいけない。これを通じてさらに先端的な世界的製造拠点に進化すると同時に、大きな世界の市場になり、世界的な創造拠点にもなるのである。それで初めてヨーロッパ、アメリカに次ぐ第3の核となることができ、世界全体も均衡した形で成長できるだろう。
そのような創造拠点になるべく、アジア各国でさまざまなイノベーション活動が意図的に進められている。こうした中、日本の研究開発費の対GDP比は、1985年以降、主要国中でずっとトップである。これは非常に重要なことで、自信を喪失している日本だが、アジアから見ると技術力を非常に持っており、それを支えているのが大きな研究開発投資だ。ただ、投資の大部分は民間によるもので、政府の投資がGDP全体に占める割合を0.75%から1%に上げると言っている程度である。一方で韓国が急速に追い付いてきており、2010年には日本と同じぐらいになるかもしれない。また中国も急速にGDP比率を上げてきている。この統計には入っていない軍事関連の研究開発費も加えれば、恐らく中国やアメリカは日本と同じぐらいのGDP比になるのではないか。
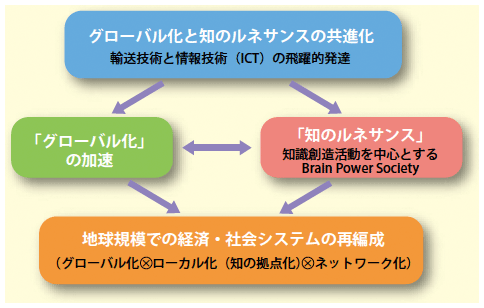
研究開発全体では、日本はアジアの最先端にいるが、特許の公開件数を見ると、環境分野では中国がアメリカや日本を抜いて世界のトップである。生命科学分野での特許の公開はアメリカがトップで、日本と欧州が同じぐらいだが、中国もすでに追い付いてきていており、韓国も非常に頑張っている。
このように各国・地域において研究開発が活発に行われ、広い意味での知のルネサンスが起こりつつあるが、東アジア内部における知のネットワークは、ヨーロッパやアメリカに比べてまだ非常に弱い。特許を取る場合は関連する特許をすべてサイテーション(引用)しなければならないが、世界銀行の資料によると、東アジアにおける特許の引用の相手国としては、日本も多いが圧倒的にアメリカが多く、日本を除くアジア内部が非常に少ない。知のハブとしての役割は、現時点では圧倒的な強さでアメリカが担っている。ただ、エレクトロニクス分野ではアメリカよりもアジア内部の相互引用が多いことから、特定分野ではアジアの知のネットワークができているといえる。アジア全体が、アメリカ、ヨーロッパに相当する第3の世界的創造拠点になるためには、やはりBrain-Power Networkを構築していくことが1つの大きな課題だ。それを通じて、アジア全体の多様な頭脳集団が知のルネサンスを起こすのである。
地域創造社会における多様性と文化
アジア全体、あるいは日本全体を知識創造社会にしていくためには、空間経済学自体もさらに包括的なものにしなければいけない。1990年代からできたNew Economic Geographyの中心はエコノミックリンケージ(E-linkages: linkages through the production and transaction of traditional goods and services)であり、もちろん普通の財の生産も重要であるが、現在は、ナレッジを通じてのリンケージ(K-linkages: linkages through the creation and transfer of "knowledge," ideas, information)、広い意味でのナレッジの生産とその連携が非常に大きな比重を占めてきている。空間経済学をより包括的にするには、こうした連携部分の理論を本格的に強化し、実証研究も行わなければいけない。
空間経済学において、集積ができ、生産性が上がる根本は多様性であるわけだが、知識創造社会で最も中心的な資源は、われわれ1人1人の頭脳(brain)である。このbrainはソフトウエアと同じで、同じものが複数あっても相乗効果は出ない。多様な頭脳、互いに差異化された知識を持った人材が集まることで相乗効果が生まれる。昔から「3人寄れば文殊の智慧」といわれているが、これは2人の場合でも同様である。もちろん、ある程度の共通知識がなければコミュニケーションが取れず、協力もできない。しかし、すべてが共通知識では協力する意味がない。従って、それぞれの固有知識と共通知識のバランスが不可欠なのである。
この「3人寄れば文殊の智慧」は重要な格言ではあるが、長期的にも本当であろうか。同じ3人がいつまでも共同で論文を書いていると、共通知識がどんどん肥大化して相対的に固有知識が縮小し、だんだん相乗効果がなくなるという現象がある。これは日本の企業や研究所の内部でも起こっていることだ。いつまでも同じメンバーで研究していると、「3年寄ればただの智慧」になってしまうのである。従って、知識労働者の一極集中には二律背反の効果がある。
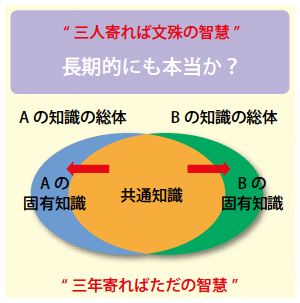
たとえば日本では明治維新以来、東京に多様なバックグラウンドを持った知識労働者の大部分が集まって、密なコミュニケーションの下で相乗効果が増大し、それが短期的には日本の成長力の大きな源泉になった。しかし1980年代には、集まるだけの人が東京に集まってしまった。さらに情報通信技術の革命でテレビも新聞も全国版はすべて東京から発信されるようになった。日本人全員が同じテレビや新聞を見ることになると、共通知識が肥大化して金太郎飴のようになって相乗効果は無くなっていく。これを防ぐには意図的に多様な組織・地域を育成し、相互間の知の交流と人材の移動を行わなければならない。
今、日本が元気がない1つの理由として、平均的なイノベーション力がアメリカに比べて劣っているという点が挙げられるかと思う。長岡貞男FF(一橋大学)は、日本で先端的なパテントを取った3000人と、アメリカでパテントを取った同数の人に克明なアンケート調査を行っているが、そこで明らかになった日米の大きな相違点は、アメリカにおける発明者の非常に高いモビリティーである。パテントを取った人のうち、アメリカでは25.7%、特にバイオでは45%が過去5年間に企業や大学を移動しており、日本は4.6%とほとんど移動していない。また、外国生まれの発明者のシェアがアメリカでは30%だが、日本はゼロに近い。それからアメリカではフロンティア型の研究が非常に大きく、意図せず驚くべき結果が多く出たのに対し、日本では意図したとおりの結果が出る研究が大部分である。さらにアメリカでは発明者のうち45%が博士号を持っているが、日本では12%にとどまっている。これは企業の内部で研究者を育てているということだ。今まではそれでよかったかもしれないが、流動性が非常に低い点は変える必要がある。
日本は旧来の同質性重視(改善型)のイノベーションシステムのロックイン効果を解いて、新たなナレッジの生産システムへ移行し、異質性重視(発見型)のイノベーションシステムを強くしていかなければいけない。そのためには組織を越えた協力関係を強め、メンバーを組織間でゆっくり入れ替え、新たな人材を吸収することが必要だ。また、地域の問題、すなわち一極集中を乗り越えて、もっと多様な地域の文化を強くする必要がある。
この文化(独自の知の集積)と創造性の関係について、対照的な二地域のケースを用いて説明したい。たとえば一極集中の代わりに西と東に対称性を持った独自の知の集積があるとする。もちろんそれぞれの地域内では非常に密な交流をしているわけで、地域内でそれぞれの代表的な2人の知識を取れば、もちろん共通知識が非常に大きい。ただ、コミュニケーションにはコストも掛かるので、違った地域から代表的な2人の知識を取ってみると、共通知識はずっと小さくなる。この違いが文化ということになる。もちろん改善型の研究は密なコミュニケーションの下に各地域で行っていけばよいが、バイオのように知のフロンティア型の研究では知の多様性が重要であり、両地域から人材を集めて大きなチームをつくって行うと、研究開発能力が大きく増す可能性が出てくる。これについては間もなく「Culture and Diversity in Knowledge Creation」という論文をRIETIのディスカッションペーパーにするので詳しく見ていただきたい。
1つの地域で研究を行い、協力やコミュニケーションにコストが全くかからない場合と、2つの地域に分けて研究を行い、協力にも知のフローにもコストがかかるが、代わりに多様性が増す場合とでは、地域全体としての知識の成長率が後者は前者の3倍近くになる可能性がある。こうしたことからも知の多様性は非常に重要だと考えている。
グローバル化と知の時代における日本再生
日本では「失われた20年」といわれるが、20年の停滞は本当は歴史的に見ても大したことではない。中国は200年の停滞があったし、ギリシャは2000年の停滞からまだ抜け出していない。
日本は戦後初期に朝鮮戦争をきっかけとして高度成長を遂げ、ニクソンショックやオイルショックも勢いで乗り越えた。ハイテク産業に構造転換し、1980年代末には「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われるところまで成長した。しかしバブルがはじけて、1990年からは大きな雪玉が谷底に止まったような形で身動きできなくなっている。いわゆる大量生産に基づく資本主義経済の下では、アメリカやヨーロッパから最先端の技術をもってきて改良すれば良かったので、日本は現在の中国と同じようにリープフロッグ型でどんどん成長し、1993年には1人当たりGDPで世界でトップに立った。そうなれば、次は自らフロンティアを開拓し、本当のBrain Power Societyにならなければいけないのだが、ネガティブなロックイン効果が働いて構造変化を十分に達成できていない。日本の1人当たりGDPは、1970年には経済協力開発機構(OECD)内で18位だったものが、1993年には2位、統計年の為替レートによっては1位となった。しかし、その後、急速に順位が落ち、2008年では19位である。これは単純な為替の変化だけでは説明できない。やはり大きな構造的な要因があるということだ。
2008年の1人当たりGDPは、ルクセンブルグが世界トップに立ち、日本の3倍になっている。このときのトップ10は、ルクセンブルク、ノルウェー、スイス、デンマーク、アイルランド、オランダ、アイスランド、スウェーデン、フィンランド、オーストリアと、ヨーロッパの小さな国ばかりで、人口をすべて合わせても6300万人と日本の半分だ。さらにフィンランドのヘルシンキからオランダまでの距離は北海道・沖縄間よりも短く、比較的小さな領域に多様な小さな国々が集まっている。ここで重要なのは、独立した言語と文化を持つ独立国家が、それぞれの政策を通じて独自の文化を持ち、非常に高度なナレッジソサエティーを達成しているということだ。これは日本の将来に参考になるだろう。
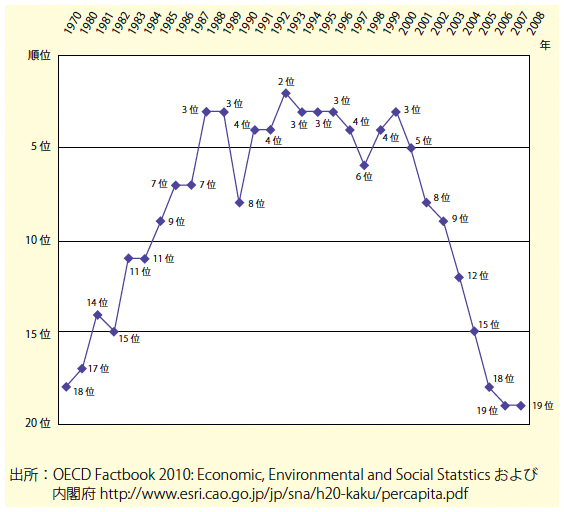
知の時代に日本が再び世界のリーダーの1つとして活躍するためには、ほかの国と棲み分けた形で、世界的なイノベーションの場、知識創造のハブになる必要がある。そのために重要なのは、あらゆるものの多様性と自律性である。人間・人材から各企業、大学、都市・地域まで、多様性と自律性をもっと強く取り戻さなければいけない。特に人材と地域については、知の時代に相応しく多様性を強化しなければいけない。
これは全く私の個人的な意見だが、将来の地域政策は、自律的な地方分権システムを通じた競争と共生が基本となる。明治維新の廃藩置県により、東京を中心とする強力な中央集権国家が成立して、20~30年前まではうまくいっていた。しかしこれが今後も適した形であり続けるとは必ずしもいえない。そのアンチテーゼとして、私は中央中心ではなくてもっと多様な地域をつくって自律的な地方分権システムにしようという意味で、「平成維新」「廃央創域」を提案している。
廃藩置県による中央集権国家には良い面も悪い面もあった。良い面としては、全体として見れば欧米の工業化社会にキャッチアップするために非常によく機能したということがある。これは現在の中国共産党のシステムとよく似ている。しかし、社会の多くの側面において多様性と自律性が失われていった。たとえば、「知識とは最先端を取って正しいものを覚えるものである」という義務教育や記憶中心の受験競争は個性と独創性を奪い、また中央による地方行政の従属化が地域の自律性を奪い、一極集中によって共有知識が肥大化し、金太郎飴になってしまった。これを中央中心ではなく、もっと多様な、小さな単位の地域を中心として、それぞれが独自の産業・知的クラスター、知能・文化の集積をもって、それらの間の競争・共生で日本中に知のルネサンスを巻き起こしてイノベーションの場として発展していくのがよいのではないか。これが私の提案である。
そのための地域政策の基本は、それぞれの地域が持つ資源を最大限に活用していくことと、新しい血と知を導入していくことである。それを通じて、住んでいる全員がわくわく楽しい、持続的なイノベーションの起こる、地域独自の環境・文化と仕組みづくりを行う。そして、多様な地域が出てくるための仕組みづくりをすることが国の役目である。
各地域が抱える1つの大きな課題は、多様な人材をどのようにして育てるか、あるいは世界中・日本中から集めるかということだ。人材は待っていても集まらない。人間の多様性と、多様性・異端者への包容力は共に進化していくものであり、意図的な努力が必要である。従って、これからの地域における非常に大きな課題は、積極的で具体的な施策を通じた、広い意味での異端者への包容力の促進である。異端者とは、社会の中心部、特に知識創造社会の中枢部に入っていない人々のことだが、その人々にもっと中心に入ってもらい、活躍してもらうということである。
典型的な例として、まずは在日外国人が挙げられる。お客さんとして来てもらう際は日本は非常に親切だが、実際には公務員になるのも大学の教員になるのもなかなか難しく、外国人労働者も非常にひどい扱いをされている。それから学歴軌道から外れた若者、そしてPh.D.を取るなど学歴軌道に乗り過ぎた若者も、企業や役所にはなかなか入れてもらえないということがある。さらには社会で活躍したい中高年者、ハンディキャップを持つ人々等が挙げられるが、特に日本社会が遅れているのが女性への包容力だ。たとえば日本に99ある国立大学のうち、女性が学長になっているのはたった2校だ。アメリカのアイビーリーグでは8校のうちハーバードやペンシルバニアを含めた4校の学長が女性だ。アメリカ、そして北欧も同様だが、こうした知識創造活動においては性差は全くなく、誰もが中枢部で活躍している。
これは逆に言えば、日本には、これから外国人や女性にどんどん中枢で活躍してもらえば発展する非常に大きな余地があるということだ。しかし熟練外国人労働者の比率を見ても、アメリカや北欧の6%に対して日本は1%未満である。日本が人材の活用、人間の多様性という点で大きく発展するためには、先ほどの施策を意図的に行わなければいけない。
アジアで人材の多様性を一番活用している国はシンガポールだ。1人当たりGDPでアジアトップのシンガポールは、異端者への包容力、国際化という点でも非常に努力している。少し前まで「Far Eastern Economic Review」という雑誌があり、そこに「Gay Asia:Tolerance Pays」という面白い記事があったのでご紹介したい。毎年、夏のナショナルデーに世界中からおよそ8千人のゲイがシンガポールに集まる。ほとんど裸になって夜中じゅうダンスを踊るというワイルドなもので、10年前のシンガポールでは考えられなかったことだ。当時は非常に中央集権的で規制が強く、チューインガムを持っていたら、「おまえはチューインガムを持っている。これをかむだろう。かんだら道路に捨てるだろう。だから逮捕だ」と、かむ前に逮捕されるような国だった。しかし今は非常にオープンになり、異端者をどんどん受け入れようという、広い意味での包容力を意図的につくっている。逆に言えば、日本の各地域がシンガポールと同じように国際化を進め、地域の活性化を独自に行うとよいのではないだろうか。
全員参加による地域活性化―多様なアプローチ
あらゆる地域が、多様なアプローチで全員参加によって地域活性化を図る必要がある。教育・研究・人材育成に取り組み、さらに強い科学技術立国にしていくことはもちろんのこと、製造業ではますます先端的な研究開発を進めなければいけないし、農業やサービス業にも大きな発展の余地がある。これはハードだけではなく、ソフトも含まれる。さらに、芸術・芸能・文化によって初めて世の中が楽しくなる。やはりこれら全体としての三位一体の形が大切である。私は、東京だけでなく地方も含めて、「Innovation Everywhere with Everybody」だと考えている。
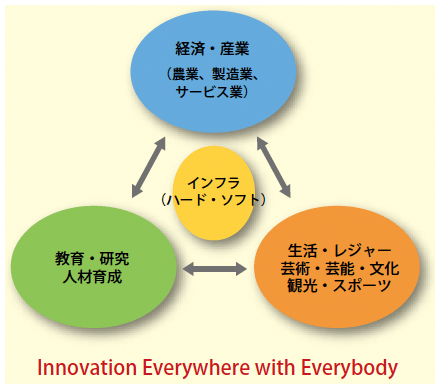
ここで注意しなければいけないのは、日本ではどちらかといえば公平性が重視され、たとえば高齢者、中小企業、女性、地方、農業などを保護しなければならないという考え方が基本的に強い点だ。これを改め、新しいシステムをつくって全員に社会革新の主役になってもらわないことには日本はもたない。大きな日の丸を少ない若者が背負っていくのは到底不可能である。韓国も中国も急速な高齢化を迎えることになるが、日本がその先陣を切る。日本は新たな形の高齢化社会に向け、新しいビジネスイノベーションによって全員主役のビジネスモデル、社会システムをつくっていかなければいけない。
実際に日本各地でそうしたイノベーションが起こっている。東京のギャル産業革命はヤングギャルを中心としたファッション革命だが、農村ではシニアレディを中心に高齢者が農村革命を起こしている。
人口約2000人の徳島県上勝町は、葉っぱをお札に変えた町として有名だ。徳島市から四国の山中に向かって2時間ほど行ったところにあるこの町では、いろいろな面白い活動が行われている。その1つが「いろどり事業」だ。事業内容は、たとえば高級日本料亭などで吸い物に使う桜の枝や、刺身のつまものに使うカエデなどの飾りを季節ごとに400種類つくって全国90の都市に出荷するというものだ。1980年に大雪が降り、それまでの収入源だったみかんの木が全滅した。もちろん谷底でつくる米などの生産は非常に小規模で、農家一戸当たりの現金収入は年間20万円ほどだった。どうしたらいいかと悩んだ末、1986年から横石知二氏が4人の主婦と始めたのが「いろどり事業」である。葉っぱをつまものにして売ることは誰でもできると思うが、誰もしなかったのだから、非常に大きなイノベーションである。
横石氏がこれを思い付いてみんなに言ったとき、典型的な2つの反応があった。1つは「葉っぱを集めてお金になるのだったら、北海道から沖縄まで日本中、金持ちになるではないか。そんなことでお金がもうかるはずがない」という意見、もう1つは「葉っぱを売ってお金をもらうなんて、そんなみっともないことができるか」という意見だ。それでも横石氏は、絶対にうまくいくという確信の下、半年かかってみんなを説き伏せた。現在は農家の人が150人参加している。女性が大部分だが、平均年齢67歳、最高齢者は95歳だ。参加者1人当たりの平均年収は170万円で、それほど大きくないと思うかもしれないが、ほとんどは夫婦で行っている。そうすると1戸当たりの現金収入は340万円になり、この事業を始める前の15倍以上になる。
この事業には20年の間に培われたノウハウが圧倒的に詰まっており、情報通信技術も駆使して行われている。全員が各々の田んぼで苗木をつくって葉を摘み、出荷しているので、それぞれが社長であり、労働者だ。さらに市場直結といっても、自分が今持っている桜の苗木の花を明日どれだけ出荷するかは、90都市の過去1カ月の市場価格の動きと将来1カ月の市場予測がないと決定できない。それは市役所の情報を基にコンピューターでみんなが判断する。コンピューターネットワークの開発を支援したのは経済産業省で、年を取った人にも使いやすい、テニスボールぐらいの大きさのマウスもつくられて、これで売上が一気に倍以上に増えた。情報を元に出荷量を決定し、パックして4時までに農協に持っていくと、徳島空港から全国90カ所に送られる。新しい商品をみんなが開発しているのだ。
上勝町は今、「笑い顔の町」と言われている。みんなが自然の中で生きて、ある程度現金収入が入るのもうれしいことだが、重要なことは市場直結で社会の中に入っていき、それも非常に環境のいいところで活躍しているということだ。人口2092人のうち、IターンやUターンの人が6.3%いる。希望者はもっとたくさんいるのだが、土地が必要になるため、どんどん入れるわけにもいかないようだ。上勝町の高齢化率は徳島県で第1位だが、寝たきりの方は現在1人もいない。1人当たりの年間医療費(国民健康保険)は26万円である。上勝町の次に高齢化率が高く、特別な活動をしていない地域では1人当たりの医療費が46万円なので、20万円という圧倒的な違いがある。
また、いろどり以外にもさまざまな活動がある。たとえば月に1回ぐらい町長がみんなを集めて「一休運動」という、新しいアイデアを出す競争をしているが、それはアイデアを出したら終わりではなくて、どのように具体化したかを3カ月後に報告し、それにまた意見を出してどんどん改良するという形で全員が参加している。みんなが笑い顔で非常に元気に活躍し、現金収入が入り、医療費が非常に低いという町である。このような形で新しいビジネスモデルを日本全体につくっていき、中国や韓国にも一緒になって取り組んでいただいたらよいだろう。「Innovation Everywhere with Everybody」となることが重要である。
オープンで多様性の豊かな創造立国へ
日本は今、一極集中の中央集権国家で非常に元気がない。そこから脱却するための方法の1つが、脱国境だ。菅首相も「平成の開国」とおっしゃっている。持続的にアジア・世界との一体化を進める。また、日本の集積力を保つには人材と地域の多様性が不可欠である。脱中央による「廃央創域」で、日本が全員参加のイノベーションの場として世界と一体化する。このような形で、日本がオープンで多様性の豊かな創造立国になればというのが私の考えである。
この議事録はRIETI編集部の責任でまとめたものです。

