| 開催日 | 2011年1月11日 |
|---|---|
| スピーカー | 青木 昌彦 (RIETI初代所長/スタンフォード大学名誉教授/東京財団特別上席研究員) |
| ダウンロード/関連リンク |
議事録
 今日はフライングギース(雁行形態)パラダイムのバージョン2.0について解説したい。日本がV字型の雁の飛行形態の先頭に立ち、その技術が次々と後続の雁に移転されていくという、フライングギースパラダイムは、もともと1930年の初めに赤松要氏がオリジナルのペーパーを書かれて、1960年代には大来佐武郎氏などが中心となり、特に発展途上経済のコミュニティでは国際的にも非常に有力なパラダイムとなった。それをバージョン1.0と呼ぶとする。ところが、1930年代には最後尾にいた中国という雁が非常に大きくなり、隊列が乱れてきた。バージョン2.0では、これを単なる技術革新のモデルとしてではなく、人口、経済、技術、それと共進化するものとしての制度の複合的な進化をみようとしている。そうした複合的な進化に焦点を当てると、実は日本、中国、韓国の間には共通性、差異性、連結性があり、そこに戦略的補完の可能性もあることが分かる。
今日はフライングギース(雁行形態)パラダイムのバージョン2.0について解説したい。日本がV字型の雁の飛行形態の先頭に立ち、その技術が次々と後続の雁に移転されていくという、フライングギースパラダイムは、もともと1930年の初めに赤松要氏がオリジナルのペーパーを書かれて、1960年代には大来佐武郎氏などが中心となり、特に発展途上経済のコミュニティでは国際的にも非常に有力なパラダイムとなった。それをバージョン1.0と呼ぶとする。ところが、1930年代には最後尾にいた中国という雁が非常に大きくなり、隊列が乱れてきた。バージョン2.0では、これを単なる技術革新のモデルとしてではなく、人口、経済、技術、それと共進化するものとしての制度の複合的な進化をみようとしている。そうした複合的な進化に焦点を当てると、実は日本、中国、韓国の間には共通性、差異性、連結性があり、そこに戦略的補完の可能性もあることが分かる。
東アジア経済圏の興隆
昨年、中国が名目GDPで日本を追い抜いたということが騒がれたが、アンガス・マディソン氏の長期にわたる歴史研究によると、19世紀半ばには、日本・インド・中国を含めたアジア経済圏のグローバルプロダクトにおけるシェアは購買力平価(PPP)ベースで50%以上あった。ところが、19世紀末から20世紀にかけてアメリカが大きく躍進し、20世紀の中国とインドの停滞、日本の敗戦を経て、1950年には東アジア経済のGDPのシェアは約10%に落ちてしまったといわれている。
さらにマディソン氏の研究では、1950年から1958年頃まで、GDPのサイズという点で中国は日本を超えていたが、中国の大躍進と文化大革命は、特に農業生産などに非常に大きな影響を与えた。最近、イギリスの学者が、地方の図書館などに残されているデータを綿密に検討して大躍進時代の影響について本を著したが、彼の計算によると、文化大革命で亡くなった人は従来いわれていた3000万人ではなく5000万人だという。そのように人口が急激に減ってGDPも非常に落ち込み、いわば中国の「失われた20年」が起こり、その時に日本が高度成長によって中国を追い抜いた。それがPPPベースで再逆転したのが、マディソン氏の推定では1990年代初期で、IMFや世界銀行の推定では2000年代初期ということになっている。IMFの計算では、PPPベースでGDPを比べると、中国は既に日本の2倍のGDPを持っており、さらに中国、日本、韓国、台湾、香港、シンガポールという東アジア圏のGDPをPPPベースで総合すると、EUを超えて、アメリカ、カナダ、メキシコというNAFTAの経済圏に迫ろうとしていることが分かる。
GDPの規模が国力を表す1つの大きな指標であることは間違いないが、さまざまな厚生を考えると、1人当たりの所得がどう動くかということも非常に重要な問題だ。特に、労働人口が全体人口のうちに占める割合については、日本、韓国、中国には、ある点での共通性が認められる。
工業化の初期条件
ハリー・オーシマ氏や速水祐次郎氏の業績が示すように、資本主義経済(市場経済)が発展する前のモンスーン農業においては、小農経営の経済が圧倒的な重要性を持っていた。土地の所有と経営が合体している場合もあるし、 地主がいても実際の経営は借地小農という家族単位で行われていたということもある。その時代の小農と小農の間、あるいは小農と地主の間の土地の貸借契約がどのように実行されたかということが、実は日本、韓国、中国のその時代における制度の差を特徴付けていて、それがpath-dependent(経路依存的)な形で現在に至るまでいろいろな社会関係の規制や政治権力の在り方に影響を与えている。この3国が全く同じだと主張するつもりはないが、小農経済から出発して、どのように工業化、市場化、近代化が進むのかという点は共通しているといえる。工業化の初期条件としての農業就業者の比率は、日本が1887年に73%、韓国が1963年に63%、中国が1952年に83%であった。中国は1979年の改革開放が始まったときにもまだ70%台という数字だったことから、生産性の低い農業部門から生産性の高い工業部門への人口の流出が1人当たりGDPの成長の1つの要素として挙げられる。農業雇用のシェアとPPPベースでの1人当たりの所得から、日本・中国・韓国の成長経路を比較してみると、2008年の段階で、中国の沿岸地方は日本の1960年代の末期頃に当たる。RIETIの関志雄コンサルティングフェローはかなり以前から、電気の使用料や寿命、乳児死亡率といったさまざまな指標を比較し、今の中国の状況と1960年代の日本の状況が非常にマッチしていると指摘してきたが、私も自分で計算してみてそれが正しかったことを再確認した。
アーサー・ルイス氏の「無制限の労働供給」という理論によれば、過剰な労働力が農業から工業(農村から都市)に移転することによってGDPが増大してくる。現在の中国がルイスのターニングポイント、すなわち、生存賃金での労働の農業からの無制限供給が終わりに近づきつつあるのか、ということが経済学者の間で1つの大きな論争になっているが、私はこの理論には賛成ではない。デール・ジョルゲンソン氏も1960年代に既に指摘しているとおり、小農といっても合理的経済主体なのだから、都市に出て行くかどうかはきちんと経済計算を行うはずだ。私は、まだ四人組が支配していた中国を1975年、当時の日中農民交流協会という訪問団に加わって農村を見に行ったことがあるが、農村の人民公社の幹部 の人たちは、農民の資本主義への復帰、すなわち近隣の町や村へ行って商売をするという行動をどのように抑制するかが鍵だと話していた。農民というのは基本的にそういったインセンティブを持っているのである。
人口動態を見てみると、日本と中国を20年ずらすと全く同じような形態になる(図1)。中国も2010年に全人口に占める労働人口の比率がピークになった。65歳以上の非労働人口比率を見ると(図2)、日本は圧倒的に老齢化のスピードが速いが、韓国も急激に老齢化が進むことが分かる。中国では60歳定年制(女性は55歳)となっているので、人民大学のDu Peng氏が計算した60歳以上の非労働人口比率を見ると、日韓とは差があまり認められない。しかも、中国はデータの上では全人口出生率(TFR)を1.8として計算しているようだが、 最近、ある在米中国人研究者によると、実は中国のTFRは既に1.3まで落ちており、韓国並みになっていると指摘した。実際どうなっているかは昨年10月に行われた国勢調査の結果が出れば分かることだが、高齢化は中国においても深刻な問題であり、一人っ子政策の再検討が必要になりつつある。ところが、中国国内には一人っ子政策の遂行をモニタリングする育成委員会という強力な組織があり、政治的な既得権者として非常に重要な層となっているため、一人っ子政策の問題をオープンに議論することがまだタブーな状態にある。しかし、遅かれ早かれ大きな問題になるだろう。
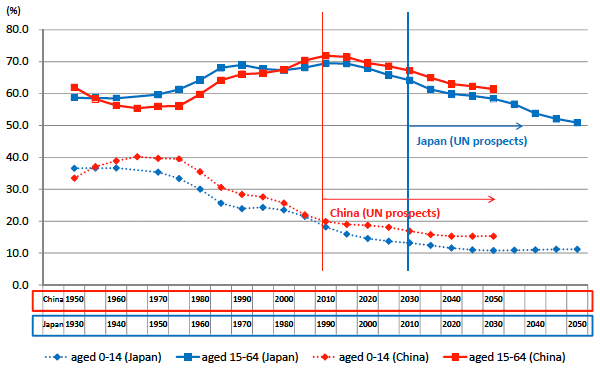
(65歳以上の人口比率):国連資料
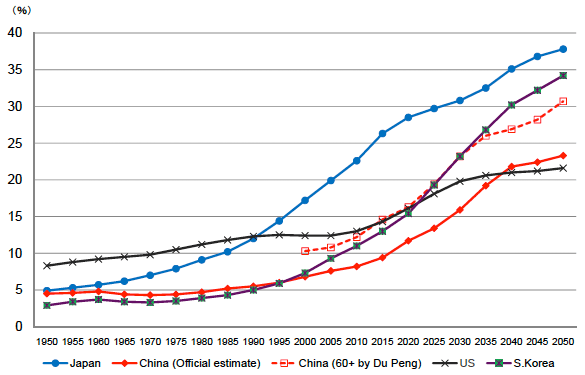
1人当たりの国民生産の決定要因
1人当たりの国民生産の決定要因は、人口がどう動いていくか、その中でも特に、労働力人口が非労働力人口(子どもや高齢者)との比率でどうなるかということが1つの重要な要素である。また、従来型の家族経営農業と工業やサービス業の生産性には差があるので、雇用の脱農業化と農業高度化に基づく構造変化の割合、さらに非農業部門における労働生産性という3つの要素に分解することができる。特に労働生産性の部分は、さらに資本労働比率の変化と全要素生産性(TFP)という2つの要素に分けられる。中国のキャピタルストックのデータは公表されていない。90年代に関しては、かなり研究が蓄積されているため、公表されていないデータを使うことができるが、2000年代に関してはまだTFPは計算できていない。
それらを会計的恒等式に基づいて整理すると、その背景にある動学的メカニズムを図示できる。その結果、日・韓・中には非常によく似たダイナミクスが現れる(図3)。高度成長の時代には、日本と韓国では1人当たりの国民所得が8%成長し、中国も8~9%成長という時期がある。こうした高度成長の時代には、農業から工業に労働力が流出していくことと労働人口の増加があわさって、労働生産性に匹敵するほどの効果がある。中国では、1980代、改革開放が始まった頃に農業から労働力が流出したことが圧倒的な重要性を持っていた。
(日本・韓国・中国)
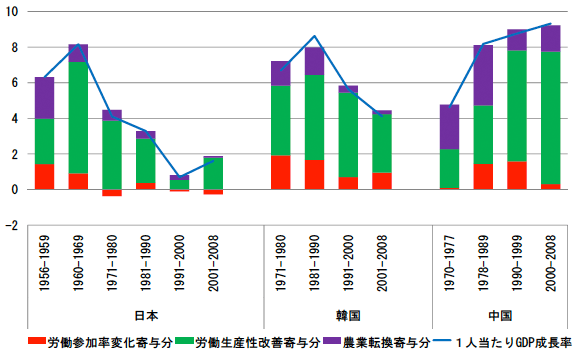
また、人口比率の影響を見ると、高度成長の前には出生率が上がっている。中国の場合、1958~1960年の大躍進政策の後に人口増大のブームが起こる。1960年代後半から1970年代前半の文革時代においても人口が増大し、1980年代に入ってから一人っ子政策に移行する。増大する新生児が15~22年も経つと、1人当たりの国民所得の成長率の源泉になっていく。これが人口統計学でpopulation dividendあるいはdemographic dividend(人口ボーナス)といわれるものだ。
この次の段階があるのは日本と韓国だが、これも非常によく似た姿を持っている。農業からの移転が減ってくるのだ。韓国の場合は1940年代から、日本の植民地化の影響もあり、20代の20%が外国に働きに出ていた。外国というのは満州と日本であった。そうした歴史的経緯もあって、韓国では農業からの流動化が早く一段落した。日本の70年代はオイルショックなどもあって労働調整が行われたために労働力人口比率のネガティブな影響が現れている。
次の段階になると、労働人口の寄与分のマイナス影響が増えてくる可能性がある。日本の場合今のところそれほど顕著に現れてはいないが、図3のゼロの横軸から下に伸びている部分が長くなっていく可能性が大きい。そうだとすると、1人当たりの国民所得を上げるためには、労働生産性をさらに向上させなければならない。また、農業と工業の間の生産性の格差を縮小する、つまり農業自体の高度化が、これに貢献する可能性もある。韓国は今は労働生産性が非常に高いが、老齢化が進むと日本型のパターンに進んでいく可能性があるのではないか。中国はまだその段階にないが、ルイスのターニングポイントということで議論されているような、 次のフェーズに向かっていくと影響がこれから現れてくると考えられる。
経済発展の諸フェーズ
以上から、経済発展のフェーズを次のように考えることができる。まず、前工業化段階では、自作農や小作農による零細自己経営農業が経済の中で圧倒的に優勢であった。
経済におけるさまざまな契約関係をどのように実行するかということが、政治権力の在り方や共同体規制の違いに現れてくる。過去20年ほどで、経済学の中でも制度分析が重要になってきたが、契約の実行がどのように行われているかということが焦点の1つだということが、ダグラス・ノース氏やアブナー・グライフ氏といった人々の貢献によって明らかにされた。彼らの関心は、都市における商業契約がどう実施されるか、特にそれが国家によるサードパーティー・エンフォースメントによってどう支えられるようになったかということが、近代化を測定する1つの大きなメルクマールになるという議論なのだが、私はこの東アジア経済においては、農業における土地貸借契約がいかに実施されてきたかということが1つの重要な要素になるのではないかと考える。
次のフェーズとして強力な政府が出てきて、マーケットメカニズムではなく税や農業価格のコントロールによって農業生産物価格と工業価格との格差を作り出し、農業から工業への資源移転を行うが、労働力の移転は抑制されるという初期工業化の時代がある。日本においても戦前はそうだった。林=プレスコット説によれば、日本の農村における田畑の長子相続によって19世紀末から戦後に至るまで農村労働力は1400万人という水準に保たれてきた。その結果、3分の1の労働生産性が失われたということである。中国の場合にも、大躍進の時代からそれに続く文化大革命の時代は、人民公社という組織化によって農業からの流出、あるいは農民の市場活動への参加を制限するという時代があった。
その次の段階は、農業からの人口流出を取り込んだプライベートな非農業部門の高度成長の時代である。さらに流出が続いて農業雇用のシェアが20%を下回ると、農業からの流出が1人当たりの国民所得を上げる要因としては取るに足らないものになってくるので、工業やサービス部門の自立的な労働生産性の増加を実現できるかどうかということがこの段階の課題になってくる。これが、日本が70~80年代に経験したことであり、韓国は90年代から2000年代にかけてこれを経験した。その次にいわゆる少子高齢化の時代がやってきて、1人当たりの国民所得の増大の持続性に対するチャレンジになる。
このようなわけで、これまでの技術移転の経済発展モデルとしては雁行形態パラダイムは成り立たないわけだが、人口動態の変化とそれに伴う経済成果や制度の変革という観点に立つと、日本は常にそうした変化を先取りしてきたということがいえる。そして現在は、近代史上未知の人口成熟化社会という危険に向かって飛行している。韓国も中国もその軌跡を遅からず追跡することになるという意味で、雁行形態パラダイムVer.2.0ということを語り得るだろう。
中国は、これから第2フェーズから第3フェーズに移ろうとしているわけだが、高度成長に伴い環境破壊やエネルギーの非効率性問題、都市農村間の所得格差、ユニバーサルな公共サービスの欠如という問題が出てきている。90年代から2000年代にかけて、農村の労働戸籍を持っている約2億人が都市に移住した。農民工というと短期の出稼ぎを想像しがちだが、こうして移転した2億人の平均年齢は非常に若い。流動人口の定義としては、制度上は農村に戸籍を持っているが実際には都市に6カ月以上住んでいる人たちを指す。北京ではそういった人たちの50%以上が家族を持っているが、彼らの子供が大学に行く資格を得ようとすると、戸籍が存在するところでしか得られないため、子どもの教育のために農民工が農村に回流していくという現象が最近は起きている。経済成長がそうした労働力に支えられてきたにもかかわらず、このような事態を招いている事が、現在、中国では大きな問題になっている。
中国では1990年代に税制改革が行われ、それまで存在しなかった中央の徴税の仕組みが出来上がった。その過程で、日本における「法人税」に当たる税の中央政府への配分割合が70%へと高められていった。税制改革前は州政府がこの税を徴収し、それを国と州でどう分配するかは一種のネゴで決まっていたが、これを制度化し、かつ中央政府そのものが徴税機能を果たすという改革が90年代に行われた。こうした税制改革は、中国全体で統一した市場経済をつくっていくという意味ではもちろん正しいが、地方政府の財政ベースを弱めてしまった。一方で、憲法上は教育や健康保険、年金は地方政府の義務になっているというため、財政改革による徴税ベースの中央集権化によって財政収入の緊迫した地方政府が考え出したのが、農地を開発して開発差益を得るという政策だった。
2007年、中国で土地の物権法が制定された。土地の所有権は依然として農村共同体にあるが、農民は30年という期限付きで土地請負経営権を借り受け、その譲渡・転貸は可能ということになった。中央政府が農地の割合を減らさないように規制をかけてくる一方で、地方政府は農民から一種の強制収用のような形で請負権を買い取り、開発業者と結託して50~70年の賃借権つきの都市住宅・商業用地に転換し、開発差益の約40%を得ている。一昨年の中国の財政収入の22%はそうした土地の開発差益だといわれている。こうした背景から、中国では戸籍制度と土地のバブルの問題、あるいは土地の所有権の問題は切り離せない関係であり、この問題を連結して解決しなければならないという議論が、今、盛んに行われるようになっている。
戦略的補完性とは
このように、中国におけるここ30年来の農民の都市への非常に早い流入によって支えられた経済は、明らかに1つのターニングポイントに来ている。これをルイスのターニングポイントと呼ぶかどうかは別だが、人口動態の関係や戸籍制度、税制度という複合的な観点から中国は1つのターニングポイントを迎え、そこからユニバーサルな公共サービスをどうするか、都市農村間の所得格差をどうするか、混雑減少をどうするかという問題が出てきているといえる。こうした問題は、日本が70年代に直面してきた問題であり、特に自民党の一党支配がこの問題に取り組んで解決したという側面があるため、日本の経験に中国も大きな関心を寄せている。
一方、工業の自立的な労働生産性向上の可能性についてだが、1人当たりGDP成長率のうち、既にみたように労働生産性の貢献度が非常に大きくなっている。中国ではキャピタルストックの公式なデータがないため、精華大学や人民大学が集めたデータを提供してもらって計算したところ、80年代には約50%がTFPで残りが資本装備率の増大であるという推計になった。土地バブルなどの現象がここにどう影響しているかということは検討する必要があると思うが、私の予測では、労働生産性の成長はまだかなり継続するのではないかと思う。これは東京大学の藤本隆宏氏や一橋大学の関満博氏など、中国の工業の現場を歩いて観察されている人たちのコンセンサスではないかと思う。中国が政治的な問題を解決する仕組み作りに成功するなら、労働生産性が継続的に成長する可能性がある。
一方で、労働力人口が収縮している日本は第4フェーズに向かっているわけだが、従来型工業力の国内ワンセット展開は、比較優位性の追及からいっても、現実的でもないし必要でもないのではないか。むしろ現在、各企業がやっているように、研究基地などを日本に持ちながら実際の生産は国際的に展開し、工業力とサービス力の新結合で付加価値の高いところを狙うべきである。
また、中国が先に指摘したような問題を持っているとしたら、都市経営や環境経営が非常に重要になる。たとえば北京はひどい交通混雑で、オリンピックの直後はナンバーによる交通規制をしていたが、その後は元に戻ってしまった。中国の新車販売台数は、2010年に1700万台、2015年には2700万台という予想が出ているが、既に大変な勢いで交通混雑が起きている。このような状況でゴミの処理などはどのように行っているのか関心があるが、北京のゴミ処理場は3カ所しかないと聞いたことがある。ただ、都市経営や環境経営の重要性は中国もよく分かっていて、中国共産党は毎年何十人という幹部候補生をハーバード大学やケンブリッジ大学に送り、スクーリングを受けさせてきた。日本でも2年前から東京大学で、都市経営や環境技術、環境経営に焦点を置いたスクーリングを受けている。
日本は今後、第4フェーズに向かっていく中で、健康や保育、介護、生涯教育、科学技術という産業の開発が必要である。また、農業も単なる大規模化ではなく、たとえば有機農業のような高付加価値の農業に大きな可能性がある。中国への日本土産で一番喜ばれるのは日本の米である。日本と外国の米価の格差も縮小しているため、その意味では農業には大きな可能性がある。現在議論されている環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)も、むしろ農業にとって1つのチャンスであり、そうした意味での開国をしていくことが重要なのではないかと思う。
中国は第3フェーズに、日本は第4フェーズに移行していく上でどのような問題を解かなければならないかということを見ると、パズルがうまく組み合わさるように補完的な関係があり得るのではないかというのが私の持論である。 国際経済関係のゲームにおいては、戦略とは単に政府の政策のことではなく、それぞれの経済における諸利益集団の私的利益や公民意識にもとづく政治行動のベクトルから成る。そうした各国間の戦略の間に、ゲーム理論的な意味での戦略的補完性があれば、両方が良い方向に向かうモメンタムが生じることもある。また、何らかの出来事をきっかけとして相互が不信に陥り、孤立主義的な戦略の応酬が陰鬱なモメンタムを生むこともある。そこで、正の潜在性をどのように現実化し得るかということを議論していくことが非常に重要だと思う。
政治形態に関しては、中国が第3フェーズに移行するための緊急要件を解決していく上では、今のような政府と特権階級との閉じた結託から、さらに開いた利益集団の間の利益裁定に進む必要がある。中国共産党が、日本の自民党のような一党支配の下で利益の裁定を図っていくという姿勢に変わる可能性は十分あると思う。日本も第3フェーズから第4フェーズに移っていくことを考えると、人口問題の変化にどのように対応していくかという国民の合意をつくるためには、リタイアした世代、現役世代、若年世代という3つの世代間の利益調整が必要になる。その観点から消費税改革の問題なども政治がリーダーシップをとって行っていくべきで、かつての自民党政治のように経済的利益集団のあいだの対立を政治家や官僚が絡んで裁定していくとか、あるいは単なる規制緩和や仕分けで効率化を図っていくということとは異なる政治的理念や公共精神が必要なのではないだろうか。
以上、さまざまなフェーズへの移転という意味では、日中韓の間にはかなりの共通性がある。しかし、そうは言っても、その中でどのように制度が変わっていくかは、市場化に向かう前の農業時代の契約関係の在り方などがpath-dependentな形で長い影響を持っているのではないかと考えている。こうした制度発展の農村起源説とでもいったことが、私の現在の研究課題の1つであるが、それについてはまたの機会にしよう。

質疑応答
- Q:
中国と日本とのアジェンダの対比において、日本経済を再生するために、健康、保育、介護、生涯教育などの面で日本が開発を進め先頭を切っていく方が良いというご指摘があった。しかし実際には、EPS細胞をはじめとして医療技術が高度に進歩すると、今まで治らなかった病気が治るようになり、人口高齢化が進むという面がある。この分野において日本経済が技術革新していくことは良いことだとは思うが、逆にそれが日本経済や世界経済に新しい課題、重荷をつきつけるのではないか。
- 青木:
高齢化が必ずしも医療費の高騰に結び付くとは限らない。医療費が膨張する部分はターミナルケアであり、アメリカでもそこに非常にお金がかかっている。予防医学をきちんと行っていけば、高齢化しても皆が健康に生きていけるので、ある程度安く国民全体の健康を維持できる。単にターミナルケアでお金を使うような投資をするのが良いのかどうかということは、健康産業をどういう方向に考えるかによる。
私が健康という言葉を使ったのは、メディケアというよりヘルスをどのように維持するかということに、むしろこの新しい産業の在り方があるのではないかと思うからだ。たとえば中国の場合、過去に農村から都市へ移住した2億人のほとんどが若者で、老人と子どもばかりが後に残された。しかし、農村にはメディケアや保険がないため、中国で老齢化が進むと非常に大きな問題になる。これをどう解決していくかは、狭い意味でのテクノロジーの問題ではなくソーシャルテクノロジーの問題である。こうした問題で、日本はさらに未知の世界に進んではいるものの、かなり先進的に蓄積しているものがあるので、今後のイノベーションがアジアの問題解決にもつながり得る。
もう1つ、少子化は果たして避けられないのかという疑問もある。最近の人口学者の研究で、国連の人間開発指数が0.93を超えると出生率が再び上がるということが統計的に言われている。唯一の例外は日本と韓国であり、その理由に関してはまだ分かっていない。女性の結婚年齢が高くなり子どもが少なくなっていくという状況で、女性が働きながら子育ができるような社会システムをどうやってつくっていくかというところに、社会の成熟度が現れるという議論もあり得ると思う。フランスやスカンジナビア諸国はそれに成功した。ドイツでも高齢化は非常に大きな問題になっているため、ドイツ日本研究所では若い研究者を集めて、老齢化という観点から日本とドイツを比較研究しているようだ。
- Q:
フェーズの問題について科学技術の切り口で見ると、中国の科学技術力の向上は目覚ましい。特にグリーン・イノベーションについては、私の手元のデータでは、燃料電池や太陽電池といった再生可能エネルギーについての英語の論文件数は、既に日本を上回っている。私が行っている技術経営の研究分野でも、中国人の研究者がかなり多くなってきている。科学技術は従来に比べて変化のスピードが非常に速くなってきており、ある部分の科学技術とそれによって実現する社会的な価値を生み出す部分については、日本を追い越していく部分もあるのではないかと予想している。この点について、どのようなお考えをお持ちだろうか。
- 青木:
グリーン・イノベーションはかなり世界的に認知されてきたが、人口問題はこれからどうなるかという状況にある。これからのアジアの問題を考える場合には、高齢化あるいは少子化の問題が、社会関係や経済関係、国際関係にどのような影響を与えていくかということが非常に大きな問題になってくる。この問題はやはり、日中韓合同での社会科学的テーマになり得ると思うので、共同研究をRIETIで行ったら面白いのではないだろうか。中国にはオフィシャルなキャピタルデータがないが、デール・ジョルゲンソン氏などはRIETIで行っているキャピタルストックの国際比較データを非常に高く評価しており、これはRIETIの1つの国際的な資産だと思うので、ぜひ発展させていただければと思う。2000年代のデータについても近いうちにRIETIの研究成果が出てくることが学会でも待望されているようなので、ぜひお願いしたい。
技術問題に関しては当然中国も大変な勢いで投資を行っているし、人的資本は疑いもなく優れたものだから、急速な進歩を遂げていることは事実だ。ただ、必ずしも日本は恐れる必要はない。すべてワンセットで最先端を行く必要はなく、日本がこれまで習得したものの一部は、社会的技術にしろ生産的技術にしろ、後からフェーズを追いかけて来る国に移転していく、あるいはそこにおける発展からわれわれも便益を受けるというフライングギースのパターンで行けばいいわけで、その先のところにどう技術投資をしていくのかということが日本にとって重要な視点ではないかと思う。
日本を再建するためには、やはり開国と世代間の再調和を中心に据えるべきである。消費税の問題などは、単に財政危機だといっても「まず事業仕分けで効率を良くしてから」と言うことになってしまう。今の状態で若い世代の将来にコストを移転して、年を取った人たちはそこから逃げ出すというようなことで果たしていいのか、という世代間の再調和の問題を、政治として訴えていくことが必要なのではないだろうか。
- Q:
今日の話の中でルイス転換点はどのような位置付けになっているのだろうか。経済発展の段階は4段階あって、今、中国は第2フェーズから第3フェーズに差し掛かっているということだったが、そのきっかけの1つがルイス転換点だと理解していいのか。中国国内では、数年前までルイス転換点が近づいているというのは少数派の意見だったが、最近は支持者が相当増えたのではないかという印象を受けている。中国政府も2011年から始まる第12次5カ年計画において、投入量の拡大ではなく生産性の上昇という形での成長パターンの転換が重要だという認識を示している。はっきりとは言わないが、恐らくルイス転換点が近づいてきたという認識も背景にあったのではないだろうか。
他の状況が同じであれば、ルイス転換点を過ぎると労働力は過剰から不足に変わるので、労働投入の寄与度は下がっていくし、農村部から都市部への労働力の移動による一種の再分配効果も減っていくことになるので、各部門の労働生産性が上昇しなければ、従来のような10%成長が当たり前という時代は終わると私も認識している。労働生産性をどう高める、どう維持していくかというのが、中国経済にとっては最重要課題になると思う。
農村部から都市部への移行が非常に重要だという点については全く同感で、これをもう少し一般化すると、産業の高度化になるのではないか。生産性の低い農業部門から生産性のより高い非農業部門に移って行くということだが、工業部門の中でも付加価値の低い部門もあるし高い部門もある。そうなると中国は、ルイス転換点が過ぎてからも労働集約型産業から卒業して、より付加価値の高い重工業なりハイテク産業なりに中心が移って行けば、労働生産性にとどまらずにTFPの上昇もある程度期待できるのではないか。中国政府は自主イノベーション能力を高める、つまりそれぞれの立場で努力することを強調するが、むしろ資源の再配分、産業の高度化という形の再配分の方が重要ではないか。この点についてご意見を伺いたい。
もう1つ、第2段階から第3段階に移ってから田中角栄の時代のように所得再分配政策が必要になってくるという点は否定しないが、ルイス転換点になってからは労働市場における需給関係も変わっていくので、市場の力でも賃金は上昇の方向にいくのではないか。労働分配比率は改善されるという方向に行くので、別に政府が所得再分配政策を採る必要はないのではないか。もっと緊急性があるのはむしろ前の段階ではないかという印象があった。
- 青木:
中国の現状認識は同じだと思うが、それをルイス転換点として性格付けていいのかどうかという問題がある。ルイスの理論は言うまでもなく、農村の生産性は低くて、それにプラスするプレミアムで雇う需要が都市工業部門にできると、無制限に労働力が移転して、それが転換点に来ると新古典派的な市場経済に移行していくというものだ。
私はそうではなくて、それ以前の段階においても、農家は合理的な経営主体であり、1970年代の四人組の時代であっても農民には自己計算で商業取引をやろうというインセンティブがあり、それを規制しようとする政府との間でせめぎ合いがあったと思っている。そういった規制が解かれてインセンティブ効果がかなり明白に現れてきたのが80年代なので、制度的な規制、政策的な規制と農家のインセンティブの絡み合いを議論していくことが重要なのではないかと思う。
また、所得配分はマーケットに任せておけばいいというのはそのとおりなのだが、一方で高齢化が急激に進み、農村地帯にはメディケアや保険がなく、一人っ子は都会に出てしまい、どこまでサポートできるのか分からないということもある。農村内部にあった共同体的な助け合いからこぼれた部分というのは、社会の安定にとって非常に重要な問題ではないかと思う。
農民は土地請負権を持っており、法律で請負権が譲渡可能になった事から、事態は良い方に進んでいるように見えるが、実は地方政府が土地を農民から買って開発するということの合法化に使われているという面もある。また、農民は土地の経営権は持っていても、それを自由に売ることについては政治的な制約がかかっている。従って、再分配制度の問題点は、マーケットに任せておけばよいというわけでもなく、戸籍制度や土地の所有制度にもあるといえる。
- Q:
フライングギースのバージョン2.0において、フェーズ4や5に行きたい日本の現状を考えると、どのような制度や仕組みの改革が有効だとお考えか。たとえば会社の仕組み、金融の仕組み、雇用の仕組み、政治や行政の仕組みという点で、今の日本の段階においてどのようなものが有効な経済制度イノベーションになり得るだろうか。
- Q:
社会保障改革について、退役、現役、若年世代の新たな和解と利益調整が必要であるということだったが、現時点で、どの程度社会保障制度を直すべきとお考えか。
もう1つは、現在、子ども手当や扶養控除を変えているが、これは場合によっては20年後に成人になる子どもの数を左右することになる。介護保険や年金を充実させずに、子どもに親の扶養義務、少なくとも経済的扶養義務を課すようにすれば、夫婦にとっては子どもをつくった方が長期的な経済保障としては得になるという仕組みもあり得る。そういった事前のインセンティブに影響を与える制度変更という面を見た場合、今どのように変えるべきかという2点についてご意見をいただきたい。
- 青木:
労働力の人口に占める比率が落ちてくるのは必然である。その問題をどうするかということをきちんと考えておかなければいけない。1つは移民の問題だが、非熟練労働者を入れる必要はないと考えている。TPPの議論でも、むしろ熟練労働者の開放をどうするかということが焦点になっている。企業がグローバルに展開していくためには外国人のマネージャーや熟練労働者などを大胆に登用していく必要がある。たとえば、JALを退職したパイロットを韓国のエアラインが雇うということが起ころうとしている。熟練労働者の労働市場はリージョナライズ、あるいはグローバライズしているわけで、日本もこの対応をしなければならない。これがいわゆる第二の開国といわれていることである。
企業がどう変わるのか、政治がどう変わるのかということについては、こうしたアジェンダをうまく遂行できるような組織あるいは政治が、正統性を得るということになるのだと思う。この問題は、過渡期においては連立や超党派間の調整のメカニズムがなければできないと思う。日本では「ねじれ」と言われるが、アメリカでも中間選挙の後はねじれが生じることが多いので、政権の後半はどのようにお互い妥協するかということに腐心する。米国のニュートン・ギングリッチ氏のように、政府の機能を停止させるような極端なことをするのは、誰にとっても良くないということは明白だ。スウェーデンの社会保障改革は、すべての政党が参加した仕組みの中で協議して出来上がってきた。そうした発想の転換が今の日本には必要だろう。しかも時間が限られているわけだから、今年、来年の間にその道筋をつけることができるかどうかが日本にとっては重要な問題である。
- Q:
フライングギースの理論で、バージョン1.0のときに出てきたプレーヤーとしてアメリカやASEANがあった。アメリカのマーケットは、アジアが発展していく上での最終消費地としての重要性があって、APECというフレームワークをつくるときにもアメリカを入れることの発想の原点になったと思うが、今までは日本が技術水準や生活水準、文化というところでアメリカマーケットに入っていくことの優位性をある程度持って先頭を走っていた。これから中国の市場が大きく発展していく中で、中国マーケットが中心になっていくとすれば、市場への近接性などの点で構造的な変化があるのか、あるいはアメリカが引き続きバージョン2.0の中で役割を果たしていく部分があるのか。
また、ASEANの中にはFTAなどで戦略的にうまく立ち回っている国もあり、中国マーケットとの関係でも製品のレベルなどの点で輸出を伸ばしたりしている。バージョン1.0のときには日本の直接投資が非常に大きな役割を果たし、フライングギースの一角を占めていた。日中関係というパズルを解く上で、2国間だけではなく他のプレーヤーとの関係も含めて考えるとすれば、どのようなことがこのバージョン2.0において考慮されるべきか。
- 青木:
最初にアジアが1つの経済圏として登場してきたと申し上げたが、当然、アジアだけで閉じて事が運ぶわけではない。だからこそTPPなどの議論があり、むしろそうした広いフレームワークの中で問題を解決していこうという方向性が、日本にとっても中国にとっても良いと思う。WTOへの加盟も、中国国内の改革派と保守派でせめぎあいがあった結果、中国としては1つの賭けだったわけだが、それによって中国の改革は進んだ。今、TPPで議論になっているようなことは、知的所有権の問題、透明性の問題、プロフェッショナルなスキルを持った人たちの流動性の問題、法人税の問題などがあるが、アメリカとしては中国を彼らの言う価値体系の中にどのように押し込めるかという狙いもあると思う。その意味では、このフライングギースはまた大きなコンテクストの中で飛んでいるといえる。
ただし、小農経営が圧倒的に多い、という状態から発展してきたという意味では、東アジアはやはり共通性を持っていて、アメリカの移民のような外部からの人口流入とは決定的に違うし、ヨーロッパとアジアでも違うということで、今日は少しアジアに焦点を当てた。特に日本では行き過ぎた中国脅威論が存在しているので、それを少し考え直すためにこうしたフレームワークを提供させていただいた。
この議事録はRIETI編集部の責任でまとめたものです。

