マクロ経済の安定は、中国政府にとって重要な政策課題である。ここでは、インフレ率と経済成長率の変動を軸に、リーマン・ショック以降の景気循環と、政策金利や、為替レート、そして株価といった重要な「価格」の変動要因を分析する。
経済成長率とインフレ率の変動から見る景気循環
中国経済は、2008年9月のリーマン・ショックを受けて、一時景気後退を余儀なくされ、2009年第1四半期の経済成長率(実質GDPの上昇率、前年比、以下「成長率」)が6.6%まで落ち込んだが、4兆元に上る景気対策と金融緩和を受けてV字型回復を見せ、2010年第1四半期の成長率は12.1%に達した。しかし、その後、ヨーロッパの財政危機をきっかけに世界経済が再び混迷に陥ったことに加え、国内では景気対策の効果が薄れ、またインフレを抑えるために金融政策が緩和から引き締めに転換されたことを背景に、成長率は低下傾向に転じ、2012年第3四半期には7.4%と2009年第1四半期以来の低水準となった。インフレ率(CPIの前年比上昇率)は成長率の低下を受けて、2011年の第3四半期をピークに低下傾向に転じた。
一般論として、インフレ率は成長率、ひいては景気の遅行指標である。中国においても、成長率が上昇すると、やや遅れてインフレ率も上昇し、逆に成長率が低下すると、やや遅れてインフレ率も低下する。2001年第1四半期以降のデータを分析すると、両者の間のタイムラグは平均3四半期である。実際、横軸に3四半期前の成長率、縦軸に今期のインフレ率をプロットすると、両者の間で極めて高い相関関係が確認され、(回帰線の勾配に当たる)物価(CPI)の生産(GDP)に対する弾性値は0.82と推計される(図1)。このことは、3四半期前の成長率が1%ポイント上昇(低下)すれば、それに合わせて今期のインフレ率が0.82%ポイント上昇(低下)することを意味する(BOX1)。
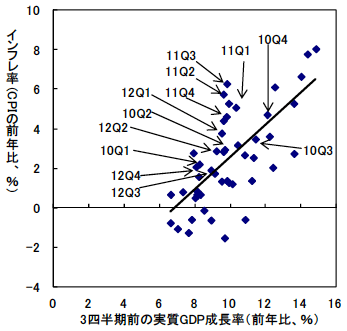
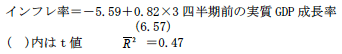 推計期間:2001年第1四半期~2012年第4四半期
推計期間:2001年第1四半期~2012年第4四半期インフレ率が成長率の同行指標なのか、それとも遅行指標なのかによって、景気変動のパターンは違ってくる。
仮に、インフレ率が成長率の同行指標である場合、成長率とインフレがそれぞれの基準値(平均値)と比べて、高いか低いかによって分類すると、景気は、「高成長・高インフレ」(=「好況期」)と「低成長・低インフレ」(=「不況期」)という二つの局面しかない(図2a)。「好況期」において引き締め策が採られ、これを受けて成長率とインフレ率がともに低下する。逆に「不況期」において緩和策が採られ、これを受けて成長率とインフレ率が上昇する。このように、景気は、「好況期」から「不況期」を経て再び「好況期」に戻るという形で循環するのである。
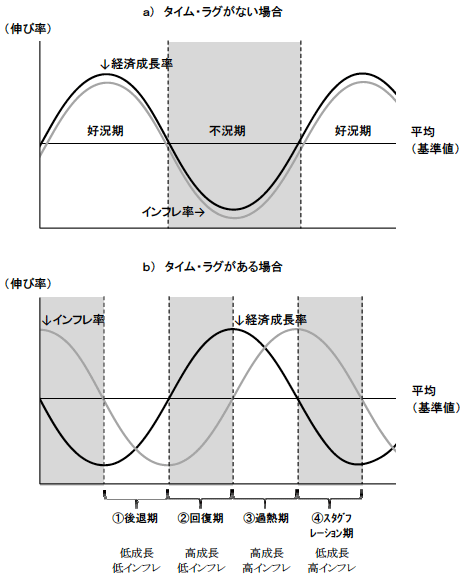
これに対して、インフレ率が成長率の遅行指標である場合、成長率とインフレ率がそれぞれの基準値と比べて、高いか低いかによって分類すると、①「低成長・低インフレ」の後退期、②「高成長・低インフレ」の回復期、③「高成長・高インフレ」の過熱期、④「低成長・高インフレ」のスタグフレーション期、という四つの局面に分けることができる(図2b)。「後退期」では、緩和策が採られ、これをきっかけに成長率が上昇し、景気は「回復期」に進む。やがて、成長率の上昇に追随する形でインフレ率も上昇し、景気は「過熱期」に移る。この段階において、政府は引き締め政策を採り、これをきっかけに成長率は低下し、景気は「スタグフレーション期」に入る。成長率の低下を受けて、インフレもやがて沈静化し、景気は再び「後退期」に戻る。このような景気循環は、横軸を成長率、縦軸をインフレ率とする座標平面において、成長率が先行し、インフレ率がついてくることを反映して、反時計回りの円として描くことができる(図3)。「後退期」における緩和策と「過熱期」における引き締め策の実施は、この循環を持続させる力となっているのである。
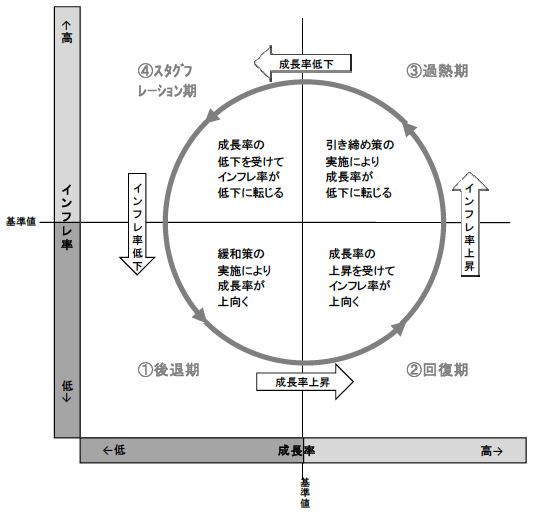
リーマン・ショック以降の中国経済への応用
この枠組みをリーマン・ショック以降の中国に応用する際、各時点において、成長率とインフレ率が「高いか、低いか」を判断するための基準値を決めなければならない。ここでは、対象期間(2008年第4四半期~2012年第4四半期)における成長率の平均値(9.0%)とインフレ率の平均値(2.7%)をそれぞれの基準値とする(図4、5)。
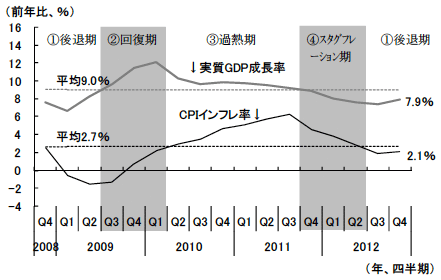
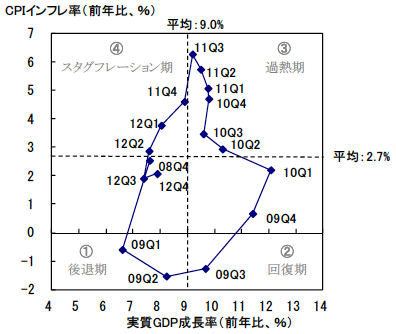
これをベースに判断すると、リーマン・ショックを受けて、中国経済は、2008年第4四半期以降、「低成長・低インフレ」という「後退期」に入った。これに対して、中国政府は素早く金融政策のスタンスを引き締めから緩和に転換させるとともに、4兆元に上る景気刺激策を実施した。これらが功を奏する形で、2009年第1四半期には成長率が6.6%で底を打ち、上向くようになった。2009年第3四半期になると、成長率が基準値である9.0%を超えるようになったが、インフレ率はまだ基準の2.7%を大幅に下回る水準にとどまり、景気は「高成長・低インフレ」という「回復期」に入った。成長率の上昇に追随する形で、2010年第2四半期にインフレ率が基準値を超えるようになり、景気は「高成長・高インフレ」という「過熱期」に進んだ。この段階において、当局は金融政策のスタンスを緩和から引き締めに軌道修正し、これを受けて、成長率は低下傾向に転じた。2011年第4四半期に成長率はついに基準を下回るようになり、景気は「低成長・高インフレ」という「スタグフレーション期」に入った。2012年第3四半期には、インフレも基準値を下回るようになり、景気はリーマン・ショック直後と同じ「低成長・低インフレ」という「後退期」に戻った。
成長率の低下とインフレの沈静化を受けて、中国政府は、2012年の年央以降、経済政策のスタンスを物価安定重視から成長重視へと転換した。それに合わせて、2011年12月から2012年5月にかけての三回にわたる預金準備率の引き下げに続いて、6月と7月に二回にわたって利下げを実施し、また投資プロジェクトの認可を加速させた。これらの政策が功を奏し、景気は8月を底に9月に上向き始めた。成長率は第3四半期に底を打った後、第4四半期には7.9%に上昇しており、景気回復は2013年にも続くだろう。しかし、労働力不足に伴う潜在成長率の低下に制約され、成長率の上昇は緩やかなものにとどまるだろう。一方、景気の遅行指標であるインフレ率が本格的に上昇に転じるのは、2013年年央以降であろう。
成長率とインフレ率に大きく左右される金利・為替レート・株価
中国では、市場経済化が進むにつれて、金利、為替(人民元)レート、株価といった主要な「価格」は、インフレ率と成長率の変動を中心とする景気動向に大きく左右されるようになった。金利が景気動向に大きく影響されていることは、経済学の教科書において、「テイラー・ルール」として定式化されている(BOX2)。ここでは、それを参考しながら、中国において、金利に加え、為替レートと株価がインフレ率と成長率の変動に対してどのように反応をするかを回帰分析という統計学の手法を使って明らかにする。なお、対象期間は、ドルペッグから管理変動制に移行した2005年7月を起点とする2005年第3四半期から2012年第4四半期とする。
1)金利の決定要因
まず、中国の銀行の預貸金利は未だ当局によって規制されており、金利の調整は、金融政策の重要な一環として位置づけられている。マクロ経済の安定のために、当局は成長率とインフレ率の上昇に対して金利を上げ、逆に成長率とインフレ率の低下に対して金利を下げることで対応する。
これを確認するために、金利のベンチマークとなる金融機関の一年満期の貸出基準金利を被説明変数に、インフレ率と成長率を説明変数に回帰分析を行った(注1)。その際、政策金利の慣性を考慮して、一期前の貸出基準金利を三つ目の説明変数として推計式に加えた。それにより、インフレ率の1%ポイントの上昇(下落)に対して金利を0.10%ポイント引き上げ(引き下げ)、成長率の1%ポイントの上昇(下落)に対して金利を0.06%ポイント引き上げる(引き下げる)という推計結果が得られた(図6)。
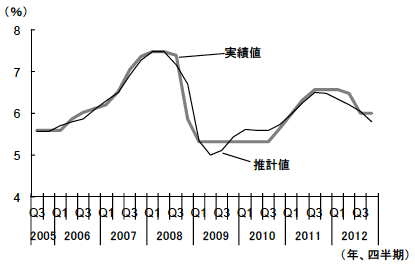
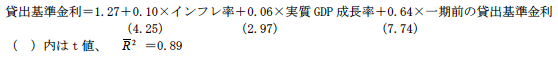 貸出基準金利は一年満期、四半期のデータは月次データの期末値の平均。
貸出基準金利は一年満期、四半期のデータは月次データの期末値の平均。推計期間:2005年第3四半期~2012年第4四半期
もっとも、インフレが1%ポイント上昇(低下)するときに、当局が政策金利を0.10%ポイントしか引き上げていない(下げていない)ことを反映して、中国における実質金利はインフレ率と逆相関を示しており、金利政策が景気を安定化させる手段として十分に効果を発揮できていないことは明らかである(図7)(注2)。当局が金利調整には消極的なのは、資本の移動性が高まる中で、利上げ(利下げ)は、流動性を抑える(拡大させる)本来の意図に反して、資本の国内(海外)への流入(流出)を通じて流動性の拡大(縮小)を招きかねないからである。
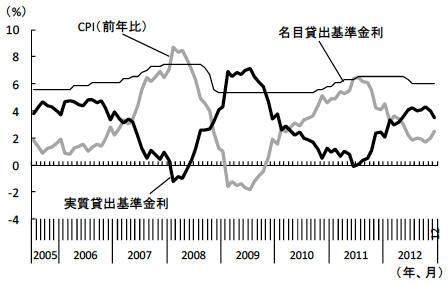
2)為替レートの決定要因
景気動向は、金利だけでなく、為替レートにも大きく影響している。これを確認するために、人民元の対ドルレート(前年比)を被説明変数に、またインフレ率と成長率を説明変数に回帰分析を行った。その際、変数間のタイムラグと為替レートの慣性を考慮して、今期のインフレ率の代わりに一期前のインフレ率を使用し、また一期前の人民元の対ドルレート(前年比)を説明変数に加えた。それにより、人民元の対ドルレート上昇率(前年比)は、一期前のインフレ率の1%ポイント上昇(下落)に対して0.53%ポイント上昇(下落)し、また成長率の1%ポイント上昇(下落)に対して0.30%ポイント上昇(下落)するという推計結果が得られた(図8)。
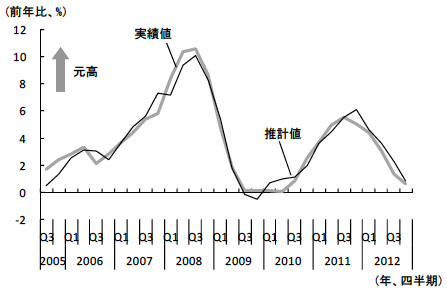
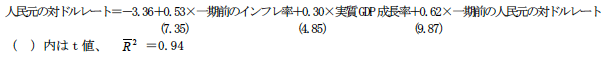 人民元の対ドルレートは四半期平均。推計期間:2005年第3四半期~2012年第4四半期
人民元の対ドルレートは四半期平均。推計期間:2005年第3四半期~2012年第4四半期中でも、2005年7月以降の人民元の対ドルレート上昇率とインフレ率の推移を比較してみると、市場原理に反して、インフレ率が高い(低い)ほど、人民元の対ドルレート上昇のペースも速い(遅い)という強い傾向が見られる(図9)。このことは、当局が為替レートを、物価を安定化させる手段として活かしていることを反映している。
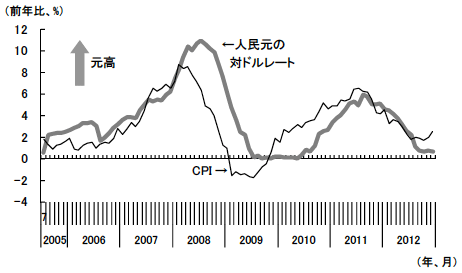
3)株価の決定要因
中国では、金利と為替レートと同様に、株価も景気動向に大きく左右される。これを確認するために、上海総合指数(前期比)を被説明変数に、成長率とインフレ率(いずれも前年比)を説明変数に回帰分析を行った。これにより、上海総合指数(前期比)は、成長率が1%ポイント上昇(下落)すれば4.86%ポイント上昇(下落)し、インフレ率が1%ポイント上昇(下落)すれば逆に3.55%ポイント下落(上昇)するという結果が得られた(図10)。この推計式に基づいて得られた推計値は、対象となる30四半期の内、実績値と同じ方向(上昇または下落)に動くのが24回に上り、実績値と逆の方向に動くのが6回だけで、「的中率」が極めて高いと言える。
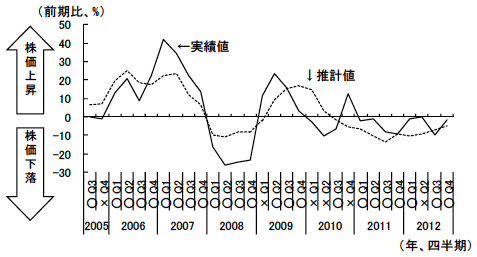
 上海総合指数は四半期平均。推計期間:2005年第3四半期~2012年第4四半期
上海総合指数は四半期平均。推計期間:2005年第3四半期~2012年第4四半期○:予測値と実績値はともに上昇または下落、×:予測値と実績値は逆の方向に動く
4)今後の見通し
現在、中国経済は、低成長・低インフレの後退期から、高成長・低インフレの回復期に向かっている。以上の分析に基づいて推測すると、当面、金融緩和の基調が維持され、人民元の対ドルレート上昇も緩やかにとどまる一方で、株価は上昇基調を辿るだろう。現に、2012年11月末から12月初めにかけて一時2000を割った上海総合指数は、その後急反発した。
BOX1:食料価格も景気次第
インフレ率が成長率に遅れて、同じ方向に変動するという結論は、近年の中国におけるインフレ率の変動が天候要因や海外市況に大きく左右されると見られる食料価格の変動によるものであることを考慮しても変わらない。実際、2001年第1四半期年以降のデータを分析すると、3四半期前の成長率が1%ポイント上昇(低下)すれば、今期の食料価格は2.00%ポイント上昇(低下)すると推計される。食料価格の弾性値がCPI全体の弾性値を上回っていることは、成長率が高くなると、農村部から都市部への労働力の流出が加速し、食料の供給が減り、逆に成長率が低くなると、労働力が都市部から農村部に逆流し、食料の供給が増えることを反映していると思われる(図)。
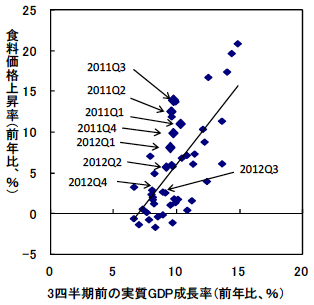
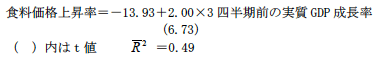 推計期間:2001年第1四半期~2012年第4四半期
推計期間:2001年第1四半期~2012年第4四半期BOX2:テイラー・ルールとは
テイラー・ルールとは、元米財務次官(2001~2005年)を務め、現在、スタンフォード大学の経済学者であるJ.テイラーが提唱する、金融政策を策定する上で、目安となるルールである(Taylor, 1993)。それによると、物価上昇率と長期的な目標値からの乖離幅と、景気変動を表す指標(例えば、GDPギャップ)の均衡値からの乖離幅に応じて、政策金利の水準を決めるべきである。当局は、現実のインフレ率が目標値を上回ったり、また実質GDPがその潜在水準を上回ったりする場合、政策金利を引き上げ、逆の場合、政策金利を引き下げなければならない。テイラー・ルールによる政策金利の適正水準は、次の式によって求められる。
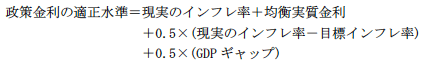
ただし、GDPギャップは、現実の実質GDPから実質GDPの潜在水準を引くことに計算され、計数が大きいほど、景気が過熱していることを意味する。
米国の例に沿って言えば、均衡実質金利が2%、目標インフレ率が2%とすると、政策金利であるフェデラル・ファンド金利(FFレート)の適正水準は、次の式によって求められる。
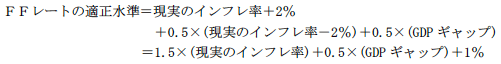
テイラー・ルールに従えば、中央銀行は、インフレ率の1%ポイントの上昇に対して、FFレートを1.5%ポイント、GDPギャップの1%ポイントの拡大に対してFFレートを0.5%ポイント引き上げることが望ましい。マクロ経済を安定化させるために、金利をインフレ率の上昇分以上に上げなければならないという考え方は、「テイラー原則」と呼ばれている。
このように、テイラー・ルールは、元々政策金利の適正水準を求めるために開発されたものである。しかし、その後、米国における政策金利の推移の説明にも有効的であることが確認されており、当局のマクロ経済の変動に対する「政策反応関数」としての側面が強調されるようになった。その場合、インフレ率(と目標インフレ率の差)の変動とGDPギャップの変動に対する政策金利の「弾性値」は、あくまでも実証によって確認されるものであり、テイラー・ルールが元々想定した「適正値」(インフレ率とGDPギャップの変動幅に対してそれぞれの1.5倍と0.5倍)と一致することが分析の前提とされていない。
参考文献
Taylor, John B. (1993) "Discretion versus Policy Rules in Practice", Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 39: 195-214.
2013年2月4日掲載


