| 解説者 | 伊藤 恵子 (専修大学)/松浦 寿幸 (慶應義塾大学産業研究所) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0065 |
| ダウンロード/関連リンク |
1990年代以降、経済学の分野では個別企業や個人といった、ミクロ・レベルのデータを活用しての実証分析が盛んに行われている。その背景には、世界各国の政府が作成している政府統計の元データが、一定の条件の下で研究者に開示されるようになったことがある。
RIETI「産業・企業の生産性と日本の経済成長」研究プロジェクトでは、経済成長の主要な源泉である生産性を多面的に分析するために、日本産業生産性データベース(JIPデータベース)を整備する一方で、経済産業省の「企業活動基本調査」など大規模ミクロ・データを活用した研究を行っている。伊藤、松浦両氏による今回の論文は、プロジェクトが取り組んできた一連の研究内容とその成果を、企業の参入・退出とグローバル化という二つの視点を中心に紹介するものだ。製造業では新規参入よりも既存企業のリストラ努力が産業全体の生産性上昇に寄与していることや、低生産性企業の淘汰が健全に行われていない現状の問題提起など、産業政策をめぐる議論の活発化への貢献が期待される。
――今回、ミクロ・データを活用した企業の生産性分析に注目したのは何がきっかけだったのでしょうか?
伊藤:「失われた20年」などといわれるように、日本の産業界は長年、経済成長率の伸び悩みという問題に直面してきました。この要因については、需要側か供給側かといった議論もありますが、私たちはまずは供給要因に着目し、その中で生産性の低迷が企業活動にどの程度の影響を与えているのかを、きちんと測定したいと考えました。
経済学においては、1990年代以降、大規模なミクロ・データ、つまり個別企業や事業所ごと、または個人レベルのデータを活用しての実証分析が盛んに行われるようになりました。この背景としては、世界各国で政府が作成するミクロ・データを一定の条件下で研究者に公開するようになったこと、パソコンの性能が向上したことによって大規模なデータの分析が容易になったこと、民間のシンクタンクやデータ提供会社が作成して販売するデータベースが増えたことなどが挙げられます。従来のマクロ・レベル、産業レベルでの分析では、ある国、またはある産業内の全ての企業が平均な企業と同じ行動をとるものと仮定していましたが、ミクロ・データを利用することで、同一国内・同一産業内の各企業の行動の不均一性を考慮した分析が可能になりました。
海外では、欧米諸国においてはもちろんのこと、こうした研究が進んでいますが、チリ、アルゼンチンなど南米の国々のミクロ・データを用いた分析も多数行われています。日本でも、経済産業省や総務省などの統計調査の個票データが徐々に研究に利用できるようになってきており、これらを利用して生産性低迷や上昇の要因を探ってみたいと考えるようになりました。
松浦:生産性の要因を分析したこれら研究の成果は、日本の産業政策や労働政策立案を巡る議論を活発化させ、国際化や内外の競争に直面する日本企業の支援にも貢献できると考えています。これまでの研究成果は通商白書や中小企業白書などに引用されていますし、各種政策シンポジウムなどでもとり上げられています。
企業の「不均一性」反映した分析が可能に
伊藤:この研究はもともと、2000年前後に内閣府で「生産性の計測に役立つデータベースをつくろう」というアイデアが出たことが始まりでした。これを受けて2003―04年にRIETIに「産業・企業の生産性と日本の経済成長」研究プロジェクト(以下、企業・産業生産性研究会、プロジェクトリーダー:深尾京司FF(一橋大学))が発足し、産業レベルの生産性分析に取り組み始めました。研究会には内閣府や学習院大学、日本大学、横浜国立大学などから研究者が参加しています。またオランダ・フローニンゲン大学との共同研究なども実施しています。
――生産性の分析において「企業の参入・退出」と「グローバル化」の2点に着目した理由は何でしょうか?
伊藤:以前はミクロ・データといえば一部の上場企業のものや、研究者が独自に行った小規模な調査のデータしか利用できませんでしたが、政府統計の場合は調査対象の企業は回答することが義務付けられているため、民間調査に比べると回答率が格段に高く、中小企業も含めた多くの企業のデータが時系列で揃っています。このように利用できるミクロ・データのカバレージが格段に広がってきたことにより、企業の新規参入や退出つまり撤退の現状が分析しやすくなりました。さらに1990年代の特徴として、企業の海外進出やM&A(合併・買収)が盛んになるなどグローバル化も進展したので、この2つにまず着目したわけです。
――使用したデータは具体的にどのようなものですか?
松浦:経済産業省が実施している「企業活動基本調査」「海外事業活動基本調査」「工業統計」などです。企業活動基本調査の場合、おおむね製造業1万2000社、非製造業で1万社ぐらいをカバーしています。調査項目は輸出入や海外子会社の有無やその活動、売上高などですが、ファイナンスやコーポレート・ガバナンス、研究・開発などに関する項目はあまり多くありません。
分析にはデフレーターの問題があります。価格の実質化にあたり、低コストで割安な製品を生産している企業に大きなデフレーターを使うとアウトプットが過小評価されて誤差が出る可能性がありますし、その逆もあります。また、非製造業の分析では生産性を調べるためのデータが少なく、デフレーターの選択も簡単ではありません。
――ミクロ・データを活用した生産性分析が産業政策全般や今後の政策論議に与えるインパクトは?
伊藤:経済産業省は最近、中小企業の国際化推進を政策課題に掲げています。中小企業をどのようにグローバル化させていくか、というテーマにも、こうした生産性分析の結果は生かされていると思います。
松浦:また、RIETIの次期の研究計画にも「アジアの成長をいかに取り込むか」という課題が明示されていますので、現地生産や輸出などを通じて企業がアジアで成功するためにはどうしたらよいか、という議論にも役立つと考えています。
――これまでの主な研究の成果についてお聞かせ下さい
伊藤:一連の研究で、製造業では既存企業の生産性が上昇する効果(内部効果)の寄与が大きく、非製造業では2000年以降、生産性の高い企業がシェアを伸ばす効果(再配分効果)や純参入効果(生産性の高い企業の参入および生産性の低い企業の退出による効果)が生産性改善につながっていることが分かりました。
さらに、1990年代には製造業で「負の退出効果」つまり、生産性の高い企業や事業所の退出増加がみられ、製造業と土木・建設業などで再配分効果がマイナスになっています。これは、生産性の高い企業がリストラなどでシェアを低下させ、逆に低生産性企業が無理して操業を続けているというような状況が考えられます。まだ十分な検証は行われていませんが、この背景には大企業が生産性の高い事業所を海外に移転させている可能性や、銀行による「追い貸し」などの影響で市場の新陳代謝が活発に行われていないことが考えられます。
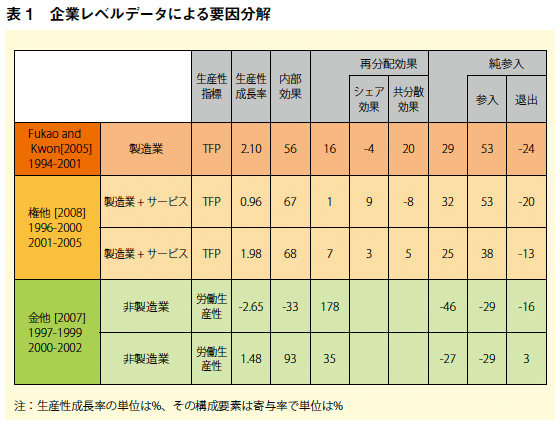
松浦:Fukao and Kwon(2005)では、1994年―2001年の「企業活動基本調査」の製造業の個票データを用い、存続企業、参入企業、退出企業の生産性を分析しています(表1)。ここでは、1)製造業全体で退出効果がマイナス、2)内部効果の寄与は相対的に大きく、医薬品、通信機器、電子部品、自動車などで目立っている、3)純参入の効果が大きく、再配分効果の寄与度は小さい――などが分かりました。また権他(2008)では対象期間を2005年まで延長するとともにさらにサンプル数を大幅に拡大し、卸小売業などの非製造業も含む分析を実施しています。その結果、製造・非製造業両方で内部効果の寄与が大きかったのですが、退出効果ではマイナスの状況が続いています。ここでは、2000年以降の生産性上昇率の改善は、存続企業のリストラなどによる生産性改善によってもたらされている、と結論づけられています。
![表2:金他[2007]による製造業の事業所レベルの生産性変動の要因分解 表2:金他[2007]による製造業の事業所レベルの生産性変動の要因分解](data/065_t2.gif)
また、金他(2007)では、日本政策投資銀行の「企業財務データバンク」など3つのデータベースを統合して非製造業86万社のデータによる分析が行われています。この研究では1997―99年と2000―02年で労働生産性成長率の符号が逆転しているため、生産性上昇要因の寄与の符号も逆転していますが、内部効果は両期間とも生産性を改善させる方向に働き、再配分効果も2000年以降回復しています。また、退出効果は一貫して生産性を改善させる方向に寄与していますが、参入効果は2000―02年では生産性を悪化させる方向に働いています。
生産性向上は既存企業頼み
松浦:さらに、製造業の事業所レベルの生産性変動の要因分解を見ると(表2)、内部効果が分析期間を通じて大きなインパクトを持っていますが、これが1990年代に半減したこと、つまり個別企業の生産性上昇率が低迷していることが、産業全体の生産性が上がらない大きな要因になっています。また、再配分効果と純参入効果は両方ともプラスで安定的ですが、個別にみると退出効果の寄与が一貫してマイナスになっています。
企業・産業生産性研究会では国際比較も試みていますが、これは大きな成果の1つだと思っています。日本企業の場合は内部効果が比較的大きいのに対し再配分効果や参入効果が少ないことが分かりました。ここでも、新規参入企業によってもたらされるイノベーションがマクロ経済に好影響を与えず、生産性向上はもっぱら既存企業の取り組みによって支えられている状況が浮かび上がります。
この背景には、半導体や自動車などの製造業において技術開発が主に老舗大手企業に委ねられているからだと考えられます。既存企業のイノベーションがあまり望めない中、この研究は「どうやって新規の参入率を上げていくか」という重要課題を提起するとともに、中小企業の役割が評価されるきっかけにもなったと思います。
――日本の製造業で退出効果の寄与がマイナスになるというのはどういう背景があるのでしょうか。
松浦:先に説明しましたように、海外進出による空洞化や、追い貸しのために低生産性企業の退出が促進されないことの影響などが考えられます。また、サービス業では退出がうまく行われている可能性がありますが、製造業では退出・淘汰のメカニズムが十分機能せず、これが低生産性につながっていると考えられます。これは産業全体に大きなインパクトを与える現象ですが、商品の代替性や事業所ごとの生産品目の相違などがあるので、統計的に比較するのは難しいといえます。
また、再配分効果の寄与度が小さいということは、生産性の高い企業が必ずしもシェアを拡大できていないことを示しています。日本は韓国などと比べて企業間格差が小さく、しかも新規参入企業のダイナミクスが小さく、既存企業も必ずしもパフォーマンスが優秀というわけではありません。
――企業のグローバル化と生産性の関係はどうでしょうか。
伊藤:グローバル化と生産性との間に正の関係が存在することは多くの実証分析で示されてきました。輸出や対外直接投資(FDI)を例にとると、そこには海外市場にアクセスするための固定費用を賄えるだけの高い生産性を有しているかどうかという「自己選択効果」と、海外市場から知識やノウハウを取り入れて生産性を向上させるという「学習効果」とが考えられます。「自己選択効果」は、結果的に規模が大きく生産性の高い企業にチャンスがあることを示唆し、日本を含む諸外国の実証分析でもこの効果は広く確認されています。学習効果の存在は、実証研究によるサポートはまだ十分とはいえませんが、欧州などの研究では学習効果が確認できたケースもあります。
先行研究では、グローバル化の進展によって生産性の高い企業がシェアを増やし、生産性の低い企業が工場を閉鎖したり退出したりしてマクロ・レベルでの生産性が向上する可能性があることも分かっています。しかし、日本の場合は、電機、電子、自動車などグローバル化が進んだ産業で、相対的に生産性の低い企業の退出や規模縮小が進んでいません。つまり、グローバル化が競争を通じて、低生産性企業の淘汰、そして産業界全体の生産性向上に結びついていない、といえます。日本では90年代以降、事業所の廃業率が開業率を上回っている状況であり、企業の淘汰が進んでいる、との反論があるかもしれません。しかし、一連の実証研究の結果からは、企業の淘汰が起きているのはグローバル化の進展した産業においてではなく、日本が国際的な競争力を失った衰退産業においてであることが示唆されます。つまり、グローバル化の進展が競争を通じて低生産性企業の淘汰を促し、産業全体の生産性を向上させる効果が、日本では比較的小さいことが分かりました。
このように、国際競争にもかかわらず生産性の低い企業が生き残っている日本独特の状況については、競争の形態や労働環境・商慣行、制度要因、そして構造的要因などを解明していく必要があると考えています。
――一連の研究で得られた結論、推論の中で重要なものは。
松浦:1990年代半ばまでは、グローバル化によって国内の生産基盤縮小などが起きて空洞化につながるといわれましたが、最近の議論はむしろグローバル化の利益をどうやって得るべきか、という点に移ってきています。これも研究蓄積の成果といえるでしょう。今後はグローバル化したくてもできない中小企業にも、いかにグローバル化のメリットを享受させるか、という方向で政策論議を進めるべきだと思います。
伊藤:生産性に関しては企業間の格差も大きく、たとえば、上位25%ぐらいの企業は生産性を向上させていますが、残り75%は生産性が伸びないまま存続しています。
省庁間協力でミクロ・データ活用促進を
――ミクロ・データによる生産性分析をさらに進めていく上で、今後どういったデータが新たに必要となるのでしょうか? データの入手という点で日本の研究環境はいかがですか。
伊藤:欧州では、個人がどんな会社で働いているか、といった雇用者―被雇用者のマッチングデータ統計などがかなり整備されつつあります。しかしデータ整備だけでも大変な作業ですので、まだ発展途上の研究といえます。
松浦:たとえば「派遣切り」が話題になりましたが、企業から見ると派遣労働者は従業員にカウントされず、派遣会社に料金を払う中間投入という位置づけになっています。このため、派遣労働者のスキルなどの分析が非常に難しくなっています。
伊藤:グローバル化に関していえば、労働需要や雇用者、あるいはスキルや人件費などに与える影響が欧米でも大きな関心事になっています。こうした問題にアプローチするためには、いろいろな省庁などがまとめている、さまざまなデータをうまく接続できるようにすることも必要です。
松浦:また、商品別、国別貿易額なども、「どの企業が、どこの国に何を輸出したか」というような、貿易データと企業データをリンクさせたデータがあれば非常に面白いと思います。財務省・国税庁は「納税資料」として法人の登記や解散・清算に関する細かいデータを持っています。これを経産省の企業データとリンクさせれば非常に有用ですが、現状では、統計以外の目的で集めたデータについては、根拠となる法律やデータ提供者との信義則の問題もあるため、データの公開は進んでいません。こうした点を踏まえて日本も統計の体系的な構築を議論しつつありますが、まだ時間がかかりそうです。
――今後の課題と研究計画についてお聞かせください
伊藤:市場やサービスの規制など、制度要因や市場環境が生産性にどのような影響を与えるのか、というテーマは、まだ研究が十分ではありません。欧州ではこの問題への関心が高く、市場の規制を指標化するなどの取り組みが行われています。規制には文化的な背景もあるので国際比較や数量化は難しいのですが、今後は海外共同研究も含めてこうした制度要因や規制に関する国際比較研究の実施も考えていきたいと思います。もちろん、先ほど言いましたように、ミクロ・データの整備や利用促進も重要な課題です。
松浦:まだ具体的に動いているテーマではありませんが、規制緩和など、過去の政策変化に対する評価も、ミクロ・データを利用するとより深い議論ができると考えています。また、企業における解雇の要件の問題や派遣労働者という要因にも注目しています。
解説者紹介

伊藤 恵子
1994年早稲田大学理工学部工業経営学科卒業。2002年一橋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。(財)国際東アジア研究センター上級研究員、専修大学経済学部講師、助教授を経て、2007年より現職。博士(経済学)。

松浦 寿幸
1998年慶應義塾大学総合政策学部卒業。2004年慶應義塾大学商学研究科博士課程単位取得退学。独立行政法人経済産業研究所研究員、一橋大学経済研究所専任講師を経て、2009年より現職。博士(商学)。一橋大学GCOE特別研究員。

