| 解説者 | 高原 明生 (東京大学大学院法学政治学研究科教授) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0042 |
| ダウンロード/関連リンク |
中国が高度経済成長を続け、国際的な地位を急速に向上させている。その躍進に世界が注目しているが、高度成長により社会のひずみが拡大し、安定が揺らぐ危険性が生じているとの見方もある。経済的にも地理的にも中国と密接な関係を持つ日本にとって、同国とどのように付き合うかが、一段と重要な問題になりつつある。
こうした問題意識から、高原明生東京大学大学院法学政治学研究科教授は、RIETIディカッション・ペーパー(DP)「中国の台頭とその近隣外交」をまとめた。中国の台頭の内実を分析し、同国が社会の安定を保つには政治改革が必要だと指摘するとともに、日本の対中外交については、1)中国の内発的社会発展への関与と人間の安全保障への支援、2)東アジアでの民主的な地域レジームの構築、3)軍事的な信頼醸成の促進と日米安全保障協力の維持、4)日中間の相互理解のための対話と交流の促進――などを提言し、日本が東アジア外交を主体的に展開することが重要と論じている。
中国の台頭、日本が外交を考える好機に
――どのような問題意識から本論文を執筆されたのですか。
RIETIの白石隆ファカルティフェロー(総合科学技術会議議員、政策研究大学院大学客員教授)をプロジェクトリーダーとする研究プロジェクト「中国の台頭と東アジア地域秩序の変容-予備的考察-」の一環として執筆したものです。中国の経済発展によって同国と近隣諸国の関係は変化し、近隣諸国と形成する秩序の在り方も変容しているなか、同プロジェクトは、「そうした秩序の変容を日本はどうマネージすればよいのか」について検討したものでした。私は中国が専門ですので、同国の台頭の内実、近隣諸国との関係づくり、地域秩序に対する考え方などを分析し、日本がどのような外交を展開すべきか考察しました。
――経済的に台頭し国際的なプレゼンスを高めた中国とどう付き合うべきか、日本が改めて考える必要があると判断されたわけですね。
その通りです。日本は第2次世界大戦後、外交戦略や地域秩序の構築といった基本的な問題について、明瞭な考え方を持たなくても済む環境に置かれていました。このため、しばしば「戦略なき日本」と評されましたが、中国の台頭によって、それらの問題を考えざるを得なくなりました。これは、ある意味では幸いなことといえるでしょう。
中国社会の安定には政治改革が必要
――中国の台頭の内実をどう分析されましたか。
「改革開放」を主導したかつての指導者、鄧小平は89年の第2次天安門事件の後、国家を安定させることができたのは「経済発展を促進して人民の生活を改善したからだ」と述べました。その言葉通り、経済成長によって大多数の人々の暮らしぶりが改善されたことが、中国社会の基本的な安定要因になっているとみてよいでしょう。たとえば、1人当たりの住宅面積は90年には都市で13.7㎡、農村で17.8㎡でしたが、06年にはそれぞれ27.1㎡と30.7㎡に広がりました。また、100戸当たりのカラーテレビ保有台数は90年には都市で59.0台、農村で4.7台でしたが、07年にはそれぞれ137.8台、94.4台に増えています。
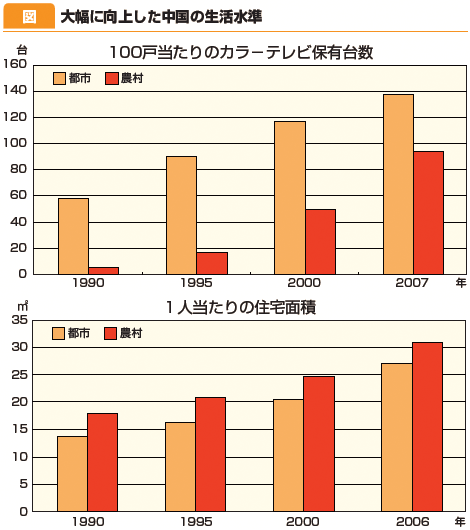
しかし高度成長のさまざまなひずみが、社会レベルにおける多くの利益衝突を生みました。それを示すのが、土地収用のための強制移転や環境汚染をめぐる紛争、さらには労働争議の増加です。それらの紛争や争議の大半は、権利侵害に対して民衆が立ち上がったもので、直接的に政治改革を求める動きとはいえません。ただ、以前と違って、共産党の中堅幹部の間でも「このままでは立ち行かなくなるだろう」「パラダイムシフトを起こさなければ中国の根本的な問題は解決しない」という認識が広がってきました。この変化は、ここ1、2年の特徴的な動きです。
現在の中国は依然として「法治社会」ではなく「人治社会」であり、制度が十全には機能しない社会です。もちろん、こうした非制度的な物事の進め方には、柔軟性を持って臨機応変に問題に対処できるという長所はありますが、しかし予測可能性が非常に低いうえに、権力の腐敗と密接に関係しています。こうした足元の紛争や争議の増加は、今すぐ社会の動揺をもたらす問題ではないと考えられますが、共産党の中堅幹部に「いずれは政治改革に踏み切らなければならない」という意識の向上をもたらしていることを見逃してはなりません。
――中国は本当に政治改革が必要なのでしょうか。
権力の腐敗や利益の衝突がこれ以上ひどくなれば、このままでは立ち行かなくなると考える人が一層増えることでしょう。社会の基本的な安定を保つために、いずれ政治改革が必ず必要になると思います。中国では誰もが、一党独裁に問題の根源があることを知っています。これまでは経済が成長し、生活水準が上がったため国民の多くはおおっぴらに文句を言わなかったのですが、不景気が長引き職を失う人が増えれば不満が噴出する可能性は否定できません。
現時点では政府に財政的な余力があります。公共投資、生活保護といった「バラマキ」が可能ですから、大きな混乱は起こらないでしょう。しかし、政府のカネが尽きたときにどうなるかが問題です。不景気と大旱魃(だいかんばつ)などの自然災害が重なれば厳しさが増します。
――現在の中国では、共産党の幹部が一党独裁を利して経済的な利益を享受しています。党幹部が自らの利益を手放してまで、政治改革を実施するでしょうか。
日本では戦前、財閥や既存の政党権力を打倒しようと若手将校が決起しました。そのような動きが共産党や人民解放軍の内部から出てくるかというと、今のところ、それほどのラディカルな運動が起きる兆候はありません。ただ、「思い切って政治改革に踏み切る方が、中国が抱えるリスクが小さくなる」という議論が盛んになる可能性はあります。
他方、一党独裁体制が民主主義体制に移行する際に、大きな混乱が生ずる恐れがあるとの見方が依然として有力です。その典型例が旧ソ連や東欧諸国だとされています。90年代初めに旧ソ連が崩壊し東欧諸国とともに民主化した際、社会や経済は大きく混乱しました。中国が、その轍を踏みたくないと考えるのは自然なことです。
ただし、歴史的にみて旧ソ連の解体をどう評価するかは難しいところです。短期的には混乱しましたが、中長期的な視点から考えるとどうでしょうか。また、問題は改革の進め方にあったとみることもできます。さらに、台湾が国民党による一党独裁から民主主義に移行した際は、社会や経済の混乱は起こりませんでした。そのように政治改革がうまく行ったケースも、実は身近にあるわけです。
――政治改革のロードマップは描けるのでしょうか。
困難ですが、方向性はすでに浮かび上がっています。1987年の第13回党大会では、趙紫陽のリーダーシップの下で大胆な政治改革構想が提示されました。たとえば、市場化によって多元化した利益を利益集団に組織し、共産党と協議対話させることが提唱されました。また、中国では5年に1回、共産党の大会が開かれますが、前回(07年)は党大会に先立ち、新たな幹部を選ぶ過程の第一段階として投票が実施されました。民主的なやり方だと胡錦濤も自画自賛しましたから、次回(2012年)の党大会でも同じ手法が採られるでしょう。
すると、今度は投票があるとあらかじめわかっていますから、選ばれたい人は自分に投票するように運動することが予想されます。その過程で党内に派閥ができ、ある種の派閥政治が制度化される可能性もあると思います。政策集団が生まれ、その集団の間で論争が展開されるといった形で、ある種の民主化が始まるような気がします。そうなれば日本の国会に相当する全国人民代表大会においても民主的な手続きで指導者を選ぼうという気運が高まったり、地方政府の首長を公選しようとする流れが生じたりする可能性もあります。
外交では多国間の枠組み作りを積極化
――中国の外交は、どのように変わってきたのでしょう。
中国は1989年の第2次天安門事件で各国から非難され、国際的に孤立しました。その後、改革開放の進展と高度成長により、近隣との経済関係を発展させ、孤立から脱却することに成功したものの、軍事力の誇示もあって今度は中国脅威論を誘発してしまいました。加えて、日米両国が冷戦後の東アジア秩序を構想するに当たって同盟関係を強化したこともあり、中国は東アジアで孤立しかねない状況に陥りました。60年代、文化大革命の時期に革命を輸出したことや、東南アジアなどで華人・華僑との民族対立が繰り返されてきたことなどの記憶もあり、中国が急速に発展すること自体が周囲を警戒させるという「発展と平和のジレンマ」が作用し始めたのです。
とって大きな問題でした。文化大革命と第2次天安門事件で国際社会から孤立し、その辛さを知っていましたから、中国脅威論の封じ込めに努めました。こうして90年代後半から、「新安全観」(新安全保障観)という名称の下で、協調的安全保障と総合安全保障の観点から、近隣諸国との多国間枠組みの構築に積極的に取り組むようになりました。
――具体的な動きを教えてください。
まず、旧ソ連諸国との関係を改善しました。ロシアとの間では、96年と97年の共同声明で「新安全観」にもとづく平和と協力の推進を唱えました。96年にはロシア、カザフスタン、キルギス、タジキスタンと国境地域信頼醸成協定(上海協定)を締結し、その後、国境地域の安全保障と経済協力、国際テロリズムへの共同対処へと機能を拡充しました。これが「上海ファイブ」ですが、01年にはウズベキスタンを加えて上海協力機構へと発展させました。
99年からは東アジア地域経済協力の枠組み作りに積極的になりました。同年11月、中国は前年に提案して実現した東南アジア諸国連合(ASEAN)+3の蔵相代理・中央銀行副総裁会議の常設化を提案すると同時に、ASEAN+3に合わせて日韓中三国首脳の会合を開くことに初めて同意しました。さらに2000年には日韓中三国首脳会合の定例化に同意すると同時に、ASEAN+1(中国)の会合でASEANとの自由貿易圏形成を提案しました。
この方針は、02年の共産党大会で「与隣為善、以隣為伴」(隣国とよしみを結び、隣国をパートナーとする)と定式化されましたが、隣国とのパートナーシップが2国間だけでなく、多国間の枠組みとしても構想されたところに重要な発想の転換があります。中国は02年以降、朝鮮半島の核危機を解決するための6者協議構想も受け入れ、奔走の末にそれを実現させました。また03年には東南アジア友好協力条約に加盟し、06年には南シナ海における係争者間の行動宣言を行動基準に格上げすることにも合意しています。
対中ODA は継続が必要
――日本の対中外交について、4つの提言をされていますね。
中国の経済的な台頭や外交戦略の変化を踏まえて考えてみましょう。日本にとって重要なのは、中国の台頭に関するリスクを下げ、チャンスを活かすことです。そのためには、1)中国の内発的社会発展への関与と人間の安全保障への支援、2)東アジアでの民主的な地域レジームの構築、3)軍事的な信頼醸成の促進と日米安全保障協力の維持、4)日中間の相互理解のための対話と交流の促進――などが外交課題になります。
まず1)について説明すると、日本にとって最も恐れるべきは、中国の「崩壊」や社会動乱です。経済的な相互依存の深さや地理的な近接性からみて、中国が混乱すれば日本の安全保障にとって大問題になります。中国の社会秩序が本当に崩壊の危機に瀕した場合、日本1国では到底支えきれるものでもなく、仮に国際社会が力を合わせてもできることは限られています。したがって、日本としては、問題を先取りする形で中国社会のリスク低下に協力し、中国側の注意を喚起することが望ましいと思います。
たとえば、日本が対中ODA(政府開発援助)などによって環境保護協力に力を入れてきたことは、中国人にも高く評価されています。確かに、世界一の外貨準備を持つ国にどうして援助が必要なのかという疑問も理解できます。しかし、中国は経済規模を拡大させながらも依然として発展途上国であり、富を再分配して貧困人口に届ける仕組みが整っていないのです。二国間関係の改善、対中ビジネスの拡大、中国の安定発展の支持、人道的な観点などのいずれの面からも、対中ODAを続ける意味があると考えます。中国国内の認知度が低いことが問題であるならば、日本側で広報に力を入れればよいでしょう。残念ながら、対中ODAの主力だった円借款の新規供与は07年12月を最後に打ち切られましたので、これに替わる仕組みを考える必要があるのではないでしょうか。
――民主的な地域レジームの構築とは、具体的にはどのようなものですか。
問題別、機能別の地域機構は、既にいろいろできています。大切なのは、構成国がそうしたフレームワークを平等な形で運用することです。「自由、平等、友愛」を原則として、特定国が支配しない仕組みを確立し、やがて形成されるであろう東アジア共同体の運営原理にすべきです。東アジア共同体がどのようなものになるか、現状ではわかりませんが、東アジアが日々、統合に向かっていることは間違いありません。ヒト、モノ、カネ、情報から新型ウィルスまで、さまざまなものの越境現象が起き、ネットワークも、それをコントロールするためのフレームワークも発展しているのです。そこで、こうしたネットワークやフレームワークをどのような原理原則で律するのかが問題になります。日本は常に「和と共生の原理」に則ったレジームにすることを提唱すべきです。そうすれば中小国から感謝されますし、孤立を恐れる中国も今は反対しないでしょう。
――本論文の政策的インプリケーションはどこにあるのでしょうか。
基本的な問題として、日本が主体的、創造的に東アジア外交を展開しなければならないと指摘した点が重要かと思います。日本の外交はこれまで受け身である場合が多く、アメリカでオバマ政権が誕生すれば、それに合わせて対応を考えるといった姿勢でした。しかし今や、アイデアを出さなければ米国も中国も日本を相手にしてくれません。米国に依存するのでもなく、プレゼンスを高める中国に、いたずらに対抗心を燃やすのでもなく、両国と協力して、その力を活用することを考えるべきです。
解説者紹介

高原 明生
東京大学法学部第3類卒業。1988年 英開発問題研究所博士課程修了サセックス大学DPhil。1989年在香港日本国総領事館専門調査員。桜美林大学国際学部助教授、立教大学法学部教授などを経て、2005年より現職。その間、在中国大使館専門調査員、ハーバード大学客員研究員などを務める。主な著作はThe Politics of Wage Policy in Post-Revolutionary China (Macmillan)、『毛沢東、鄧小平そして江沢民』( 共著 東洋経済新報社)、 『現代アジア研究1 越境』( 共編 慶應義塾大学出版会) など。

