多くの国は自国が「中所得の罠」に陥っていると考えている。Lant PritchettとLawrence Summersは、この罠は実際のところ成長の平均への回帰にすぎないという新たなエビデンスを示している。「中所得の罠」だと思っていることにより、政府は目下の問題を間違って解釈しかねず、この結果は重要な示唆を含んでいる。低中所得国にとって、21世紀は魅力的に映るだろうが、19世紀型の問題はいまだ解決されていない。また、急成長の持続には創造的破壊の「創造」と「破壊」という2つの側面が求められるが、政府や経済エリートに受けが良いのはその片方だけである。
何十億の人々の生活水準、あるいはグローバル・システムの進化にとって最も重要なことは、各国経済が次世代にわたり、どれだけ急速な成長を遂げられるかということである。将来の成長見通しを評価するにあたり、従来の考え方では2つの重大な間違いをしてしまうと思われる。
- 第1に、新たな大展開がない限り、これまで急成長してきた国は今後も急成長を続け、停滞してきた国は今後も停滞し続けるだろうと、外挿的に推測をしていることである。
実際には、一般に思われているほど、過去を元に成長を推測することはできないということを、我々は研究で示している (Pritchett and Summers 2014)。
- 第2に、従来の考え方では、「中所得の罠」という概念が支持されている。すなわち、国が中程度の所得水準に達すると、以前より成長が困難になるということである。
我々の研究では、このような傾向はほとんど見られず、しばしば中所得の罠の原因とされているものは、成長率の平均への回帰と考えた方がよいということを示している。
スポーツ記者が「2年目のジンクス」ということをよく言うが、これは1年目に華々しい成績を上げた新人選手が、2年目のシーズンで成績が振るわないという傾向を指す。同様に、「タイム誌の表紙の呪い」ということもよく言われる。著名人やセレブはキャリアのピーク時にタイム誌の表紙を飾り、その後は下り坂になるというものである。いずれの現象も平均への回帰という統計的原則を反映している。一時的な不規則変動が存在するいかなるプロセスにおいても、増加の後は減少、平均を上回る水準の後は落ち込む傾向が見られる。
Pritchett and Summers (2014)において、この枠組みを国の成長率の分析に当てはめ、平均への回帰には頑健な規則性があることを明らかにしている。我々の研究は、国の成長率における過去数十年の間の相関関係は驚くほど低く、一般的に相関係数は0.2~0.3の範囲内であるという先行研究 (例:Easterly et al. 1993) を裏付けるものであった。これは、成長率により高い持続性を想定し、成功も失敗も継続することを前提とした典型的な予測とはまったく対照的である。また、高度に安定した国の特徴である文化や制度の質、開放の度合いなどによって成長実績を説明しようとする多くの一般的な成長理論とも相容れない。成長率の一般的な平均への回帰パターンに基づけば、中国の成長の外挿予測について本質的な疑問が生じ、今後10年間のいずれかの時点で、中国の成長率は大減速するリスクが大きいと考える。
平均への回帰よりも、「中所得の罠」の考え方に何か意義があるのか疑問に思うことは当然である。最近「中所得」に分類されるようになった国は、当然のことながら、最近になって急成長を遂げた国がほとんどであることから、明らかに2つの現象を区別することは困難である。我々は、平均への回帰と比較して、3つの点で「中所得の罠」への懸念が誇張されていると考えている。
どの国を「中所得」と考えるべきか
第1に、中南米諸国からロシア、中国、インドネシア、インド、ベトナム、エチオピアに至る国について議論する場合、「中所得の罠」の意味を理解することは難しい。このような急成長中の(あるいは他の)国すべてが成長鈍化のリスクについて大いに懸念すべきであるということに異論はない。しかし、数十年前に世界銀行が譲許的融資用に設定した任意の基準は別として、もし1人当たり国内総生産(GDP)が米国の11%以下の国々(インドネシア10.2%、インド8.5%、ベトナム8.0%、エチオピア1.8%)までも中所得に分類され、リスクがあるとみなされるのであれば、「中所得の罠」が何を意味するのかまったく明確ではない。2011年の1人当たりGDPの世界平均は1万4467ドル、中央値は8491ドルだった。メキシコ(平均GDP 1万2709ドル)やマレーシア(1万3468ドル)、トルコ(1万4437ドル)といった国は明らかに「中所得」国であり、このような経済発展レベルに達したことで、さらなる発展を継続することが難しくなるかもしれない。しかし、インドがメキシコの2011年時点の1万2709ドルというレベルに達するには、20年間、6%の成長率を続けることが必要であり、エチオピアの場合、47年かかる見込みである。もし成長中のすべての国が、現在の所得水準に関係なく「中所得の罠」に陥るリスクがあると考えるのであれば、「中所得の罠」を平均回帰の成長ダイナミクスから切り離すことは不可能である。
所得水準は成長鈍化の予測材料として有効ではない
第2に、成長鈍化(低成長への離散的変化)の相関を実証的に比較してみると、所得水準よりも急成長の方が減速の可能性を予測する材料として有効であることがわかった。我々は最近の論文(Pritchett and Summers 2014)において、Kar et al.(2013)から成長エピソードのタイミングを用いて成長鈍化のダミー変数を推定し、それを現在の成長率および1人当たり所得レベルの4次関数形で説明する回帰分析を行った。
図1は、平均的な国の成長率、インドの年間成長率6.3%、中国の年間成長率8.6%における、それぞれの予測値を3つ描いたものである。
第1に、所得の4乗項までが同時に有意かどうかF検定を行った結果、0.037水準で有意であると認められるが、これはすべて超高所得の国とその他のサンプルとの差に由来する。つまり、高所得の国ではリスクが徐々に低下するということを反映している。同様の回帰を2万5000ドル以下(あるいはさらに低基準)の国について推定すると、所得項は同時に有意にはならない。
第2に、所得の4次関数形の回帰モデルにおいて、高所得になるにつれて減速のリスクが高まりその後小さくなるという「中所得の罠」の特徴が若干見られるが、そのピークと谷の差は小さい。平均的な成長率の国については、減速の可能性が最も低いのは所得水準が約5500ドルの場合で4.3%であり、所得水準が約1万9000ドル時点で5.7%まで可能性は上昇する。モンゴルやジャマイカの所得水準から、ハンガリーやバーレーンといった高中所得国まで、予想される減速の可能性はどの年をとっても1.4ポイントの上昇にしか過ぎない。当然、低いF検定の値を考えると、これは予測値の標準誤差よりもはるかに小さく、この範囲内では「中所得の罠」に陥る最大リスクと最小リスクとの間に有意の差はない。
急成長は将来の減速の有効な予測材料
第3に、所得水準による影響が極めて弱いのとは対照的に、成長鈍化の可能性に対する現在の成長率による影響は大きく、有意かつ重要である。成長率が1ポイント上昇すれば、減速のリスクは1.46ポイント上昇する。これは「中所得」層への移行による谷からピークまでの上昇に等しい。過去の成長率に関するT値は13.3である。図1に示すように、現在の中国の成長率8.63%における鈍化の可能性は14.4%と予測され、同じ所得水準の場合、サンプルの平均的な成長率1.84%における鈍化の可能性はわずか4.5%となり、10ポイントの差がある。
したがって、このような成長鈍化の相関の予測によると、急成長中の国の成長鈍化リスクはかなり大きいが、それは平均への回帰によるところがほとんどである。一方、「中所得の罠」による影響は小さく、「中所得の罠」のリスクがピークにシフトした場合でも、推定値は実証的にほとんど価値がない。
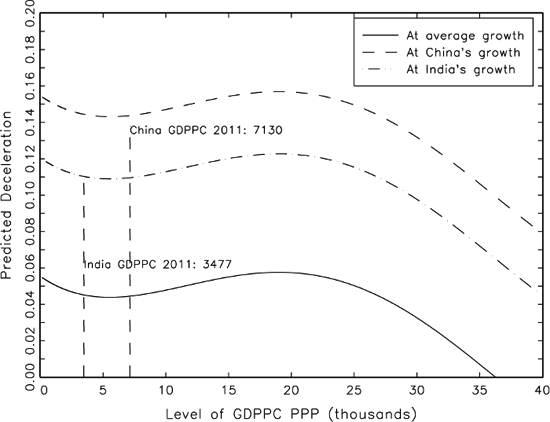
統計的有意性の低さ、実証的影響度の低さ、成長の予測変化における大きな違いという3つの研究結果は、成長加速率を前期の成長率と所得の4次関数形で説明する5年単位の単純なパネル回帰分析でも当てはまる。加速の可能性はある程度まで上昇し、それを超えると低下する。しかし、1万1000ドル以上の所得水準で、「中所得の罠」が成長の加速を低下させる純粋な影響度は、平均への回帰による効果と比べて小さい。前期の成長率の係数推定値は0.83であり、力強い平均回帰と一致する。
成長持続政策を採用する誘因が、「中所得の罠」ではなく、平均回帰論に基づくかどうかをなぜ我々は気にしなければならないのか。どちらの論調においても、急成長の維持は難しいということと、低成長への最短ルートは急成長の間に油断しているということが強調されている。しかし、重要な相違点が3つ考えられる。
政策判断においての重要な3つの相違点
第1に、2年目のジンクスの原因は「選手の2年目に何が良くなかったか」を問うことでは見つけられない。2年目のジンクスの原因は、1年目が例外的にラッキーだったことにつきるかもしれない。2年目は成功することが質的に難しくなったわけではなく、選手が下手になったわけでもない。物事は収斂に向かう傾向があるに過ぎない。米国の金融危機の経験から苦痛を伴って学んだように、物事が順調に進んでいるように見える時こそ、将来について慎重になることが最も重要である。成長維持の問題を「中所得の罠」と決めつけることは、政策によって実際にできる以上に成長鈍化リスクを上手に管理できると示唆することになってしまう。
多くの人が、中国の成長が減速することはない、なぜなら減速は政治的に高くつくため、中国の政策立案者は何がなんでも回避しようとするだろうと言う。だから減速を回避すべく行動するだろう。そして既知の「罠」は容易に回避できるはずである。しかし、持続不可能なまでに高い成長率を維持しようとすることは、その後の調整をより厳しいものにしてしまう可能性がある。友人であるRicardo Hausmannが言うように、「8%成長から4%成長への道はマイナス2%を通る場合が多い」。
第2に、成長の鈍化という一般的なリスクを「中所得の罠」と決めつけてしまうことによって、目下の問題を間違った視点で捉えてしまう恐れがある。すなわち、中所得国から先進国に移行する最終段階にどう対応するのかということであり、バイオテクノロジーやソフトウェア・エンジニアリング企業といった先端産業を誘致先に選びたいという「明るい光」の誘惑を伴うものである。しかし、世界銀行が「低中所得国」と分類するほとんどの国にとって複雑なのは、21世紀が魅力的に映る一方、対処すべき19世紀型の問題がいまだ解決されていないことである。都市の水道や衛生設備が極めて不十分なため、インド人の6割は今でも屋外で排便している。2010年、ベトナムでは家計支出に占める食費の平均割合は依然として5割であり、中心となる農業問題に引き続き取り組む必要がある。
第3に、急成長の持続を非常に困難にしている要因の1つは、成長には創造的破壊の「創造」と「破壊」の2つの側面によることであるが、政府や経済エリートに受けが良いのはその片方だけである。新たな投資、新たな産業、新たな利益をもたらすことから,誰もが「創造的」なことを好む。しかし、一般的に持続的な経済成長は、新たな産業が生まれるという継続的な構造変化に依存するが、その一方で古い産業は、相対的にもしくは絶対的に縮小する。持続的な経済成長には不可欠であるものの、政府も既存企業も破壊を好まない。競争力のない産業の淘汰には、地理的シフトや雇用の転換、企業の退出を伴うためである。以上から、成長を継続させること(多くの国が成功している)に比べ、急成長を持続させること(ほとんどの国ができていない)はより困難になっている。これは「中所得」水準で起きているが、産業革命時における地主貴族に対する新興産業資本家の脅威によって引き起こされた問題から今日における最先進国が直面している様々な問題まで,あらゆる発展段階における経済的移行の一部でもある。成長の持続は「中所得」に限った問題ではなく、あらゆる発展段階における根本的課題なのである。
最後に、統計的エビデンスから分かったことは、たとえ急成長を長期にわたって続けてきた国においてもそれは当然のことではないということである。急成長を続けるためには優れた政策を常に更新すること、そして運も必要である。これは中所得層に属する国だけではなく、すべての国にとって厳しい現実である。
本稿は、2014年12月11日にwww.VoxEU.orgにて掲載されたものを、VoxEUの許可を得て、翻訳、転載したものです。



