| 解説者 | 宮川 努 (ファカルティフェロー) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0096 |
| ダウンロード/関連リンク |
先進国の経済成長を議論する際、生産性の向上がカギを握る。企業レベルでの議論では、個々の企業がいかにイノベーションを実現するかに加えて、最近は、企業パフォーマンスを改善するための企業組織のあり方も重要な課題として浮上している。宮川ファカルティフェローらは経営管理の向上、すなわち組織改革など組織管理面での改善と、モチベーションの維持など人的資源管理に着目し、日韓で比較研究を行った。経営管理面での改善が日韓ともに企業パフォーマンスの向上につながるとの分析結果から、政策支援と企業努力を通じて、経営スタイルの見直しを進める必要があると指摘する。また、韓国企業が日本企業に経営管理面でキャッチアップしていることも明らかになった。
――この論文は大規模な研究プログラムの一環ですが、まず研究プログラムの全体像を教えてください。
経済産業研究所(RIETI)では2011年度に「産業・企業生産性向上」と題した2年計画の研究プログラムがスタートしました。生産性などに関する7つの研究プロジェクトを包含する大規模なもので、深尾京司(一橋大学経済研究所所長)がプログラムディレクターとして全体を統括しました。そのプロジェクトのうちの1つが、私がプロジェクトリーダーを努める「日本における無形資産の研究」です。
人的資産マネジメントや組織改革など広義の無形資産は生産性向上に寄与
――無形資産に注目した理由は何ですか。
多くの実証研究により、無形資産が生産性の向上やイノベーションに大きな役割を果たすことが明らかになってきたからです。ここでいう無形資産とは研究開発投資、ソフトウェア、特許、意匠・デザイン、ブランドといった狭義の資産にとどまりません。人的資産マネジメントや組織改革のための投資なども含めた包括的な資産です。
研究開発投資をはじめとする狭義の無形資産が生産性の有力な決定要因になるということは、かなり早くから認識されていました。これに対して、人的資産管理や組織改革の大切さがクローズアップされたのは、最近のことです。契機になったのは、1990年代の後半から進行したIT革命です。
過去の技術革新の場合、新たな技術や機器を導入すれば、それだけで生産性が上がるケースが多く見られましたが、IT革命の場合は全く違います。ソフトウェアの導入はもちろんですが、そのソフトを使いこなす人材が必要ですし、通信網の発展で組織内の階層がフラット化するなどの変化も起きます。先端機器やソフトの導入に加えて、人的資産の管理手法や組織の在り方を見直さなければ生産性は向上しないのです。このように重要性を増す無形資産を包括的に捉えて、産業・企業レベルで計測し、その経済効果を分析することは、大きな意義があるのです。
――無形資産の研究プロジェクトは、どのような研究者が、どんな問題意識や目的で取り組んだのでしょうか。
共著者の枝村一磨(科学技術・学術政策研究所)、Keun Lee(ソウル大学)、Jung Hosung(サムスン経済研究所)、金榮愨(専修大学)など10人近い研究者が参加していますが、特徴的なのは経済学だけでなく経営学や人的資源管理の専門家が加わり、経済学と経営学の学際的な研究チームになっていることです。
人的資源管理や組織改編は生産性を考える上で重要な概念ですが、実際にデータを集めたり、産業ごとに議論したりするのは難しいです。「産業・企業生産性向上」プログラムではマクロレベルでも取り組んでいますが、その頑健性をチェックする上では、やはりミクロベースでの分析が必要になります。その点に集中した研究を進める中で、インタビュー調査を活用して組織管理と人的資源管理を評価する先行研究に行き着きました。その枠組みを使って、日本あるいは韓国の経営環境を考慮しながら、より精密な質問紙を作成して調査を行うことにしました。組織管理や人的資源管理などの無形資産が生産性の向上にどのような役割を果たしているかを検証するのが狙いです。
――インタビュー調査の核となる質問紙の内容を教えてください。
参考にした先行研究としては英国の経済学者であるニコラス・ブルーム(Nicholas Bloom)とジョン・ヴァン・リーネン(John Van Reenen)の論文(2007)が挙げられます。ちょうど、私がロンドンに在外研究で滞在していたころにこのような研究活動がされていることを知りました。
実際にインタビュー用の質問を作成するのにあたっては、まず、上記の論文との比較を可能にするため、できる限り同じような基本質問項目を作成しました。その上で、日本や韓国の経営環境を踏まえて色々と付加的な質問を用意しました。
質問紙は経営管理について尋ねるもので、組織管理6問、人的資源管理10問に分かれています。例えば組織管理については、「過去10年の間に組織改革をしたかどうか」、そして実施した場合はその時期や対象となった従業員の規模、改革に要した期間などを質問します。さらに、組織改革の理由と、主たる目的についても書き込んでもらいます。
先行研究にはない独自の工夫としては、組織改革では、組織改革の範囲や権限委譲という項目を加えました。それからインフォーマルなコミュニケーション、いわゆる根回しのような日本的な部分の質問を追加しました。また、人的資源管理については、欧米では当たり前なのでわざわざ質問するまでもない項目、つまり、成果主義の原則や専門性などを問う質問を新設しています。日本では成果主義の原則や職員の専門性については、企業によって異なると思われるので、きちんと質問する必要があります。逆に、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)のように、欧米よりも日本で発達した人材育成法についても、明示的に尋ねておくことが必要なため、質問に加えました。
――具体的な質問内容を決めるのが最も重要で、大変だったと思いますが、ほかにどんな苦労がありましたか。
メンバーが議論を重ねて、質問紙の作成には結局、約1年を費やしました。かなり苦心しましたね。
まず、そもそも、どうやって回答を集めるかです。Bloomらは電話による聞き取り調査を行いました。大学院生がアルバイトでこなしたのですが、欧米では経営学を専攻する学生がインターンのような形で実際の調査活動の労働集約的な部分を請け負うということがあるので、実施可能な方法といえます。しかし、日本にはそのような環境はありませんし、大量の人を集めていっせいに電話で調査をするというのはコストもかかって大変です。
そこで、私たちは対面方式の聞き取り調査を実施しました。その上で、調査で記入された評価点が本当に妥当なのかどうかについて、メンバー全員で評価点のシートを見ながら、そのスコアが正しいかどうかを議論しました。その際、具体的な事例についての情報が欠かせませんので、聞き取り調査の時には具体例についても相手に聞いておく必要があります。このように工夫しながら、丁寧に調査しました。
インタビュー調査は2008年と、2011~12年の2回にわたって実施しました。2回目の調査では日韓比較がしやすいように質問紙をさらに改善しました。具体的には韓国の実態を知るために、主要製品の海外におけるシェアなどの質問項目を加えたりしています。また、1回目の調査には非上場企業も加えていたのですが、日本企業の業種が電子製造、情報サービス、小売業に偏ったせいか、パフォーマンスの分析に不満が残りましたので、2回目の調査では上場企業に焦点を絞りました。
日韓企業800社以上が対象の大規模なインタビュー調査を2回にわたって実施
――本論文の特徴についてご説明ください。
1回目と2回目の調査では、それぞれ日韓合計で800~900社の企業からデータを得ることができました。経営関連の主要データがそろったことが特徴といえます。大学などがこうした調査を実施する場合は、調査1回あたりにカバーできる企業数は100社に満たないのが実態ですが、RIETIの調査ということで、かなりのデータがとれました。経済学の手法を使って、Bloom and Van Reenen(2007)のように、日本企業について実証的経営分析をしたケースはあまりありません。
分析手法そのもので新規の点があるわけではないのですが、日韓比較を行ったというのは新規の試みだと思います。Bloomらも国際比較研究を行っていますが、中国は比較対象に入っているのに、韓国は含まれていないからです。
――分析結果は、どのようなものでしょうか。
まず、予想されていたことがデータ的に裏付けられたという点から、お話しましょう。韓国は組織管理、人的資源管理の面で、日本にかなりキャッチアップしていることが明らかになりました。集計したデータで日韓比較をすると、GDPの比率でみても、韓国の無形資産には進歩が見られることがマイクロデータでも裏付けられました。
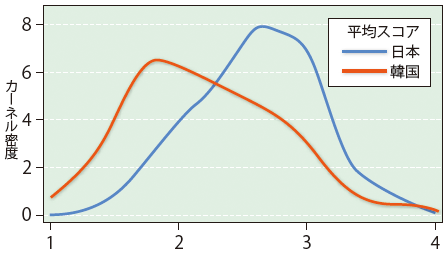
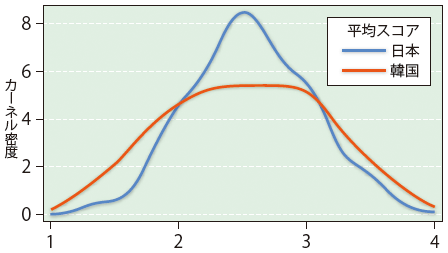
| (単位:%) | ||
| 日本 | 韓国 | |
|---|---|---|
| 75%以上 | 66.4 | 43.6 |
| 50%~75% | 16.7 | 18.2 |
| 25%~50% | 9.7 | 18.8 |
| 25%未満 | 6.0 | 19.4 |
|
※日本は、不明と回答した企業の割合をのぞいた比率 注) [原表はTable7-1] |
||
それから、韓国製品の海外志向の高さが挙げられます。一方で、日本製品は国内市場志向が高く、国内の競合社数が多いことが確認されました。
次に、予想されていなかったことが判明したという点ですが、日韓の経営環境の差は、それだけでは生産性に影響していませんでした。韓国がキャッチアップ傾向にあるという特性の差はあるのですが、それが日本と韓国の生産性の差として表れるということではありません。国内競合社数が多いと生産性が低くなると予想していたが、そうでもなかったですね。
最後に先行研究では得られなかった知見です。経営管理の向上が資本と労働のどちらに効果を及ぼすかというのは興味深いことなのですが、経営管理が向上すれば、資本の効率利用にプラスの効果をもたらす一方で、労働の効率利用には影響しないという結果が得られました。経営管理の向上は、労働者が機械設備をうまく使えるようになるため、資本の効率性を上げる効果があると考えられます。しかし、労働効率性は上がりませんでした。経営管理の向上は、労働をより効率的に使う、つまり、労働の効率性、労働の質を高めることにならないのです。
経営管理は資本の効率向上に寄与するが、労働の質の向上にはつながらず
――ちょっと意外な結果が出ましたね。
その理由としては、経営管理のスコアが高いことだけが、必ずしも企業のパフォーマンスの向上につながるわけではないためと考えられます。
企業を次のように3分類してみましょう。①終身雇用制を軸とする「伝統型」企業、それから②成果主義を軸とし、終身雇用を取らない「アングロサクソン型」、最後に、③伝統型とアングロサクソン型の両方の要素を持つ「ハイブリッド型」の3種類です。日本企業は「伝統型」のパフォーマンスが良好なのに対し、③の「ハイブリッド型」がいちばんよくないという結果が出ました。これは③の場合は、経営管理面での改善がまだ途上にあるため、中途半端な状態に陥っている可能性があるためと思われます。
アングロサクソン的な経営管理は、成果主義を軸にする一方で終身雇用制をとらないという経験と土台に支えられているので、フレキシブルな人事制度など改善努力をすれば経営効率が向上し、企業のパフォーマンス改善が期待されます。これに対し、日本企業の場合は最近になってようやく成果主義の導入が盛んになったという歴史の浅さがありますし、終身雇用制がまだ色濃く残ってフレキシブルな人事システムになっていない場合も少なくありません。経営管理スコアが高くても、それが一様に企業のパフォーマンスの改善に直結するというわけではないのはそのためです。
――日韓では分析結果に違いがありましたか。
日本と韓国の違いはありました。韓国の方が人的資源管理のスコアが企業パフォーマンスとより密接な関係にあります。これに対し、日本は組織管理の方が生産性への効果が認められます。
それから韓国企業が企業目標を変える際の意思決定のスピードが速いという結果も得られました。
| (単位:%) | ||
| 日本 | 韓国 | |
|---|---|---|
| 1ケ月未満 | 5.8 | 25.6 |
| 1ケ月以上3ケ月未満 | 16.0 | 40.1 |
| 3ケ月以上6ケ月未満 | 4.6 | 17.5 |
| 6ケ月以上1年未満 | 63.2 | 10.4 |
| 1年以上 | 10.4 | 6.3 |
| 注) [原図はTable7-3] | ||
――本論文の政策的含意は何でしょうか。
組織改革と人的資源管理はいずれも日本の生産性の向上には重要です。ただ、組織改革や人的資源管理が改善されれば必ず企業パフォーマンスが上がるというわけではありません。成果主義を導入したからといって、人事政策との組み合わせ方によっては、思ったように成果が出ない可能性もあります。どの企業にも当てはまるような一様なやり方というものはないのです。
政策面からいえば、労働市場改革を進めて新規企業を育てようとするなら、労働市場改革を進めて企業がフレキシブルな人事体系を採用できるようにした方がよいでしょう。今の労働市場の規制は硬直性があり、より流動的な労働市場のほうが開業もしやすいし、その方がフレキシブルな人事体系を採用し、生産性も向上が見込めるからです。しかし、労働市場改革をすれば、すべての企業の生産性が上がるわけではないのです。業種によっても、その効果は異なります。大事なことは、一律の政策展開を目指すのではなく、企業が様々な選択肢の中から、最適なものを選んで、自社の経営改革とつなげることができるようにすることなのです。
今後の課題はサービス業と準公的部門の研究――非正規雇用者の働き方の分析がカギに
――今後の課題研究の方向を聞かせて下さい。
特にサービス業についてもっと精緻な分析を試みたいと思います。そもそも、Bloomらは、現行の彼らの調査は製造業向きのものだと思っており、サービス業向けに特化した経営管理の調査の仕方があると考えていました。アンケート調査を使うとしても、どのような経営管理がより望ましいのか、という判断基準は製造業と異なる可能性があるからです。確かに、サービス業は業種によって特性の差が大きく、しかも、非正規雇用の従業員が多いという特徴があります。この点をどう乗り越えていくかは大きな課題といえます。
Bloomらはサービス業の代表例として病院サービスを取り上げていますが、その場合のパフォーマンスの指標として手術の成功率を使っています。ひとくちに手術といっても千差万別ですし、このようなデータを取るのはなかなか大変です。教育や医療はサービス産業としてとらえることもできますし、準公的部門の視点から考えることもできるでしょう。実は、現行の調査では準公的部門の無形資産がカバーされていません。アプローチの仕方が難しくて、データも取りにくいからです。悩ましい問題ですね。これは将来的な課題となります。
――この研究プログラム自体はどうなるのでしょうか。
研究プログラム自体は今年度で終わりますので、積み残した研究課題は別の形で引き継いでいくことになります。ただ、「無形資産」研究プログラムでは、今年度中に6本の論文を発表する予定です。これらの研究成果を中心に書籍化も目指したいと思います。
解説者紹介
学習院大学経済学部教授。1978年東京大学経済学部卒業。2006年一橋大学大学院経済学博士号取得。1978年日本開発銀行入行。その間にも、88年ハーバード大学国際問題研究所客員研究員、89年エール大学経済成長センター客員研究員、また、92年から数年に渡り日本経済研究センター主任研究員等も務める。2004年よりRIETIファカルティフェロー。2006年よりLondon School of Economics客員研究員も兼任。主な著作物:『長期停滞の経済学』東京大学出版会(2005)、『日本経済の生産性革新』日本経済新聞社(2005)等多数。


