| 解説者 | 吉川 洋 (シニアリサーチアドバイザー・ファカルティフェロー) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0086 |
| ダウンロード/関連リンク |
1930年代に登場した際、革命とさえ呼ばれたケインズ経済学は、1970年ごろを境に、「ミクロ的な基礎づけを持たない」という批判を浴び、新古典派経済学に主流の座を譲るようになった。しかし、吉川SRA/FFは、ケインズ経済学に対するこうした批判が正しいのかどうか、これまでの考え方を根本から覆すような新たな視点から検討を行った。
吉川SRA/FFは、新古典派経済学における代表的な企業と家計を想定する理論モデルは自然科学の潮流からは異質の発展を遂げているとして、自然科学、特に統計物理学にまで視野を広げ、多数の経済主体がそれぞれの立場からとる合理的で目的のある行動を確率的な視点からマクロ全体の把握につなげるアプローチにより、ケインズ経済学にミクロ的な基礎づけを与えられると結論づけ、ケインズ経済学の有用性を再度、考え直すべきだと強調する。
――まず、執筆に至った問題意識を教えて下さい。
この論文(DP)は、マクロ経済学の基礎理論に関する私の考えについて、RIETIで発表の機会を得たものです。「基礎理論」などと聞くと、経済政策とは何の関わり合いもない浮世離れした論文だと思われるかもしれません。しかし実際には、この論文で取り上げている内容は、現実の経済政策と深く関係しています。アベノミクスを議論する上でも重要な関連がありますので、それについては後ほど説明したいと思います。
執筆の問題意識をお話しするにあたっては、ケインズ経済学が盛んだった今から40年ほど前に遡る必要があります。1970年頃までは、経済学は二刀流だという考え方が世界の主流となっていました。つまり、ミクロ経済学とマクロ経済学の二刀流と考えられていたのです。
ミクロ経済学は新古典派の経済学で、価格をシグナルとして、さまざまな資源は諸々の制約の下で効率的に配分されていくというメカニズムを明らかにするという考え方にたっており、価格理論とも呼ばれました。これに対するマクロ経済学は、当時はケインズ経済学でした。資本主義経済は市場を中心に運営され、色々な用途に資源を効率的に配分していきますが、深刻な不況による失業者の増加などで、市場経済は機能不全に陥ることがあります。ケインズ経済学では、財政出動のような財政政策や金融政策によって景気を刺激し、市場の機能不全状態の改善を目指します。これは、戦後の代表的な経済学者であるサミュエルソンなどの考え方でもあります。
このように、今から40年前は、マクロ経済学といえばケインズ経済学でしたが、1960年代の終わり頃から学界の様相が変わってきました。経済主体として家計、企業といったミクロの経済主体の活動をもとに、マクロの経済を把握しようという考え方が広まり、マクロ経済学のミクロ的な基礎づけが重視されるようになりました。こうした視点からケインズ経済学はミクロ的な基礎づけがないと批判されるようになり、マクロ経済学の世界ではミクロ的な基礎づけを重視する現在スタンダードとされる経済学が、ケインズ経済学にとって代わるようになったのです。
ミクロ的基礎づけのあるマクロ経済という"常識"への疑問
――ミクロ的基礎づけとは、一体どのようなことでしょうか。
ミクロ経済学では、経済主体としては個人あるいは家計、企業を考えます。そして、家計であれば、所得制約の中で効用の最大化を目指し、企業であれば利潤を最大化するように活動する、というように考えます。制約条件がある中で、効用や利潤を最大化するために最適な選択や行動を行う点に着目するもので、最適化の議論といえます。
ケインズ経済学では最初からマクロ経済を対象としているのに対し、それに批判的な議論は、企業や家計の最適化行動を考慮した上で、マクロ経済を考えるべきだと主張します。とはいえ、家計や企業の最適化とひと口にいっても、企業は400万社を超えますし、家計は6000万世帯にのぼるとすれば、それぞれの個別の家計や企業の動きを全て捉えて分析することは不可能です。
そこで、代表的な家計や企業を想定し、それについて詳細に調べるという手法をとるのです。その上で、マクロ経済は、代表的な家計や企業を相似的に拡大することで把握できる、と考えるのです。これが現在、スタンダードなマクロ経済学での考え方なのです。
――ミクロ的な基礎づけがマクロ経済学でも求められるということですね。
ケインズ経済学はかつて、「どマクロ」などという蔑称がついたくらいですので、現在のスタンダードな考え方からは、ミクロ的な基礎づけに欠けるとの批判を浴びてきました。しかし、本当にそうなのだろうか、というのがこのDPの出発点です。ケインズ経済学がミクロ的な基礎づけに欠けると批判されますが、そもそも現在スタンダードとされている経済学の考え方において、果たして本当にミクロ的な基礎づけがなされているのかを問い直したいと思っています。
――これまでの考え方との差は大きいのでしょうか。
このDPは、スタンダードなマクロ経済学が過去40年間とってきた方法論とは180度異なる考え方にたっています。詳しい議論をする前に、自然科学でとられている方法論について、考えてみましょう。
物理学であれ、化学であれ、生物学であれ、生態学であれ、自然科学の分野ではいずれも二刀流の発想をとります。つまり、全体を把握するマクロ的なアプローチと、1つのモノを把握するミクロ的アプローチを分けているのです。
1つの事物や事象を追うミクロ的なアプローチの具体例として、1つのボールを空に投げたり、太陽の周りを地球が回転するなどのケースを考えましょう。この場合は、観察対象である特定の動き、つまりボールや地球の動きをきちんと把握して分析します。これはごく当たり前のこととして理解しやすいでしょう。
では、マクロ的なアプローチの場合はどうでしょうか。ここでいうマクロとは、たくさんのミクロが入り込んでいたり、たくさんのミクロのユニットで構成されたりする場合を指しています。具体的には、部屋の温度を例に挙げてみましょう。部屋の中にはたくさんの空気の分子があり、ものすごい勢いで動き回っています。空気全体の温度がマクロとすれば、空気の分子の動きがミクロにあたります。マクロ(空気全体、つまり部屋の温度)を知ろうとして、個々の空気の分子の動きを把握するために「代表的な空気の分子」に着目して詳細にその動きを分析しても、マクロである部屋の温度は分かりません。このように、統計物理学では、マクロがミクロで構成されるとしても、ミクロ(ここではミクロは量子といった意味ではなく1つのモノといった意味)とは違うマクロの視点で考えます。たくさんのミクロの動きを詳細に観察しても、マクロの分析には意味がないからです。
化学でも生物学でも生態学でも、物理の考え方を基本としています。こうした自然科学で展開されてきた常識から見れば、これまで40年近くの間、スタンダードとされてきたマクロ経済学の考え方は異質な発展を遂げたといえます。
統計物理学という新たな視点でマクロ経済現象を見つめ直す
――分子の動きに関する説明は納得できます。でも、人間の活動にも適用できるのでしょうか。
たしかに、経済学においては、個人でも家計でも脳を備えた人間が対象であり、人間は目的を持って行動をするので、無機質な分子と同列には論じることができない、という反論がありえます。
そこで、経済学の視点からもとり上げられることが多い車の渋滞について考えてみましょう。車の流れそのものは無機質にみえますが、個々の車を運転しているのは、脳を備えた人間です。ですから、運転者は安全で快適な運転を目指して判断をしながら運転をします。こうした個々の自動車の運転はミクロ現象で、そうしたミクロが集まることによって生じる渋滞はマクロ現象といえます。
この渋滞というマクロ現象を引き起こすメカニズムは、統計物理学によってかなりの部分を説明することができるのです。道路を碁盤の目のような升目に分けて、1つ前の升目が空かないと自動車が先に進めないというような簡単な進行上のルールをつくるだけで、渋滞の発生メカニズムがかなり明らかになります。さらにいくつかルールを追加すると、より精緻に渋滞のメカニズムを再現することができます。
これをスタンダードなマクロ経済学の発想でアプローチした場合にはどうでしょうか。「代表的な運転手」が合理的な行動をしたことで渋滞というマクロ現象が起きるということになりますが、それでは説明できませんね。伝統的な経済学では「外部性」という経済主体間の相互作用がトラブル発生の原因として考えられてきましたが、これは「標語」だけで、それから先の定量的な分析には進めません。
――新古典派の「ミクロ的な基礎のある」マクロ経済学という主張に疑問が生じるわけですね。
過去40年間のマクロ経済学の流れでは、ケインズ経済学にはミクロの基礎的な裏づけがないといわれ、欠陥品扱いされてきました。しかし、そのような認識は正しくないと考えています。なぜならば、そのような批判をしてきたスタンダードなマクロ経済学において、「しっかりしたミクロ的な基礎」だと考えられているものが、より広い学際的な視野からみた際には、先述のように独りよがりとも感じられるほど異質なものに映るからです。
生産性に着目し、ケインズ経済学にミクロ的基礎づけを与える
――実企業の生産性にも着目していますね。
ケインズ以来、不完全雇用など労働がフルに活用されない場合、失業がその指標として指摘されてきたのですが、実はもう1つ重要な指標があるのです。それが生産性です。生産性の分布は擬似失業の重要な尺度ともいえます。たとえば、工場が不況時に従業員の解雇はしないが、ペンキ塗りや敷地内の雑草を抜くなど、生産に直接結びつかない業務を行わせるような場合は、失業率は上がりませんが生産性は下がります。実際、リーマンショック後に生産性の分布は下方にシフトしました。
――これまでの議論を現実のマクロ経済現象に当てはめて見ると、どのようなことがいえるのでしょうか。
2008年のリーマンショック後のマクロ経済を考えてみましょう。リーマンショック後に世界中で失業率が上昇しました。ひと昔前なら、ケインズ経済学を知っている人であれば、学部生であっても「有効需要が落ち込んだからだ」と簡単に説明することができました。アメリカについては金融危機から設備投資や住宅投資が非常に落ち込んだことが挙げられますし、日本では輸出の落ち込みが顕著でした。このように需要減少の理由はさまざまであっても、総需要の減少によって不況が生じるということを明確に説明できたのです。しかし、ケインズ経済学を捨て去ってしまった現在のスタンダードな経済学では、リーマンショック後に失業率が上昇している現状を説明するのに、非常に複雑な議論をしないといけません。
そもそも、リーマンショック後に各国政府が財政出動をしましたが、それは現在スタンダードとされるマクロ経済学の議論ではストレートに出てこないものです。
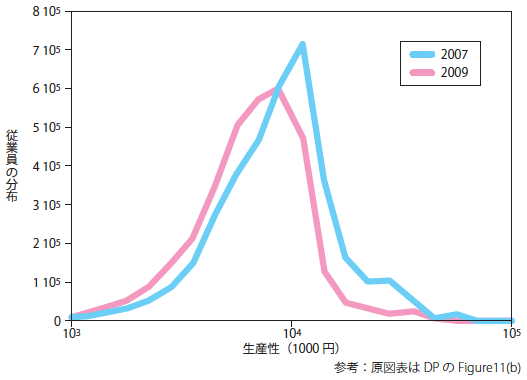
このように生産性を考慮に入れたモデルを構築することで、ケインズの有効需要の考え方に、ミクロ的な基礎づけを与えることができるのです。
新たな視点が解明するリーマンショック後の世界
――アベノミクスで注目されている期待インフレ率についてはいかがですか。
デフレ下ではお金が正のリターンを生むので、その結果として人々はお金を持つことにしがみつきます。しかし、もし、期待インフレが上昇すれば、人々はお金にしがみつくのではなく、モノを買い始めるようになるという理屈になります。そこで問題になるのは、デフレの下で、そう簡単にインフレ期待が起こせるのかどうかということです。
現在のスタンダードな経済学では、ミクロの主体の動きを分析する際の理論モデルの中で、代表的な家計1人、代表的な企業1社および政策担当者の3者が互いに向かい合っている構図を考えます。ちょうど、碁でも打っている格好になります。仮に、政策担当者を日銀だとした場合、代表的な家計である「the 家計」は常に日銀の動きを見ていることになっているわけです。
こうした理論モデルの中では、日銀が金融政策という明確なサインを出していれば、日銀に相対するthe家計は1人ですので、そのサインを理解して「期待インフレが起きる」と考えざるをえないわけです。これが、スタンダードな経済学において「しっかりとしたミクロの基礎づけ」と考えられているものなのです。
――現実の経済現象もそのとおりになると考えられますか。
私自身は、こうした理論モデルは全くおかしいと考えています。スタンダードなモデルの中では、複数のミクロ主体である家計6000万世帯と企業400万社超が、それぞれ1つのマクロをシェアしています。しかし、企業や家計が合理的な行動をするのは、それぞれの「小宇宙」の中で行うものです。個別の企業や家計が日本経済全体のことを考えて、合理的なミクロ経済活動をしているわけではないのです。ですから、1つのマクロ経済ですべてのミクロの経済主体が共有するというモデルは非現実的なものです。もちろん代表的企業や家計といった考え方は受け入れ難いものです。
繰り返しますが、個々の企業や家計を取り巻く経済環境はそれぞれ異なります。たとえば、企業でいえば、外食チェーン、自動車会社、鉄鋼会社が相互に共通点をたくさん持つとは考えにくく、むしろ、別々のビジネス環境にさらされていると受け止めた方が良いのではないでしょうか。
さらに、碁や将棋のように、日銀と「the家計」と「the企業」が対座しているという構図にも、疑問があります。先ほどの理論モデルに照らせば、アベノミクスで日銀が国債を大量購入すれば、日銀の当座預金も大きく変わるので、個々の家計や企業も日銀の当座預金の変化を知っていた上で期待インフレを抱くという図式が簡単に成り立ちます。しかし、実際には、大企業の役員であっても日本銀行の当座預金残高がいくらかなのかは知らない人が多いのではないでしょうか。それはある意味当然で、彼らにとっては通常業務を遂行する上で必要とされる情報ではないからです。このように、それぞれの企業や家計は自分たちを取り巻く領域や環境の中で合理的に行動しているのであって、日銀の当座預金残高をみてマクロ的に合理的な行動をとっていると想定するのは無意味です。
――今後の研究について聞かせてください。
統計物理学の視点を生かした実証研究はRIETIの「中小企業のダイナミクス・環境エネルギー・成長」研究プロジェクト(プロジェクトリーダー:青山秀明FF(京都大学))においてもメンバーの1人として取り組んでいます。統計物理学による理論・実証研究はまだ緒についたばかりですが、もっと進めていき、多くの人に関心を持っていただきたいと思っています。
このインタビューを読んで関心を持たれた方、あるいは疑問や反論をお持ちになった方は、DP本文(「StochasticMacro-equilibrium and Microfundations for KeynesianEconomics」)をぜひ、読んでいただければと思います。
ミニ解説
「個々の経済主体の合理的行動と確率」
個々の企業や家計などは、空気の分子のようにランダムに行動するわけではなく、それぞれの立場から合理的に行動する。雇用を例に取ると、企業も個人も生産性や需要など、さまざまな条件の中で最適の選択をしようとする。しかし、個々の事例において、どのようなミクロ要因(ショック)でミクロレベルの均衡が生じたのかを知ることはできないので、個々のミクロに着目してマクロを把握するのは困難である。
そのため、新古典派は代表的な企業や家計などを想定するのだが、吉川SRA/FFは発想を転換して、統計物理学のアプローチを援用する
つまり、マクロを把握するために、個々の企業や家計などの行動を確率的なものと考える。企業や家計などがミクロレベルでは合理的な行動をしていても、その合理性がマクロ全体で共通しているわけではなく、マクロ経済を分析する第三者にとってはむしろそれを確率的なものと考えるほうが有効だからだ。
解説者紹介
1978年ニューヨーク州立大学経済学部 助教授。1982年大阪大学社会経済研究所 助教授。1988年東京大学経済学部 助教授。1993年東京大学経済学部教授等を経て、1996年4月より東京大学大学院経済学研究科 教授。主な著作物:『デフレーション』、(日本経済新聞出版社,2013年)、『いまこそ、ケインズとシュンペーターに学べ』(ダイヤモンド社,,2009年)、 Reconstructing Macroeconomics: A Perspective from Statistical Physics and Combinatorial Stochastic Processes , Cambridge University Press, 2007 (with Masanao Aoki).


