| 解説者 | 西村 和雄 (ファカルティフェロー) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0073 |
| ダウンロード/関連リンク |
理科離れがいわれて久しい。高校の学習指導要領の変化は理科の科目学習を減らしてきた。このような高校における学習内容の変化が大卒就業者の得意科目にどのような変化をもたらしたのであろうか。そして、その変化は所得の差にどのように表れているのだろうか。
西村和雄FFらは、2011年2月に行ったインターネット調査によって得られた1万人以上の回答を用いて、1955年から段階的に行われた学習指導要領の変化に応じ、世代間で得意科目と所得にどのような関係があるかを調べた。調査結果からわかったことは、より若い世代ほど物理離れが目立ち、所得との関係では物理や数学が得意な人の所得が高くなることだ。西村FFは、労働市場においては物理などの学習により培われる数理的かつ論理的思考力の価値が高まっており、小中高校教育において物理を含めた理数系の学習の充実が求められると指摘する。
――「高校での理科学習が就業に及ぼす影響」を研究された動機は何ですか。
これまでにも大学の文科系学部を卒業した人が大学受験の際に数学を選択した場合と、そうでない場合で、所得にどのような差があるのかを研究して発表してきました。また、英語、数学、国語、社会の各科目の得意・不得意と所得の関係についても調べました。さらに昨年(2011年)には、理系出身者と文系出身者の所得の間にどのような差異があるかについてパネルデータを用いて調べ、分析結果をRIETIのディスカッション・ペーパー「理系出身者と文系出身者の年収比較」(11-J-020)として公表しています。世の中には、「理系出身者よりも文系出身者の方が高所得」という通念があり、それが理系志望者減少の要因の1つではないかと危惧していますが、分析の結果は通説とは必ずしも一致せず、理系出身者の方が文系出身者より年齢の上昇と共に所得上昇の傾斜が大きくなることがわかりました。今回の研究は、こうした一連の研究の延長線上にあります。
日本の国際競争力の源泉となる研究開発の効率性を向上させるためには、研究開発者の質的向上が重要です。そこで、学校教育における理科教育が研究者を含む労働者の労働生産性に与える影響を調べたいと思いました。生産性を示す指標については、色々な考え方がありますが、一連の研究では所得を用いています。なぜなら、生産性にはいろいろな変数が入り込んでいて、それらを区別することは難しいですけれど、所得には働く人たちの需要と供給が反映されているからです。この需要と供給の関係は産業界の経済活動から生まれてくるものです。
――調査に使用されたデータは、どのようなものですか。
2011年2月にインターネット調査の方式で、調査会社の持つモニター母集団から無作為抽出した10万人を対象とするアンケート調査を実施しました。回答者のうち、大卒以上の略歴を持つ1万1399人のデータを使用しています。
質問項目のうち、出身大学と学部名については非常に回答率が高く、これによって理系と文系を判別しています。これが今回の調査では重要でした。人文・社会科学・ビジネス・芸術・家政・食物系は文系学部に、理工・医薬・農学・生物・技術系は理系学部に、情報系については出身大学・学部名から総合的に判断して分類し、その他判断が困難なものは欠損値として扱っています。この分類によると、理系学部出身者は3456人、平均年齢43.7歳で全体の3割を占めています。
その他の質問項目の作成にあたっては、正確な情報を得るために、答える方が苦にならないよう答えやすい表現を心がけました。
――学習指導要領の変遷に沿って、教育を受けた世代を区切って分析されていますが、その理由は何でしょうか。
理科離れが進んでいると良くいわれます。理系学部の入学者自体は一定ですが、高校生の中で理系志望者の割合が減っているのは事実です。その原因については、簡単には決められませんが、少なくとも高校までの教育の変化に何かしらの要因があるのではないかと考え、その傾向を調べることが1つの見方ではないかと思ったわけです。そこで今回の研究では高校における必修科目数の変化のあり方で3世代に分けています。学習指導要領のキーワードでいうと、「教科学習の系統性」と「教育課程の現代化」の世代(世代A)、「ゆとりと充実」の世代(世代B)、「新学力観」の世代(世代C)の3世代です。ただ、一番新しい世代の「生きる力」世代は若すぎて今回は調査できていません。(表1)

英語は得意に、物理と数学は不得意に
――分析の結果、どのようなことがわかりましたか。
まず、理科以外の科目について。文系、理系どちらとも若い世代ほど英語が得意な人が増え、不得意という人が減っています。英語が不得意というのは文系では2割強から1割台後半へ、理系では4割弱から3割弱へと、1割ほど減っています。一方、数学が不得意という人は、文系で3割台前半から4割台へと1割増え、理系でも0.6割から1割台前半へと1割弱増えるなど、若い世代ほど数学が不得意になっています。
次に理科の中で得意、不得意の科目を見てみました。(図1)
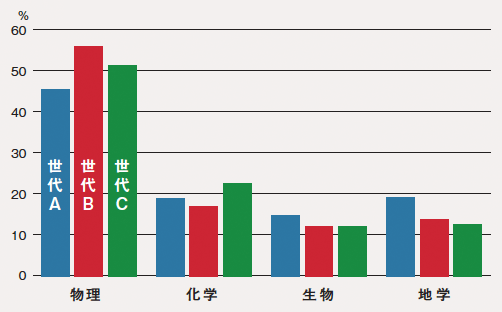
物理が得意という人は2割台後半から1割台後半へと、若い世代ほど得意とする人が1割ずつ減っています。逆に生物が得意とする人は、3割前半から4割後半へと、世代が若くなると1割強増えています。つまり、物理が得意な人が減って生物が得意な人が増えているのです。理科の中での不得意科目は文系も含めた全体で、物理が不得意というのが半分近くに達しています。文系では数学、理系では物理と、より数学的な科目について不得意な人たちが増えています。この背景には、そうした科目の履修者が減っていることがあると考えられます。文系で数Ⅱまで、理系で数Ⅲまでを勉強する人が減り、そして文系、理系とも物理を履修する人がだんだん減っているのではないかと推測されます。理数離れがいわれる中で、文系では数学離れ、理系では物理離れが理数離れの具体的な中身になっているのです。
――得意・不得意科目の他にどのような質問をしていますか。
数学離れや物理離れといった学習の偏りについて、得意・不得意とは別の方向から見るために、自分のこれまでの経験からみて「役立った科目・役立たなかった科目」と「もっと勉強してくべきだった科目」、また「将来世代に勉強して欲しい科目」についても質問しています。
役立った科目では、文系で英語、国語が多くありました。これはある程度当たり前のことです。その次に数学と社会が続きます。文系の場合、役立った科目に数学がかなり多いことには注目すべきです。理系では数学が一番多く、理科、英語が続きました。役立たなかった科目は「なし」が圧倒的に多く、6割前後を占めました。これは、幅広く勉強することの価値を認識しているからだと考えられます。役立たなかった科目では文系で理科が2割あり、他の科目は1割ぐらいでした。
将来世代に勉強して欲しい科目というのは、自分の反省ということになるのでしょうが、文系、理系にかかわらず英語が一番多くなりました。文系では国語、数学が続きました。理系では数学、国語、理科と続きます。英語は日本人が英語に不得意で英語力が低いということと、経済・社会のグローバル化が進んでいることから必要と考えられるのでしょう。理系で理科が数学、国語より上でないのは、基礎的な科目として数学、国語を将来世代には勉強して欲しいということだと考えられます。文系では数学と並んで社会も挙げられています。これも基礎的な科目として勉強して欲しいということだろうと思います。理系の人であっても理系の科目だけを意識していないのは、将来世代に対して、文系、理系にかかわらず基礎的な勉強をして欲しいということでしょう。
物理、数学が得意な人の所得は高い
――得意科目は、就業後の所得に影響を与えていましたか。
まず、今回の調査データを使って、理系と文系それぞれの平均所得を算出したところ、理系が637万円と文系の510万円を127万円上回りました。これは、昨年(2011年)行った「理系出身者と文系出身者の年収比較」(DP:11-J-020)の結果と同様、「理系出身者よりも文系出身者の方が高所得」という通念を覆すものでした。これを得意科目別に見ると、理系、文系合わせて、3世代とも一番所得が高いのは数学で、次が理科、そして社会、英語、国語と続きました。(図2)
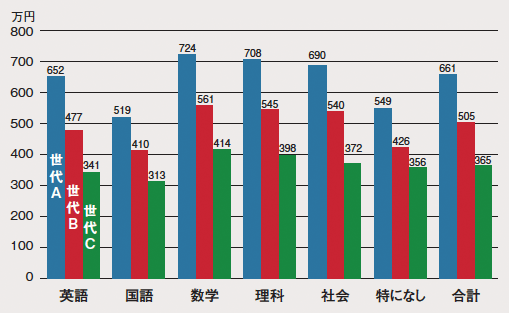
理系に限ると、理科の得意科目別で所得が高いのは物理、化学、地学、生物の順でした。ただし地学はサンプル数が少ないので除外して考えてもいいと思いますので、実質的には3世代とも物理、化学、生物の順になります。得意科目が物理と生物の所得の差は、「ゆとりと充実」以前の世代で100万円、「ゆとりと充実」世代で120万円、「新学力観」で60万円と、かなり大きい差が出ています。(図3)
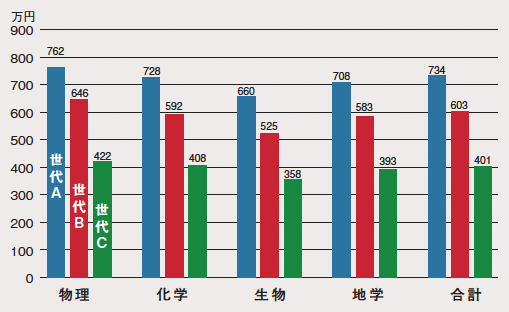
これをまとめて見ると、理科の他の科目に比べた物理と、全体の他の科目に比べた数学が得意な人の所得が高いという結果になりました。これは、数理的、論理的な思考力を身に付けていることが所得の高さに結びついているということを示しています。
もうひとつ重要なことは、物理や数学といった科目が得意である場合は、他の科目が得意なことが求められるような場合にも適応できるということです。つまり、物理や数学は、それらの学習内容や思考力が他のものを学ぶときや、他の仕事をするときにプラスになる可能性が高いのです。これは、言い換えれば、数学的な思考ができる人は仕事の適応性があるということで、それだけ仕事の選択肢が広くなるわけです。これとは逆に、物理や数学的な思考を必要とする職場には、それができない人は適応できません。仕事の選択肢が広いということは、より広い選択肢の中から仕事を選ぶことができるわけで、その結果、平均所得が高くなります。また、こうした思考ができる人は転職が可能であり、所得が上がることにつながります。もちろん、その背景にこうした思考ができる人に対する需要と供給の問題もあります。
――こうした傾向は、大学の入試難易度により違いがありますか。
アンケート回答の大学名から、旧七帝大(北海道大学・東北大学・東京大学・名古屋大学・京都大学・大阪大学・九州大学)と東京工業大学、一橋大学、筑波大学、慶應義塾大学、早稲田大学の12校を入学難易度校として選んだ高難易度大学ダミーを使って、分析を行いました。まず、高難易度大学とそれ以外の大学の理系出身者を比べると、世代を問わず高難易度大学の方が、全体的に所得が高いという結果になりました。
得意科目別にみると、難易度大学に限った場合でも、物理を得意とする人の所得が一番高いという結果になりました。また、高難易度大学とそれ以外の大学の所得格差について、理系、文系で比較した場合には、理系の方が所得の差が小さくなりました。この点については、これまでの分析でも、数学で大学を受験した場合や、物理を学習している場合は、高難易度大学でなくても所得が高くなっています。
――理科の得意科目別の所得に関する重回帰分析ではどのような結果になりましたでしょうか。そこからいえる結論はどのようなことでしょうか。
物理が得意な人の所得が高いことが統計的に分析しても裏付けることができました。物理学習がどの世代にとっても、より高い所得に結びつくといえます。
物理の履修率を上げる努力を
――分析結果から、どのような政策インプリケーションが得られましたか。
今回の研究では、理科における高校のカリキュラムの変化によって世代を区切って検討してきました。その結果、物理が得意な人たちが所得は高いということがわかりました。これは、物理が得意な人たちが貴重であり、求められている割に供給が少ないことを示しています。この結果からは、日本の研究開発者を含む労働者の質を向上させるためには、よりいっそう物理教育に力を入れ、より多くの高校生が物理を学ぶ、つまり履修率を上げることが求められると考えられます。
しかし、そこで問題になるのが、この努力を誰がするのかという点です。現在の制度では、高校生に物理を選択することを強制はできませんので、高校生自身が物理を選択したくなるような仕組みをどうつくるか。もっと物理を学習しやすい、学習したくなる枠組みづくりが必要になります。より社会の需要に合った科目が選択されるようにしなければいけません。
さらに理系に限っていえば、理科4科目のうち、少なくとも物理を除いた地学、化学、生物の3科目を高校で学習できるようにすべきだと思います。現状のように、2科目だけしか選択できないカリキュラムでは、何かが犠牲になってしまいます。また、高校から大学への理科学習の連携が必要である以上、大学入学試験のあり方も検討が必要です。その上で、大学は3科目中で受験しなかった科目について、必要に応じて入学後に補修できるようなカリキュラムを組むようにする必要があるでしょう。ただし、その場合も、物理については高校で学習をしているということが必須の前提になります。
このように理科の履修者が増えていくと、教える側の先生が不足する可能性が出てきます。そのため、先生が不足する前から、不足を補うための社会的な理科教育の仕組みを検討していくことが重要です。小中高の教育の中で、理科教育を充実させていくためには、たとえば引退したエンジニアなど、社会の資源である人材を学校教育に利用することが考えられるでしょう。
外国人技術者の採用などで新たな課題も
――今後の研究課題をお聞かせ下さい。
理系出身者の理科の得意科目について、平均所得だけでなく、その後の進路に得意科目が生かされているか、現状の就業形態について、もう少し掘り下げて調査してみたいと考えています。
これからは外国人技術者が多く採用されるようになるでしょうし、正規社員と非正規社員の関係もこれまでの世代とは違ってくると考えられます。このように、いろいろと新しい社会状況が出てくる中で、単純にこれまでの分析のように世代ごとに平均所得を見るのではすまなくなってきます。
これまでの一連の研究の目的は、日本の国際競争力回復にむけた問題解決の糸口を、何とかして見つけることにあります。今回は得意・不得意科目ごとに平均所得を見たことで、何が若い世代で不足しているかを調べることが解決策につながると考えました。今後、新たな問題に対しては新たな切り口が必要になるかも知れません。
解説者紹介
1970年東京大学農学部卒業、1976年ロチェスター大学大学院経済学研究科博士課程修了(Ph.D)、1987年京都大学経済研究所教授、2000年パリ大学・マルセーユ大学客員教授、2009年サンタフェ研究所特任教授などを経て、2010年京都大学名誉教授・京都大学経済研究所特任教授。主な著書は、『マクロ経済動学』(共著)(岩波書店)、"Equilibrium, Trade, and Growth; selected Papers of Lionel W. McKenzie"(Tapan Mitraと共編)(MIT Press)、『複雑系を超えて』(共著)(筑摩書房)など。


