| 解説者 | 岩本 康志 (ファカルティフェロー) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0061 |
| ダウンロード/関連リンク |
少子高齢化に直面するわが国では医療や介護などの社会保障費用がますます増大し、これをまかなうためには税負担増が避けられないことは多くの国民が実感している。だが、実際にどれだけの財源が必要となるかという点については、2008年10月に社会保障国民会議が発表した「社会保障の機能強化のための追加所用額」による2025年までの試算を超えるような長期的な分析は、これまで十分ではなかった。岩本FFらは、長期的視点にたった税制のあり方を検討する際には長期的な社会保障費用の推計が必要だ、との考えのもと、社会保障国民会議の試算を元に、自己負担比率の変化や財源の計算などを細かく見直し、より長期的な視野から社会保障の公費負担の動向について分析を行った。
医療・介護に対する公費負担の総額は2070年代まで上昇を続けるとの分析結果を踏まえ、岩本FFは、財源調達の手段についても費用増加の視点からの検討が必要であり、将来世代の生涯負担率を考えると積立方式への移行が望ましいのではないかと指摘する。
――まず、「医療・介護保険の費用負担」というテーマを選んだ背景と問題意識を教えてください。
今回の研究は、中長期的な視点から社会経済構造の変化に対応した税制のあり方を検討するRIETIの「社会経済構造の変化と税制改革」プロジェクトの一環として行いました。このプロジェクトでは、税制改革全般を分析するのですが、中長期的に持続可能な税体系を構築するためには、将来にわたって増大する社会保障費をどうまかなっていくのかということが非常に重要な課題となります。
2008年10月に社会保障国民会議が発表した「社会保障の機能強化のための追加所要額(試算)」では、年金・医療・介護・少子化の4分野において将来に必要となる追加負担が推計されました。追加負担は、2025年度には消費税率換算で6%程度になり、このうち医療と介護で同4%程度の財源が必要になる、との結果が報告されています。しかし、2025年というのはわずか15年先の将来で、当然ながら日本の高齢化はそれ以降も進展していきます。また、政策が効果を生み出すにはタイムラグがあることを考えると、より長期の推計が必要です。たとえば欧州連合では、社会保障、教育など人口に依存する財政支出について2060年までの予測を行い、財政の持続可能性を検証しています。
日本政府も、これまでに中期的な経済財政展望を作成していますし、先述した社会保障4分野のうちで公的年金は、比較的研究が進んでおり素晴らしい研究が数多くあります。しかし、将来の財政事情について社会保障費の増加を含めるかたちで長期にわたって整合的に見通せるような分析は今までありませんでした。数字に基づかないで税制改革を論じることはできませんので、国民会議のシミュレーションを補い、より長期的かつ精密な分析によって医療・介護における公費負担の伸びを推計しようと考えました。
――医療・介護の費用負担に関する先行研究にはどのようなものがあるのでしょうか。
医療や介護は現物のサービスを必要に応じて給付するため、まず需要変化から分析する必要があります。場合によっては年金以上に需要が増えることもあり、医療技術の進歩による費用増などの予測も難しいという問題もあります。そのため、年金の分析に比べると数は少なくなりますが、研究は確実に進んでいます。「人口高齢化と社会保障」(2005岩本)では過去の医療費を元に、医療費の将来推計を試みています。また、「医療・介護保険財政モデル」(福井、岩本、2007年)の最新版(09年9月)が、今回の分析に活用されています。
――「国民会議」が示したシミュレーションの結果と、それに対する評価はいかがでしょうか。
国民会議のシミュレーションではいくつかのシナリオが考慮されていますが、そのうち2008年10月31日の経済財政諮問会議に吉川洋座長が提出した資料「社会保障の機能強化のための追加所要額(試算)」でとりあげられているものを「基準ケース」として考えることにします。
試算結果は、「基準ケース」(名目経済成長率=2.0%、物価上昇率1.0%、名目賃金上昇率=2.5%、医療・介護の中身の充実具合を示す改革シナリオは中程度として、費用の対GDP比=12.0%、とそれぞれ設定)の場合、2007年から25年にかけて医療の公費負担がGDP比で2.3%増加し、介護では0.6%減少するというものでした。これらを賄うためには、先述のように消費税率換算で約4%分の新たな財源が必要となります。介護はGDP比で減少することになっていますが、これは、ベースラインの推計方法によるところが大きいのではないかと考えています。推計の基となる費用は、大きく分けると人件費と物件費になりますが、そのうち、器具や施設などの物件費の部分については、所得が伸びたとしても現在と変わらないものを使う、つまり提供されるサービスのレベルは一定だという前提になっています。一方、医療費については、賃金および物価の上昇の他に、過去の医療費の伸びから「自然増」分を見込んでいるため、一人当たり所得に比べ高い伸び率となっています。
80年代までは医療費の伸びは安定していて所得の伸びとほぼ同じぐらいでしたが、90年代に入り医療費が所得を上回る勢いで伸びるという問題が起こり始めました。そのため、2000年代以降、社会保障給付費を抑制する方向での改革が続けて行われました。具体的には、2004年の年金改革で保険料の抑制政策が打ち出されましたし、また05年には介護保険改革が、翌06年には医療制度改革もスタートし、長期には予防重点主義を導入、短期には診療報酬の引き下げや自己負担の引き上げといった方法で社会保障費抑制を目指す一連の政策が実施されました。こうした抑制的な改革に対し、医療・介護の現場ではサービス実施体制のゆがみを心配する意見や、医療費などの削減は限界ではないかといった声が出てきました。国民会議はこうした点を踏まえ「社会保障の充実」に舵を切ったと言えます。
長期的視点に立った分析で税制の構築を
――今回の分析にはどのような特徴がありますか。
先に述べた通り、国民会議が示した2025年までの予測は、わずか15年先の未来です。長期的視点にたった税制のあり方を検討する際には、長期的な社会保障費用の推計が必要であるため、今回は、より長期的な視野で公費負担の動向を分析しています。
このとき、費用の伸び率と所得の伸び率が最初に少しずれると、長期の推計の最後のほうでは大きな乖離が起こってしまいます。われわれは2105年までの長期の推計を行っていますので、2025年または2050年から先はこうした伸び率の乖離が起こらないように注意を払いました。
また、国民会議では財源の計算がやや精密ではありませんでした。たとえば、高齢者の医療保険の自己負担率は現役世代より低いので、これから高齢者の割合が増えると患者自己負担の割合が増えると予想されますが、この点はうまく考慮に入れられていません。また、高齢者になると自己負担率が下がるため、年齢別の自己負担額を計算・集計しています。さらに、保険料と公費の割合についても、保険の加入者の構成変化を考慮するようにしています。
――推計の基となった条件設定や手法について、詳しく教えてください。
国民会議では経済前提や医療費単価の伸び、医療・介護のサービスの質がどれほど向上するかで場合分けされています。経済前提は、Ⅰ(経済財政諮問会議の有識者議員提出資料「給付と負担の選択肢について(2007)」)とⅡ(厚生労働省「人口の変化等を踏まえた年金財政への影響(暫定試算、2007)」)の2通りの条件を採用しました。その上で、1)高成長をとるか2)低成長をとるか、そしてそれぞれ①医療費単価の伸びが低いケース、②高いケースに分けました。さらに、メニューの充実度などによって計る医療サービスの質を現状維持とするAから、改革の度合いに応じてB1、B2、B3の4段階として、2×2×2×4=計32通りのシナリオを設定しました。国民会議が基準ケースと考えているだろうと思われるものは、このうち、経済前提がⅡ-1、医療単価の伸びは①、そしてサービスの質をB2、としたもので、今回の分析でも同様の前提を「基準ケース」と定義しています。具体的な設定値は前に述べた通りです。
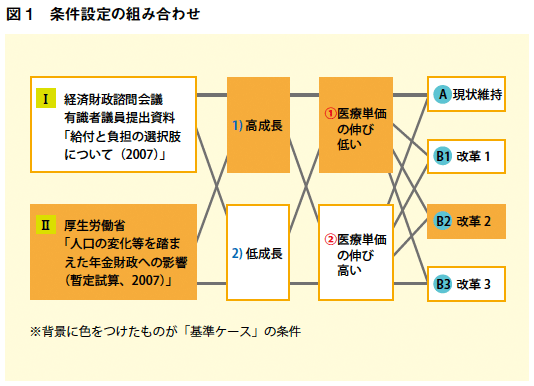
今回の研究ではこの32通りの中から上から下まで幅を持たせ、代表的なケースを選択するため、①「基準ケース」のほか、シナリオのB2をAに変えた②「シナリオA(現状投影ケース)」と、そのシナリオAの下で2025年以降も賃金に占める医療費の比率が上がり続ける③「シナリオA(現状投影、伸び持続)」、そして基準ケースに比べて名目の経済成長率や賃金上昇率を低く見積もった④「Ⅱ-2」という経済前提を新たに設定しました。推計を行う上では、やはり最も悲観的な条件設定でどうなるかというところに目を向けねばならないと考えたからです。
ここでは基本的に、年齢別・一人当たりの医療・介護費用がどれだけ伸びるのかというポイントについて、人口データや所得データに基づいて推計しています。費用の伸び率や総額は出来るだけ国民会議の推計に合わせるようにしました。なお、国民会議の推計がサービスを細かく見ていたのに対し、われわれは世代間の違いに注目するため年齢別の推移に注目しました。
2025-2050年も医療・介護でGDP比2.3%の公費負担増に
――推計結果はどうなったのでしょうか。
推計によって、基準ケースの場合で2025年から2050年にかけて医療でGDP比1.25%、介護では同1.05%公費負担が増加し、2050年以降も増え続けるという結果が出ました。これらの合計はGDP比2.3%で、消費税率に換算すると4%を超えます。この点で、2025年までに消費税率にして4%程度の負担増、とした国民会議の推計値にほぼ匹敵する負担増がその後に来ることが分かりました。ただ、2060年代以降は人口増加が一段落するため、公費負担の伸び率も鈍化します。
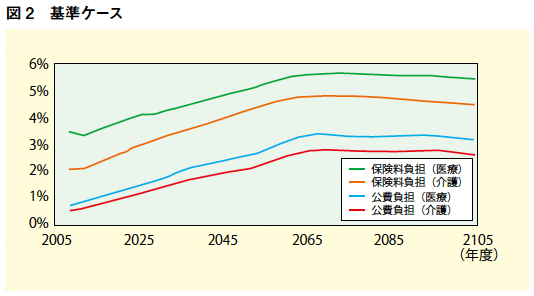
4つの異なる設定条件による結果の幅については、医療保険の公費負担の対GDP比が2025年で2.97%から3.14%(基準ケースでは3.01%)、2050年では4.20%から4.44%(同4.26%)となりました。介護の場合は2025年が1.23%から1.57%(同1.54%)、2050年では1.81%から2.64%(同2.59%)と、医療に比べて、上下の幅がやや大きくなるという結果が出ています。
これらの結果から重要な示唆が得られます。日本はOECD諸国に比べると平均余命が長い割には医療費の水準は低い。つまり、医療の質や効率、パフォーマンスは悪くありません。ただ、高齢化が進む中、今と同じように現役世代の負担だけで高齢者の医療を支えようとすると、保険料と公費負担のための税を引き上げざるを得なくなることが考えられます。したがって、現状でも高い負担だと思っている人にとっては、将来はもっと厳しいものになるだろうと予測されます。
積立方式導入で負担は平準化
――今後の社会保障における政策提言は
社会保障の問題における政策立案では、高齢化の進展や財政支出の拡大など、将来にどういう課題があるのかを正しく把握し、数字に基づいて理解したうえで的確な手段を講じる必要があります。現行制度では保険料の伸びよりも公費負担の伸びが大きいため、税による財源調達に困難が生じることが予想されます。制度改革によって、医療・介護に必要な費用は保険料によってまかなう分を増やし、公費負担に依存する要素を減らして行かねばなりません。
負担率を減らす方法は、所得を増やすか費用を減らすかの方法がまずあります。所得を増やすには人口を増加させる少子化対策が不可欠となりますが、出生率が上がったからといってすぐに労働力人口は増えません。一方で、費用を削減するために医療や介護の質を落とすことは、生活の質の低下に直結するため、こちらの方を採ることも国民にとって非常に難しい選択となります。また、医療・介護の水準を「現状のままでよい」と満足してしまうことは進歩をあきらめることにもなります。高齢者も消費の担い手なので、「寿命」というのは経済成長によって価値が高まるものです。寿命を伸ばす方向に費用を使うことは十分合理的だと考えられます。医療技術の進歩でコストがかかるようになったという意見もありますが、これは一面的な見方です。技術がなくて使えなかった、つまり無限大(利用できない)だった医療費が有限(価格が高いが利用できる)になるのが技術進歩です。こうしたことを考えると、2050年までは人口減・負担増という状況が避けられません。
現在の制度のまま均衡財政方式(賦課方式)で公的な医療・介護保険制度を運営していくと、将来は保険料率と税負担率がともに高まっていくため、将来の世代ほど生涯の負担率が大きくなっていってしまいます。そのためにも均衡財政方式から積み立て方式へと移行し、将来の負担が重くなることを回避するとともに負担の格差を平準化する必要があります。
積み立て方式に移行する場合、特定の世代が「その時の受給者分」と「将来自分が給付を受ける分」の二重負担を負わされるとの指摘があり、これが移行の障害となっていると一般的に言われています。しかし、基準ケース(改革シナリオB2)を基に、「均衡財政」「積み立て」両方式における世代ごとの生涯負担率を推計してみると(図3)、積立方式への移行によって二重の負担を負うとされる世代(2030年代頃の生まれ)の生涯負担率は、均衡財政方式の下での負担率よりも低くなることが示されました。これによって、有権者世代はすべて負担増となりますが、現状のまま放置するよりも世代間の負担の格差は縮小することになります。この方式なら、現在の有権者のなかでの利害対立は起こらないといえます。また、シナリオA(現状投影)を前提とした推計でも同様に、積立方式に移行しても「二重の負担」を被る世代の生涯負担率はやはり均衡財政方式の場合よりも低くなりました。この点からも、積立方式への移行は負担の平準化に寄与すると言えるでしょう。
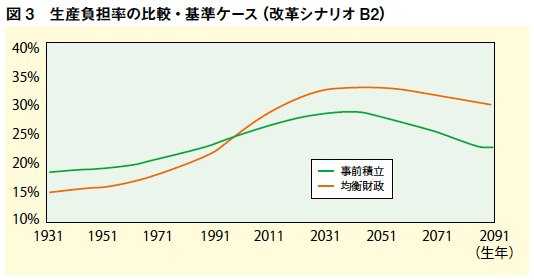
――今後の研究計画についてお聞かせ下さい。
今回行った医療・介護における公的負担の推計では、前提条件を変えて4通りのケースを想定しましたが、今後はこうした条件設定の仕方などについて改善を図りたいと思っています。特に今回の論文でも提案している「積立方式」を導入した場合のシミュレーションについては、年金の推計で使用したような方法を応用し、費用や経済成長率を確率変数にして将来の負担率を分布の形で示せないかと考えています。たとえば、経済成長をどう反映させるのかといった問題意識で成長を織り込んだ計算も必要でしょう。海外の事例でも、完全な積立方式をとっているところはありませんが、シンガポールでは「医療貯蓄口座」という個人単位の積立制度がありますし、米国のメディケア(高齢者医療制度)も一部に積立金があります。日本に積立金の制度を導入する場合、実際にどういった組織が運営にあたるのか、また、現在の制度からどのように移行していくべきかといった問題についても検討が必要だと考えています。
解説者紹介
1984年3月京都大学経済学部卒業。1991年2月大阪大学経済学博士。1987年4月大阪大学社会経済研究所助手、1990年2月大阪大学経済学部講師、1991年7月京都大学経済研究所助教授、2002年4月一橋大学大学院経済学研究科教授等を経て2005年4月より現職。主な著作は、『経済政策とマクロ経済学』日本経済新聞社(大竹文雄,齊藤誠,二神孝一氏と共著)、『社会福祉と家族の経済学』東洋経済新報社(編著)など。


