| 解説者 | 若杉 隆平 (研究主幹・ファカルティフェロー) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0031 |
| ダウンロード/関連リンク |
輸出やFDIを行い国際的に活動を展開する日本企業に関する研究は数多いが、国際化した日本企業の実像を包括的に示す実証研究は乏しかった。若杉RIETIファカルティフェローらの研究チームは、海外展開している企業の個票データを活用して、国際化した日本企業の全体像を探るための多角的な分析を行うとともに、企業レベルの研究で先行する欧州企業に関する分析との比較も試みた。
企業の国際化と生産性などの分析を通して、国際化した企業のパフォーマンスが国際化していない国内型企業よりも高いなど、欧州企業との共通点が確認された一方で、国際化企業と国内型企業のパフォーマンスの差が、日本の場合は欧州よりも小さいといった日欧の差も浮き彫りになった。
――どのような問題意識から、この論文を執筆されたのでしょうか。
従来の国際貿易分野の研究では、国際的な活動をする企業は同じ形をしていると考えて、代表的な企業を想定して議論されてきました。しかし、企業は多様で異質な存在です。輸出や海外投資などの国際的な事業活動をするにはコストがかかるので、そうしたコストを賄ったうえで利益を出せる企業が、輸出や海外直接投資(FDI)をしていると考えられます。理論面の研究では、こうした高い生産性を持った企業だけが、輸出・FDIなどの活動ができるということをモデル化し、分析を深めつつあります。
また実証面では、米国で、生産性や資本、技能集約度、雇用規模などの企業特性と輸出との関係を論じた研究が積み上げられたほか、欧州でも、欧州連合(EU)全体を対象に研究が取り組まれ、国際貿易やFDIは生産性の高い少数の企業により担われていることが明らかになってきています。それに対し、日本の企業については、欧米のように輸出やFDIを行う企業の包括的な姿をとらえるような研究が少ないのが実情です。
そんな時、RIETIと研究交流のある英国シンクタンクのCEPR(CentreforEconomicPolicyResearch)から、日本でも欧州と同様の研究をしてみないかという誘いがあり、国際化する日本企業の実像を探る研究を始めることにしました。
こうした研究には、個別企業の詳しいデータ、つまり、個票データが欠かせませんが、日本では「企業活動基本調査」と「海外事業活動基本調査」のデータから企業のミクロレベルの情報を得ることができますので、これらのデータを用いて分析を行いました。
もっとも、データの整備という点では欧米はもっと進んでいることが研究交流で明らかになってきました。特に欧州では、フランスのように、企業別にどの国にどの品目を輸出したかという仕向け地別・品目別のデータまで整えている国もあります。
この研究は欧州企業との比較という観点で、日本企業の特性を探ったものですが、欧州ではそうした分析が可能なデータが日本以上にそろっているという印象を受けます。欧州がこうしたデータ整備に力を入れている背景には、輸出やFDIなどの国際化企業の活動を支援するための政策が必要であるという合意がEU域内にあり、そのために不可欠な統計データの収集環境が、EU統合以降に整備されたのではないかと思われます。
上位10%の企業が輸出全体の9割をカバー
――生産性が高い少数の国際化した日本企業は、貿易・投資全体のどの程度の割合を占めているのでしょうか。
図1をみると、製造業における輸出企業全体のうち、上位10%の企業が輸出額全体に占める割合は、2003年時点で92%を占めています。上位5%でも全体の85%を占めており、上位1%というごく僅かな企業群で62%を占めるほど、上位企業の占める比率は高いのが特徴です。雇用者数でも上位集中の傾向がうかがえますが、輸出額では、輸出全体に占める上位企業への集中度がさらに高いことがわかります。
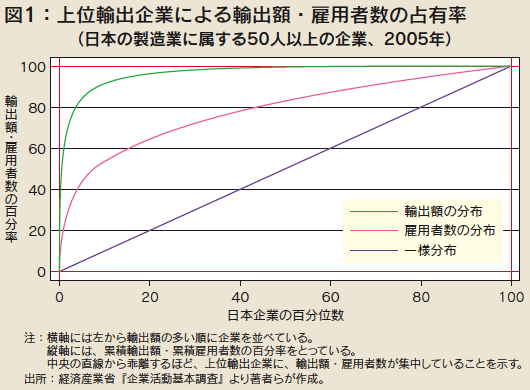
こうしたトレンドは1997-2005年の間、ほとんど変わっていませんので、上位企業への集中という傾向は一時的な現象ではなく、長期間にわたって少数の企業が輸出のかなりの部分を担ってきたということができます。ただし、上位1%の企業が占める割合に関してだけ見ると、近年やや減少傾向にあり、輸出への参入が進んできていることも注目されます。
一方欧州でも、少数企業が輸出を担ってきたという傾向は同様であり、こうした生産性の高い少数の大企業を「thehappyfew」(幸福なる少数者)と呼んだEUの研究文献があります。ちなみにこの呼び方は、シェークスピアの『ヘンリー5世』からの引用で、自軍を「幸福な少数者」と称えて力づけた演説にちなんだものです。
――国際化した企業の特性を議論する前に、まず国際化企業の定義を教えてください。
私たちは、FDIないしは輸出をしている企業を「国際化企業」と定義しています。いずれもしていない企業が非国際化企業、すなわち国内型企業ということになります。
なお、時系列で議論する時は、ある時点で輸出やFDIをやめた企業については、国際化企業から除外しています。
国際化企業のパフォーマンス、非国際化企業を大きく上回る
――では、国際化した企業はどのような特性を持つのでしょうか。
国際化した企業と、国内型の企業のパフォーマンスについて調べてみました。ここでは、雇用者数、付加価値、賃金、資本集約度、技能集約度の5項目に関して、まず、輸出企業の平均値が輸出していない企業の平均値をどの程度上回っているかを計算しました(表1)。輸出企業の平均値と、輸出していない企業の平均値の比(これを「プレミア」と定義します)が、1を上回っているかどうかを確認しました。同様に、FDI企業の平均値が、非FDI企業の平均値をどの程度上回っているかもみました。
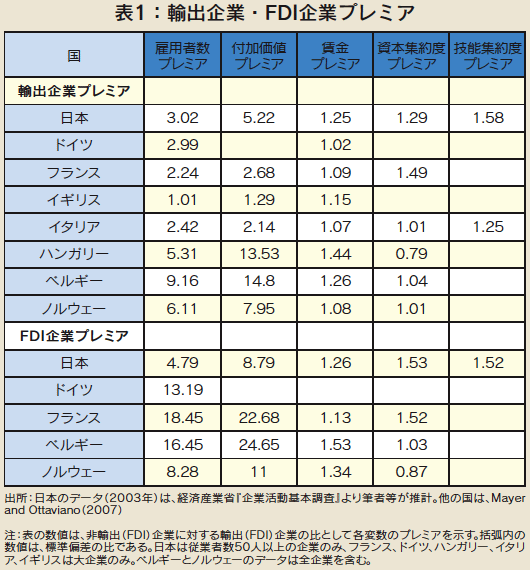
表1より明らかなように、ごく少数の場合を除いて雇用者数、付加価値、賃金、資本集約度、技能集約度の5項目のすべてについて、すべての国でプレミアは1を上回っています。つまり、輸出・FDI企業は、輸出やFDIを行っていない企業と比較して、多くの人を雇用し、より高い付加価値を生み出し、より高い賃金を支払い、より資本集約的であり、より技能集約的でもあるということになります。
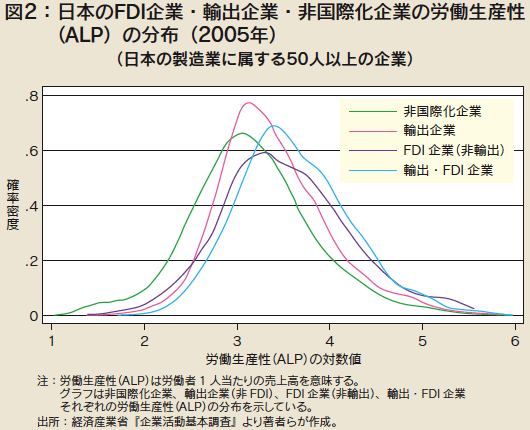
次に、生産性という観点から見ても、図2が示すように国内型企業の生産性が最も低く、続いて、輸出あるいはFDIを行っている企業、輸出とFDIの両方を行っている企業の順に高くなっていきます。図の分布の中心が右にあるほど生産性が高いことを意味しています。ここでは生産性の指標として労働生産性を使っていますが、全要素生産性(TFP)という別の生産性の指標でみても同様の結果が得られます。
こうした結果は、国内での事業活動に比べて輸出やFDIはコストがかかり、そのコストをカバーして利益を出すには企業の生産性が高くなければならない、という理論面での研究成果と合致します。
――日本の企業の特徴は、欧州企業と比べて違いがありますか。
欧州企業についても日本企業と同じような研究結果を得ていますが、表1をみると、輸出・FDI企業と、国内型企業のパフォーマンスの差は、日本よりもさらにはっきりしています。例えば、FDI企業で見た場合、雇用者数に関する日本のプレミアが4.79なのに対し、ドイツは13.19、フランスは18.45と10を大きく上回ります。これだけ日欧で大きな差があるとすると、生産性の違いが、国際化企業と国内型企業のパフォーマンスの違いを説明する重要な要素だとしても、それ以外の要因が働いていると考えることもできるかもしれません。
例えば、欧州企業の輸出・投資先は、本社がある自国と比較的同質な欧州圏の国に集中するのに対し、日本企業の場合は、例えば最大の貿易相手国である中国が資本や技術の面で格差が大きいなど、輸出・投資先の比重が高いアジアが必ずしも自国とは同質とはいえない点を考慮すべきかもしれません。こうした観点を考慮した理論、実証分析が求められることを示唆しています。
国際化の進展が後押しする生産性の上昇
――国際化企業の高いパフォーマンスの原因は何でしょうか。
国際化企業は投資などのコストをカバーできるだけの高い生産性を持っているのですが、その理由としては2つの説明が考えられます。
1つは、数多くある企業のなかで、生産性の高さという条件を達成した企業だけが生き残ることができるという考え方です。自然淘汰(self-selection)仮説と呼ばれるもので、生産性の高さは、研究開発や技術革新など既存の研究成果を活用して測定します。
もう1つは、国際化することで、外国市場に関する知識を得たり、外国の技術を吸収したりすることが企業の生産性の向上につながるという関係による説明も考えられます。これは経験による学習(learningbydoing)仮説と呼ばれます。
――これらの仮説について、分析ではどのような結果が得られましたか。
企業の国際化と生産性の因果関係については、これまでにもさまざまな実証研究が行われてきていますが、自然淘汰仮説は広く確認されている一方で、学習効果に対する評価は明確ではありません。本論文では、次のようにしてこれらの仮説に簡単な検討を加えてみました。
2000年時点で国際化をしていない企業群を対象として、2001年に国際化(輸出ないしはFDI)を始めた企業群と、依然として国内型の企業群の生産性が、どのように変化するかを、2000年から2005年の労働生産性の推移で調べてみました。その結果、国際化にスイッチした企業は、国際化へスイッチしない企業に比べて、労働生産性がより大きく向上していく傾向があることが分かりました。2つの企業群における労働生産性の差は国際化したことのみによるとは断定できないにしても、生産性の差が生じたことには国際化が影響した可能性はありえるのではないでしょうか。
これ以上の議論をするには、より厳密な研究・議論が必要になりますが、もし国際化の進展が生産性の上昇につながるとすれば、政策的には強力なメッセージとなります。生産性が向上するためには限られた資源が有効に使われる必要がありますますので、国際化は企業の効率性を高めるという観点から経済全体にとって望ましいということになるからです。
貿易・投資のコストが左右する進出企業の数
――企業の国際化と、投資先との距離の関連についても分析しておられますね。
元々は相手国との貿易額の変化を、進出した企業数と、一企業のあたりの貿易額に分解して、その要因分析をしたかったのです。欧州では、企業レベルで相手国別、品目別の輸出額のデータが入手可能なため、貿易額での分析が可能です。しかし、日本では企業レベルでは相手国別の輸出額のデータが入手できないため、FDIによる海外現地法人の売上高に着目しました。
日本企業が海外に持つ販売子会社の現地での売上高(=販売額)の増加理由を、1社当たりの売上高が増えたのか、あるいは販売する会社(=進出企業)数が増えたのかというように分けて、分かれたものそれぞれに、「進出先の経済規模」や「日本から進出先までの距離」という要素が、どのように影響を与えるかを、グラビティモデルを使って分析しました。
その結果(表2)、「進出先の経済規模」は、企業数、販売数に同程度に影響を与えていますが、「日本から進出先までの距離」は、進出企業数に大きな影響を与えることがわかりました。つまり、投資相手国までの距離の遠近が、当該国へ進出する企業数を変化させることにより、総売上高に影響を与えているわけです。
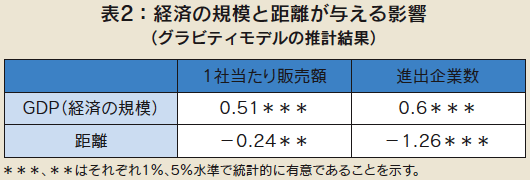
――産業別には何か特徴がありますか。
産業別の傾向をみると、日本からの距離が現地の販売額に大きな(マイナスの)影響を与えるのは、電機機械産業です。部品メーカーを含めた電機機械産業は、近隣諸国で生産して国際市場に販売する傾向が強いと考えられます。これに対し、同じ基幹産業でも、自動車産業は米国などの生産国における国内市場向けに売られる傾向が強いため、距離の影響が比較的小さいと考えられます。
――この分析結果からどのような政策インプリケーションが得られるでしょうか。
日本からの距離が圧倒的に企業数に影響を与えているのは、日本の多くの企業が東アジアに直接投資して現地販売・輸出などの企業活動を行っていることが理由になっていると思います。距離とは、すなわち国同士の貿易コストを示しており、今回の分析でも、国と国の間の取引にコストがかかると、企業数が急激に減ることが分かります。
今回の分析結果から、より多くの企業が国際化という流れに参加できるようになるには、自由な取引ができ、貿易コストが低い環境を作る施策が効果を持つという政策インプリケーションを導くことができると思います。
――今後の研究の課題は何でしょうか。
前にも述べましたが、生産性だけが唯一の国際化を決める要因ではないかもしれません。例えば、産地のような企業集積地を考えると、情報の蓄積、人材の教育などの外部経済性、つまり企業外の要素が国際化に寄与する可能性があると考えることができます。外部経済性としては他にも、ファイナンスの制約要因を除去するための政策などが、国際化に影響する要因として考えられるわけで、これらを考慮した研究を進めることも重要であると思います。
また、従来のFDIについての議論は、投資先の同質性を前提にした水平的な投資という欧米式の発想になりがちであるため、異なる水準にあるアジア諸国への投資が多い日本企業にそのまま当てはめることができないかもしれません。日本企業の実情にも合うように、もう少しモデルを工夫する必要があるとも考えられます。
さらに、国内型企業と国際化企業を分ける境界値(カットオフポイント)を理論的に算出してみますと、欧州企業と日本企業では、その境界値が異なることが分かります。その理由を掘り下げてみることも課題です。
解説者紹介
東京大学経済学博士。1989年信州大学経済学部教授、1990年通商産業省環境政策課長(初代)、1992-2004年横浜国立大学経済学部教授、98-2000年同大学経済学部長、2000-03年同大学副学長、2004-07年慶應義塾大学経済学部教授、2006年からRIETI研究主幹・ファカルティフェロー。2007年から京都大学経済研究所教授・慶應義塾大学客員教授。第2回小島清賞受賞。主な著作は『現代の国際貿易』(岩波書店)(国際ビジネス研究学会・学会賞受賞)、『国際経済学(第2版)』(岩波書店)、『技術革新と研究開発の経済分析』(東洋経済新報社)等。


