| 解説者 | 鶴 光太郎 (上席研究員) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0016 |
| ダウンロード/関連リンク |
企業の合併・買収が増加し日本でも敵対的買収への関心が高まる中、買収防衛策を導入している日本企業は既に300社を越えている。鶴RIETI上席研究員は、RIETIディスカッション・ペーパー『買収防衛策導入の動機―経営保身仮説の検証―』において、買収防衛策の導入に経営保身目的の要素があるかを、防衛策を導入している企業の特徴を分析することで検証した。鶴氏は、買収防衛策への制度的対応として、少数株主保護の観点からは、米国型のポイズンピル型防衛策ではなく、欧州型の公開買い付けルール(特に全部買い付け義務)の強化の視点が重要であると指摘する。
どのような企業が買収防衛策を導入しているのか?
――まず、この分析をされた狙いをお話ください。
M&A(企業の合併・買収)を取り巻く環境は大きく変わりつつあります。日本では敵対的買収というのは稀ですが、米国では80年代に多く、その弊害や逆に米国経済の構造改革に結びついた効果などが指摘されています。欧州も80年代までは敵対的買収はほとんどなかったのですが、90年代末以降状況は大きく変わりました。日本でも数は多くありませんが、敵対的な買収がいつ起こっても不思議ではない状況になってきました。
日本で敵対的買収が起こるのは自然な流れです。90年代から株式の持ち合いや安定株主の持ち株比率が減り、外国人投資家の株式保有比率が高まっている中、株式が相当流動化してきているからです。
そのときに、経営者は一体どうすべきか。本来的には企業価値を最大化する経営をするのが防衛策としての正攻法だと考えています。しかし一方で、産業界での不安感も高まり、また買収防衛策導入のためのルールがなかったため、経済産業省・法務省が2005年5月に指針を公表したわけです。その後、いわゆるポイズンピル型の買収防衛策を導入する企業は、加速度的に増加しました。
では、この防衛策をどのように評価したらよいか、というのがこの論文の背景にある問題意識です。企業価値を破壊するとんでもない買収に対する正当防衛的な性格なのか、あるいは企業の経営者が企業価値最大化から逃げ回るための経営保身的なものなのか、見極める必要があると感じたわけです。
これに対する直接的な答えにはならないかも知れませんが、買収防衛策を導入した企業の特性を分析し、防衛策を導入した企業と導入しなかった企業を比較して、違いを見極めようというのがこの論文の狙いです。
――具体的にはどのような分析をすすめられましたか。
第1の要因は、利益率や株価が低い企業、いわば経営パフォーマンスの悪い企業が、買収されるのを恐れて導入したのかどうか。本来、経営パフォーマンスが悪いことで敵対的買収の可能性が高まっているとすれば、最大の防衛策は、経営の効率化、収益最大化であり、その努力を行うことなく安易に防衛策を導入しているならば、それは保身目的といえます。第2に、もともと買収されるのが嫌だ、株主からの圧力を受けたくないという、経営保身的な傾向の強い企業が導入したのか。防衛策導入企業において、社齢、経営者のテニュア期間、取締役会の構成との関係といった要素から経営保身を生みやすい企業の特徴が見られるかを検証しました。第3に、企業がコントロールできない外的な環境変化によって、買収される可能性が高くなっていることによるのかどうか。具体的には、企業規模、外部株式保有構造、負債比率といった要因から、買収のターゲットになりやすい企業が防衛策をより導入する傾向があるのかを見ることで、保身目的の影響を検証しました。
第3の要因でしたら、ある意味では経営努力を越えているということになるので、そうした要因をコントロールした上で、経営パフォーマンスの悪さなのか、経営保身かを見極めようとしています。それぞれの要因について、以上のような指標を選び、計量的な手法を用いて調べました。対象は2005年度と2006年度に買収防衛策を導入した企業とそれ以外のほとんどの上場企業です。
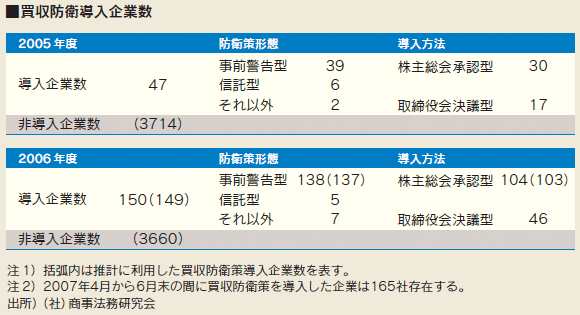
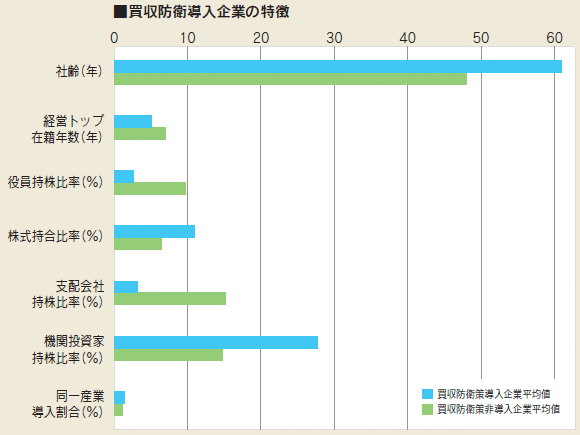
経営保身要因による買収防衛策の導入への影響
――結果はいかがでしたか。
まず、企業の収益や効率を表すROA(総資産利益率)やトービンのqなどで測った経営パフォーマンスの悪い企業が導入しているのではありませんでした。つまり、経営怠慢による買収脅威の高まりに対して、「隠れ蓑」として買収防衛策を導入しているのではないといえます。
第2の経営保身要因では、役員持ち株比率の低い企業が導入しているという結果が出ました。経営陣の持ち株が多ければ、株価が上がることが経営者自身のメリットにもなりますので、株主との利害対立が起こりにくいのですが、ここでは株主との利害対立が起こりやすい企業が導入している事がわかりました。
また、企業は外部からの圧力を防ぐために、株式持ち合いを進め、経営者の周りに「塹壕」を築くとよく批判されますが、そうした持ち合い比率の高い企業ほど、防衛策を導入しているという結果となりました。これは、経営保身要因を示す顕著な要因であるといえます。なぜなら、持合株主比率の高い企業は、他の条件が同じであれば買収されにくいはずであり、それにも関わらず導入の可能性がより高くなっているということは、高い持合比率がその企業の経営者の保身的傾向の強さを反映していると見られるからです。
このほか、社齢の長い企業ほど導入している傾向もでており、こうした企業は保守的になりがちな企業としてとらえることができると思います。
最後の経営者がコントロールできない外的要因ですが、親会社や特定の支配株主の比率が低く、機関投資家の持ち株比率が高い企業が導入しています。こうした企業は株式の流動性が高く、その意味で買収されやすい企業であるといえます。また、流動性資産比率が高く、負債比率が低い、買収者にとって魅力的な企業ほど買収防衛策を導入することが強いことが分かりました。
まとめてみると、買収防衛策は、経営怠慢によるパフォーマンスの悪い企業が、経営の非効率を全面的に放置したまま買収脅威への自己防衛として導入しているとは結論づけられないでしょう。一方で、防衛策を導入している企業には、役員持ち株比率が低い、株式持ち合い比率が高い、社齢が長い、といった傾向が比較的強くみられることから、企業や経営者の持つ経営保身要因が防衛策導入に影響を与えている事を示唆している、といえると思います。
全部買い付け義務による敵対的買収防衛策
――米国の結果と比較してどうでしょうか。
他の企業との株式を持ち合い比率が高い企業を買収することは難しいので、そうした企業は普通に考えれば買収防衛策を導入する必要性が低いはずですが、そうした企業がさらに防衛策を導入しているという、かなり強い結果が得られました。経営保身の強い企業がさらに「塹壕」を深く掘っているという意味ですので、正当防衛で導入していると言い切るのは難しいでしょう。
もう1つ強い結果だと思っているのは、企業規模についてです。大きい企業ほど買収防衛策を導入しているという傾向があります。一般的には小さい企業の方が狙われやすく、導入していると思われがちですが、結果は逆でした。この結果は米国での実証研究とも同じです。実は、買収防衛策を導入するには、弁護士事務所などに高い費用を支払わなければならず、固定費用が高くつくという問題があります。したがって大企業は導入しやすいのですが、小さい企業も同じように高いお金を払って導入しなければいけない不利があるわけで、これは望ましい状況ではないのではないか、という問いかけに発展してくるような結果といえます。
――そこは政策的なインプリケーションにもつながってきますね。
もともと、買収マーケットというのは、非効率的な経営をしている企業を買収して、より効率的な企業経営に変えるというメカニズムがあります。これが資本主義の根本であるともいえます。ある意味で株式持ち合いなどは、こうした機能を阻害し、資本市場の発展には大きなマイナスの効果を持ちます。企業が自分だけ生き延びれば良いというのでなく、国全体として最適な資源配分を達成し、国を発展させていくには健全な資本市場が必要です。
実は欧州では、ポイズンピルではなく、全部買い付け義務というルールを設けています。グリーンメーラーのように少し買って買い戻しを要求するということを許しません。そういうやり方が欧州では標準的な買収防衛、TOB(株式公開買い付け)の規制になっています。日本にはポイズンピル型が導入されてしまいましたが、私はこの欧州のルールの方が合っているのではないかと思っています。
両方の防衛策を導入することはさすがに買収抑制的になりすぎるので、そういう国はありませんが、理論的に考えるとそちらの方が望ましい。ポイズンピルに頼ることについても反省の流れが出てくると個人的には思っています。
また、買収防衛策導入には高い固定コスト負担が伴い、規模の小さい企業は相対的に不利になることも考えれば、企業が個別にポイズンピル型買収防衛策を導入するのではなく、公開買付ルール(特に全部買付義務)の強化を図ることで、濫用的な買収を排除していくという視点も重要であると考えます。
――日本の買収防衛策自体にも問題があるのでしょうか。
米国のポイズンピルは実質的に発動されたことはありません。もともとは抜かずの伝家の宝刀であって、株主がなるべく高い値段でTOBに応じられるように、時間を稼ぎ、株主のために交渉する手段です。本質的に企業を何がなんでも守り切るための手段ではありません。米国と日本の大きな違いはその認識にあります。こうした事はMBO(マネジメント・バイアウト)をめぐる最近の裁判にも通じるところがあるように思われます。
全部買い付け義務の場合には、少数株主の保護を念頭に置いており、残った株主がどんな価格でも売らなければならないという不利な状況に陥ることを防いでいます。日本ではそうした考え方がまだまだ根付いていませんが、少数株主の保護が資本市場の発展には不可欠です。大株主の論理だけでは株式市場の厚みや流動性が足りず、本来の役割を果たすことができません。こうした本質的な理解が進んでいないことが、敵対的買収への対応にはっきり出ていると思います。
――ブルドックソースのスティールパートナーズに対する防衛策発動をどう見ますか?
地裁判決では、株主総会でつねに正しい判断ができるのかという点に言及しています。株主総会万能主義を取らず、スティール側が経営方針を明らかにしなかったのがポイントだと述べている事は評価できると思います。
高裁の判決で、スティールを濫用的買収者と認定したというのは疑問が残ります。濫用的行為があったかどうかを問題にすべきだったでしょう。しかし、発動が認められるかどうかは、相手をみてケースバイケースで判断するという論点には注目しています。企業は株式持ち合いと買収防衛策の相乗効果で企業防衛をしようとしていますが、どんな場合でもOKというわけではなく、相手によっては発動できない可能性があることが示されました。まともな相手で、正当な価格での提案をしてくれば、ポイズンピルで買収者を排除することは難しいということを意味しているとの解釈も可能だと思います。スティール・パートナーズや村上ファンドが買収した企業でも、その後に業績を大きく改善させた例があり、必ずしも企業価値が毀損されたわけではありません。徹頭徹尾、買収者を排除することはできません。まともな買収者には防衛策があっても守りきれないのではないでしょうか。今後、どのような司法判断がでるかに注目しています。
最近気になるのは、ポイズンピルが取締役会の判断で導入できるにもかかわらず、多くの導入企業が株主総会での判断を求めている点です。これでは取締役会が何もせずに、善し悪しは株主が判断してくれという事になります。これは取締役会の義務の放棄とみられてしまいます。
――今後の研究の方向性についてお聞かせ下さい。
この研究は2006年度までですが、今年度にデータを拡大して特性をみて、2005年度、2006年度との違いを見てみたいと思っています。また、TOBをかけた企業、かけられた企業はかなりの数になりますが、この中には敵対的だけでなく友好的な買収も多いのです。それぞれどういう特性を持つのかというのも、興味深いテーマです。
今研究を進めているのは、非上場会社も含めて、合併や買収に焦点を当て、その後のパフォーマンスが改善しているかどうかです。企業の合併は生産性やイノベーションなどの企業の成長戦略にプラスの影響を与えているのか、そのための有効な手段なのかという問題にチャレンジしています。
解説者紹介
RIETI上席研究員。東京大学理学部数学科卒業。オックスフォード大学大学院経済学博士号取得(D.Phil.)取得。経済企画庁調査局内国調査第一課課長補佐、OECD経済局エコノミスト等を経て、2001年より現職。内閣府本府政策企画調査官、慶應義塾大学大学院商学研究科特別招聘教授、中央大学公共政策研究科客員教授も兼務。代表著作は、『日本の経済システム改革―「失われた15年」を超えて』(日本経済新聞社)、『日本の財政改革―「国のかたち」をどう変えるか』(東洋経済新報社)(青木昌彦氏と共著)等。


