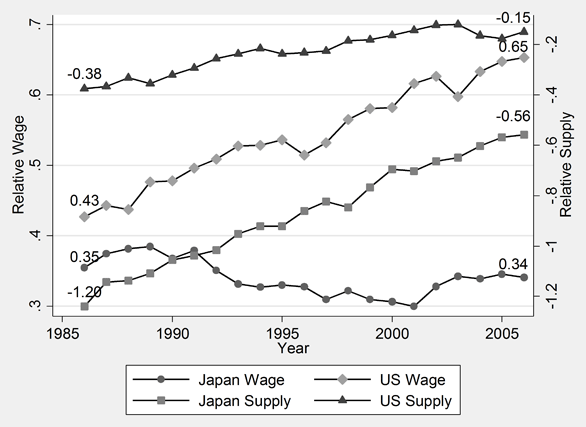このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
人的資本プログラム (第三期:2011~2015年度)
「労働市場制度改革」プロジェクト
米国では1980年代前半から現在に至るまで賃金不平等が拡大し続けており、深刻な社会問題として認識されるに至っている。一方、日本では2000年代に入ってから、若年層を中心に賃金不平等の問題が指摘されているものの、米国において観察されたような賃金不平等の拡大は起こっておらず賃金不平等度は比較的安定的に推移しているということができる。
米国において賃金不平等度の拡大と大卒・高卒間賃金格差の拡大はほぼ軌を一にしており、情報通信技術の発達という技術進歩と国際貿易や海外直接投資の拡大が大卒労働者への需要を増やした一方で、高卒労働者への需要を減らしたことが賃金不平等拡大の主因の1つとなっていることについては学界のコンセンサスがほぼ成立している。
情報通信技術の発達やグローバル化の進展といった大卒労働者への需要増加要因は日本経済にも共通しているのに、なぜ日本では賃金不平等の拡大が観察されなかったのだろうか? この分析では日本とアメリカの大卒者の伸び、すなわち大卒供給の伸び、のスピードの違いにその原因を求める。
第二次世界大戦後の日米比較を行うと、大卒者の比率は米国のほうが常に高いものの、伸びのスピードを比べると日本のスピードは米国の約2倍におよぶ。日本の大学進学率の急伸を説明するためには団塊世代(1947年から1949年生まれ)の後の急激な出生数減少と、1970年代前半の団塊ジュニア世代以降の長期的な出生数の減少に注目する必要がある。これらの人口減少が18歳人口の減少をもたらした一方で、4年制大学の定員は戦後徐々に増えてきたため、大学に進学したいもののできないものが減り、大学進学率が上昇することにつながった。
一方の米国では第二次世界大戦後出生数が増加するベビーブームが1960年前後まで長期にわたって続いた。定員の面からみると米国における大学教育の主力は州立大学であり、その運営が公的資金によって支えられているため、大学定員の設定は政治的な決定に大きく依存しており、18歳人口が増えたからといってすぐに定員が増えるという関係にはない。そのため、ベビーブームが継続し18歳人口が増えると大学進学率は低迷することになる。
日米両国の大卒者への需要構造の変化を推定し、大卒労働者と高卒労働者の相対供給量を日米で入れ替えたシミュレーションを行ったところ、両国の大卒・高卒賃金格差の動き方の違いの約1/3は相対供給の伸びの違いで説明できることが明らかになった。後の約2/3は大卒労働者需要の伸びのスピードが異なることなどで説明されることになる。
この研究結果は戦後の出生率の動向が日米で異なっていたという事実が、大学進学率変化に影響を与えることを通じて両国の近年の賃金不平等度の変化の仕方に無視しえない影響を与えていたことをあきらかにしている。大卒労働者の供給動向が賃金不平等の動向に影響を与えるという視点は今後の大学政策、特に量的な政策を決定するうえでは無視しえない視座を提供する。また、同時に戦後一貫して米国のほうが大卒者の高卒者に対する相対量が多かったにもかかわらず、大卒・高卒賃金格差は米国のほうが大きかったことも特筆に値する。さまざまな要因があろうが日本の大学教育の質の低さと高校までの教育の質の高さが大卒・高卒賃金格差を小さなものに押しとどめていた可能性も否定できない。
技術進歩と経済活動のグローバル化が不可避的に進む中、今後も大卒労働者の高卒労働者に対しての相対需要は伸び続けるだろうことが予想される。この需要増に大学教育の量的拡大や質的改善といった供給がどのように対応するかが、今後の日本の賃金不平等度の行方を決める重要な要素となるだろう。