ライフステージから見た中小企業論
中小企業に関する研究はその多様性を反映して様々なものがあるが、最近、徐々に広がりを見せているものとして中小企業をライフステージごとに追跡していくというものがある。
「企業の一生の経済学」ともいえる一連の研究がそれに当たる。
およそ、この世に存在する全てのもの、森羅万象には始まりがある。そして、それはまだ来ていないにせよ、終わりというものがいつかは来る。人間でいえば誕生という始まりの瞬間があり、幼少期を経て青年期を迎える。そして中高年齢期を経て老齢期を迎え、やがて死という終わりのときが来る。そしてそれらの人生のそれぞれの段階において人は様々な課題に直面する。
企業の一生もこれと同じである。企業の誕生の瞬間とは創業である。生まれたばかりの企業はごく例外的なものを除いて従業員数名の小さな、とるに足らない存在である。さらにその全てが過去の経営実績を有していない。まだ、経済社会において認知されていない小さな存在としての幼少期の企業は、業暦を重ねるにつれてその経営の安定性を高めていく。この内的充実の過程は企業としての発展として捉えることができる。また、幼少期の企業の一部はその後、従業員数等で見た量的成長を遂げる。
こうして企業は創業後、発展、成長段階を経験していくわけであるが、他方、それらのいずれの段階にある企業においても常に付き纏う危機は、企業の「死」としての退出である。企業の退出については多様なパターンが観察される。「老衰」ともいってよい廃業もあれば、死の予兆のある「病死」(つまり長期の営業不振による退出)、それすらない「事故死」ともいえる倒産という形態もある。
さらに人間の場合、物理的には不可能であるが、企業には倒産等の「死」のあとに「再生」という局面がある場合がある。企業はたとえ経営体として機能しなくなったとしても、蓄積された人材、技術、経営ノウハウ等の経営資源を残し、それらの中には企業体が死滅してもなお、市場価値を有するものもあるからである。
個別の企業はそれぞれこのような企業のライフステージを経つつ、個人(企業)史を刻んでいくわけであるが、それぞれの局面でまさに、人間が対面するような様々な課題に直面することとなる。これを追っていくことが「企業の一生の経済学」的アプローチである(第1図)。
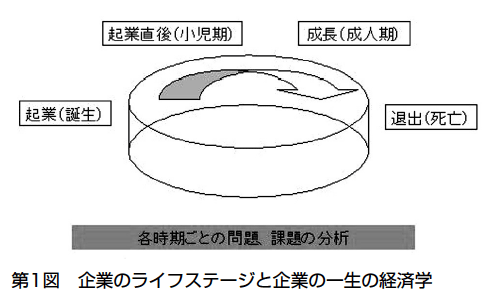
「企業の一生の経済学」的アプローチの特徴
「企業の一生の経済学」的アプローチには、これまでの経済学では無かったいくつかの特徴がある。
第1は研究の対象が「群としての中小企業」ではなく、時間軸で見た個別中小企業であることである。内外における中小企業を巡るこれまでの研究成果は膨大なものに上り、筆者がこれを総括することは到底不可能であるが、方法論的に見ると経済学を基盤とする研究の少なからぬものは、群としての中小企業、言わばマーシャルの「森のアナロジー」における「森」を対象としたものであり、そこに生息する企業、いわば「木」を対象としたものではなかった。日本で言うと山中篤太郎の「中小企業問題」論や、有沢博巳の二重構造論等、いずれも「群としての中小企業」を日本経済の中でどのように位置づけるかが主な研究テーマであり、政府が毎年発行する中小企業白書も「群としての中小企業」の動向を追跡するというものが主であった。これに対して「企業の一生の経済学」的アプローチは、「木」に着目する。集合体としての「森」の変化ではなく、その中に息づく「木」のライフステージ毎の経年変化のパターンを研究対象とする。
ここまで書いて誤解の無いようにすぐに付け加えなければならないのは、第2の点である。それは、近年、急速に広まりつつある「企業の一生の経済学」的アプローチは、特定の「木」の歴史、つまり特定企業の発展過程を対象とした研究ではないということである。ある企業を選び、主にその成長発展と(まれに)失敗について研究する文献は、経営学的アプローチでは個別企業の発展を追う手法が数多く見られる。こうしたアプローチと「企業の一生の経済学」的アプローチは、「群としての中小企業」を分析するというわけではないということでは同じであるものの、前者が特定の企業をピックアップし、これについてその発展や成功、失敗の詳細な分析を行うのに対して、後者は個別企業のデータから抽出される成長企業、失敗企業の代表的な姿を映し出すことを主眼としているという相違がある。
「企業の一生の経済学」的アプローチの有用性
ここまで「企業の一生の経済学」というアプローチについて論じてきた。このようなアプローチには、他のアプローチからは得難い新たな知見をもたらしてくれる。
第1は中小企業行政を行う行政庁に対して、ライフステージのどの段階でどういった形の企業助成を行えばよいかの指針を与えることである。
「中小企業基本法」では1999年の全面改正により、以下の視点が追加された。
1つは以前の中小企業基本法が群としての中小企業を支援する、つまり中小企業全体の底上げを図るという思想を持っていたのに対して、改正後の中小企業基本法では、個々の「やる気と能力のある中小企業」を支援するという形で支援対象が変わった。
これに加えて改正後の中小企業基本法では、創業という企業の一生の特定段階を支援することを明記している。さらには事業再生の観点をも取り込んでいる(第22条)。
このように改正後の中小企業基本法は「企業の一生」という観点を組み入れている。そして、創業や再生といった個別ステージを対象とした政策として何が必要かの分析、すでにある政策の有効であるか否かの検証は、「企業の一生の経済学」的アプローチにより可能である。
例えば政策の目的が雇用創出にあるとすれば、雇用創出率と企業年齢、企業規模、業種等企業属性の関係を計量モデルにより分析していけばよい。こうした試みは80年代以降、途上国を含め幅広く行われており、規模が小さく、年齢の若い企業ほど、高い雇用創出力を有していることが明らかになっている(Age=Size Effectという。なお、わが国についてのAge=Size Effectの成立の厳密な分析については、Yasuda(2005)参照)。
そしてこのことは、創業の円滑化や中小企業の支援のための政策に対する一定の根拠を与えるものである。
また、しばしば指摘されることに、創業に当たり起業家が最も苦労するのは資金繰りということがある。しかしながら、これとてもすべての起業家が一律に資金繰りに苦労するのではなく、特定のタイプの起業家が特に苦労すると考えるのが自然である。その場合、個別の起業家についての多様なデータがあれば、特に資金調達が問題となる起業家のタイプを抽出でき、政策資源をそこに集中投下することが可能である(こうした方向の試みとしては本庄(2006)等が上げられる)。
さらに政策を「投与」した企業と「投与」しなかった企業について、企業属性を考慮に入れた場合のパフォーマンスの差を見ることによって、政策の効果を査定することも可能である。
例えばMotohashi(2001)等が中小企業創造法の効果について検証し、パフォーマンスにプラスの寄与との報告をしている。また、安田(2005)は、国民生活金融公庫の融資制度と創業規模の関係を分析し、同制度の存在は民間からの借入を政策金融に代替させるというより、民間金融では限界がある融資を補完する働きがあることを指摘している(第2図)。
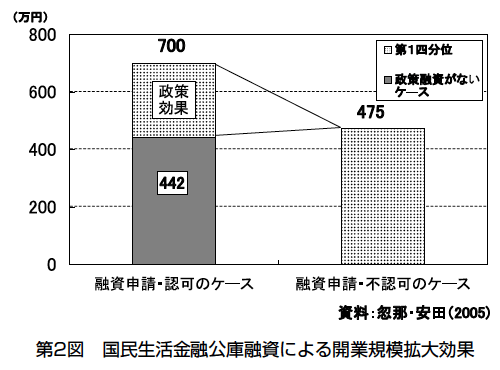
このように「企業の一生の経済学」的アプローチは、政策の立案や修正に対して有用な情報の提供を行っていくものであるが、中小企業関係の実務に携わる者にとっても有益な示唆を与える。すなわちそれは、これから企業を目指す者、既に経営者となっている者、さらにその周辺の金融機関、会計士、コンサルタント等に、ライフステージの各段階で直面する課題を提示し、それに対する対処法を提示する。どのような企業がこれを乗り越えることに成功し、どのような企業がそれに失敗するのかを明らかにすることである。
こうした点から「企業の一生の経済学」というアプローチは、実経済に携わる者にとっても有用な知見を与えるものと考えられる。
「企業の一生の経済学」発展のための課題
このように、極めて実務に近い存在である「企業の一生の経済学」的アプローチについて、今後、それを発展させていくためには何が課題であろうか。その最大のものは統計インフラの整備である。「企業の一生の経済学」的アプローチにとって必要性の高い研究インフラは、他のアプローチによる研究と大きく異なる。官庁等から通常発表される統計は、一般に企業全体の動きを捉えるもの、いわば「森」についての統計が多いのに対して、「森」ではなく、「木」をみる「企業の一生の経済学」においては、多くの企業についての個別データ(個票)が必要となる場合が(全てではないが)多いからである。創業からの企業の年齢が分かり、かつ、それぞれの企業の行動属性が分かれるデータがあれば、年齢による企業の行動や、直面する問題の違いについての様々な分析が出来るわけである。それは丁度、老若男女の身長と体重のデータをある時点で集めれば、それを元に人間の年齢による肉体的成長のパターンが明らかになるのと同じである。そして後述するように、こうした個票データを用い国内外で様々な研究が行われている。
但し、単なる個票データを用いる分析では不十分である場合がある。一調査時点での企業年齢別データからは、企業の年齢増加(加齢)による影響と企業を取り巻くある時点の環境が、企業に対して与えた影響を峻別できず、真の関係が把握できないことがあるということである。
一例を挙げよう。先に述べたように一般的には、若い企業の方が高齢企業に比べ高い成長を示すということがいわれている。従って、ある観察時点で創業時以降の企業年齢によるグループ毎に、企業の創業以降の年平均従業員成長率を算出すると、創業後間もない若い企業のグループほど高い成長率を達成するはずである。しかしながらもし、企業が活動している経済が著しく縮小している場合には、若い企業は悪化する経済の中で低成長を余儀なくされ、かつてのより良好な経済の果実を享受した古い企業に比べ、低い成長率となってしまうかもしれない。従ってこの経済を観察する経済学者は、企業の年齢と企業が活動した時代の影響を混同して、若い企業ほど成長率は低いと判断するであろう。
では、こうした誤謬を回避するためにはどのようなデータが必要であろうか。必要なのは個別企業毎に期間毎の変化を追跡した時系列的データである。このようなデータを経済学ではパネルデータという。パネルデータがあれば、個別企業自体の時間経過に伴う変化と、企業を取り巻く環境が企業に対して与えた影響を峻別出来る。
ここまでみたように、「企業の一生の経済学」的アプローチを進めるためには統計データについて2つの点が重要となる。すなわち、
(1)個票の学術研究のための利用の容易さ
及び、
(2)個票データを時系列的につなげたパネルデータの整備
である。
第1点目の個票の利用については、わが国の場合、統計法の基本的考え方である「統計情報の守秘義務」という観点から、国が作成する統計については、困難な面がある。
しかしながら、国が実施する指定統計、承認統計以外については、近年、研究者の個票利用を促進する関係機関の動きが日本でも少しずつ進んできた。こうした例として、東京大学社会科学研究所が1997年から構築した統計情報アーカイブがある。このアーカイブには、民間調査機関等から寄託された多数のアンケートの個票データが利用可能である。
第2点目としてパネルデータの整備については、現在のところ、筆者の知る限り広く中小企業研究の用に供する民間データは、ほとんどない。非政府機関による調査では特定企業に毎年、アンケートの回答を求めることは困難であることによるのであろう。政府及び政府関係機関の試みは少しずつ進展しているものの、なお努力が必要であろう。
まとめ
以上、「企業の一生の経済学」的アプローチの中小企業研究における特徴、有用性、課題について概観した。統計データの豊富な欧米においては、この種のアプローチから様々な興味深い成果が生まれてきたが、それらを紹介することは誌面の関係で到底、可能ではない。
他方、独立行政法人経済産業研究所は、2004、5年に研究プロジェクト「中小企業とベンチャービジネスの発展の諸段階」の中で「企業の一生の経済学」的アプローチに基づく中小企業分析を進めてきた。昨年6月には「中小企業のライフサイクルと日本経済の活性化」というタイトルで政策シンポジウムも行った。そして今般、RIETI経済政策分析シリーズとして『企業の一生の経済学』*が出版される。そこでは、創業、青年期、さらには経営者の交代や最終段階としての企業の死といった中小企業のライフステージの各段階における課題克服に係る分析が、8本の論文の形でまとめられている。
「企業の一生の経済学」的アプローチを多く盛り込んだ日本における数少ない試みであり、かつ、欧米におけるこの分野の研究成果のサーベイも行っている同書は、本論では紹介に留まった「企業の一生の経済学」について感心のある方にとって有用なものである。
こうした書物を出版する経済産業研究所の活動が、日本の中小企業研究に新しい視角を提供することを期待して本論の結びとする。
*…橘木俊詔・安田武彦編著『企業の一生の経済学』、ナカニシヤ出版より近刊。


