10年ぶりのケンブリッジ
約10年ぶりにアメリカに住んでみて最も印象的だったのは、日本から見える世界とアメリカから見える世界のスコープと厚みが違うことでした。その最大の理由は、10年前には半導体問題やプラザ合意などの世界の最先端の問題に日本が参加し、日本のマスコミや知識層も当然それを巡って色々な議論をしていましたが、現在はそういったイシューに日本が参加する機会も減り、日本のマスコミや知識層の取り上げ方も小さくなったことにあると思います。この変化の背景は、下表「世界のGDPに占める構成比」がうまく表現していると思います。世界のGDPに占める割合では、アメリカは80年から90年は横ばいだったのが2000年以降盛り返しています。ヨーロッパは着実にウエイトを下げていますが、まだ最大のシェアを持っています。日本は80年から90年にかけて飛び上がったが2000年にかけて下がってきていること、そして東アジア、これは中国が中心ですが、急速に大きくなってきているということが分かります。
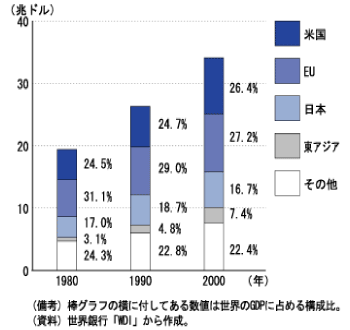
この結果、アメリカの世界各国に対する吸引力は増す一方で、話題としてもそもそも外国に学ぶというよりもアメリカ自身の事が中心になり、ヨーロッパと日本のウエイトは小さく、中国の存在感が大きくなっています。ヨーロッパの場合、こうして存在感が下がっても人的なプレゼンスはあるのですが、日本の場合には存在感が下がると同時に国際的な場に呼ばれなくなり、行かなくなるという傾向が、拍車をかけているように思われます。
アメリカ再生の要因
10年前のアメリカは先端産業の苦境と日本のハイテクの脅威にさらされていました。その後驚異的な経済再生を成し遂げたわけですが、3つの要因が挙げられます。まず第一は、10年間で移民を中心とする3000万人もの人口増加とそれに伴う個人消費の伸びが挙げられます。また、財政収支は95年から2000年にかけて財政黒字に転じており、この結果金利も下がり、機動的な財政金融政策が取れるようになりました。しかし何よりも大きいのは、その好条件を生かしたIT投資とそれによる生産性の向上だったと思います。この10年間でITを中心に新たに生まれてきた市場化の波にアメリカはきわめて上手に適応しました。まず、過去20年の間に何度かのラウンドを通じて経済のボーダーが無くなり、グローバルな市場ができて来ました。また、情報化が進み、膨大な情報を素早く処理できるようになることによって市場は大きく強力なものに生まれ変わりました。この結果、非常に速くダイナミックな変化を伴う強力な市場が誕生したことで、どんなに優秀な企業・有能な経営者であっても、環境が変わった瞬間に過去の投資が不良債権に変わるリスクに面することとなりました。しかし、同時にリスクテイクし、かつリスクマネージできない企業は市場機会のメリットも享受できないという競争環境が生まれたわけです。そういう新たな時代に、アメリカは極めて適した社会構造を持っていました。具体的には、アメリカの自由と競争への信仰は、その市場の力を生かす上で最も重要な競争環境を作り出し、資本市場においても出資を中心としつつさまざまな工夫ができる自由な資本市場の形成につながり、元々柔軟であった労働市場をより柔軟にし、さらに、市場に敏感な経営と徹底的に収益を求める厳しい市場型ガバナンスを作り出しました。また、インターネットは新たなIT投資とITインフラをフルに生かす環境を作り出し、今やITは社会の隅々まで浸透し、生産性パラドックスと言われていた状況から具体的に生産性向上へ結び付く方向へと動き出したわけです。これらの変化は成長力の源泉であるR&Dに関しても大きな変化を作り出しました。今までのように3、4年の期間、身内だけで研究を実施し商品化をしていくというスタイルは、スピードの上でもスコープの上でも間に合わなくなりました。その結果、改革された大学を中心とする多くの研究拠点と、それらをいち早くビジネスに結びつける人々がその周りに形成され、それがベンチャーとなって結実するというこれも極めてアメリカ的なシステムが自由と競争の環境の中に出来上がって行きました。
また、人口増加はアメリカが魅力的で世界中の有能な人をひきつけていることを示しています。この点大学は特に強く、それがまたさらに人を呼び込む魅力になり、また、多様性も強みになっています。と同時に教育全体に対しても人口増加による競争圧力は、学校側の競争とあいまってきわめて強い研究・教育事業体を形作っています。
資本市場を見ると、日本と比較してアメリカでは株式市場などを通じてリスクマネーが家計から企業へ多く流れており、また債権市場・信託が発達していることから、個人金融資産がこれらを通じても企業に流れています。また、アメリカのコーポレートガバナンスは、日本やヨーロッパと比較すると会社法より証券法のウエイトが高く、出資中心で、株式の分散所有が進んでいるという特徴があります。この結果、制度的にも他のステークホルダーの利益に比べて株主利益の最大化が強調され、銀行ではなく市場が中心となった外部ガバナンスの形成などが見られます。そして、それが米国が世界経済をリードし、グローバルスタンダードになっていったと言えます。その過程でペンセントラル事件や機関投資家問題、エンロン・ワールドコム事件などへ素早く対応し、取締役会の一元化、外部取締役中心という徹底したスタイルに行き着いたわけです。この仕組みは1つの極端な制度で、アメリカ型の単一スタンダードの押しつけと反発もかっています。イギリスやドイツを見てみると、1つの原則を提示しつつ原則を取らない場合は説明を求め、例外をある程度受け入れる幅があるのと比較するときわめて対照的です。アメリカ型スタンダードの押しつけに対し、世界がどういった反応を示すかは別として、資本市場でも労働市場でもガバナンスでも、市場の力を徹底的に追求させる仕組みを作り、かつそれが今のところ成功していると言って良いと思います。
では次に、アメリカ経済の再生が何をもたらすのかということを考えてみます。まず、急速な生産性向上は雇用無き経済再生を生み出し、貧富の差や分配問題を生みだしているといわれています。しかし同時に豊かになった資金がNGOや大学などに流れたりすることで、より多くの人々がその恩恵に浴しているのも事実です。この状況がアメリカを分裂させていくのか、それとも豊かな社会、新たな働き方に導いていくのかというのが1つのポイントだと言えます。また、経営者に徹底的に利益を求めるコーポレートガバナンスのシステムは、企業の社会的責任とどう調和していくのかという問題を生じさせています。さらに、50年代や60年代、また現在のブッシュ政権にも見られる通り、アメリカが一人勝ちをした時に頭をもたげる「自由と民主主義を世界に」という宗教的ともいえる使命感は、コミットメントを拡大させ財政赤字につながる要素もあります。現在の財政赤字と経常赤字が膨らんでいく姿は、70年代のベトナムを思い出させ、ある種の不安を作り出していると思います。そういった意味で、アメリカ経済の強さというのは本質的には変わりませんが、この3つの問題について今後どういった形で展開していくのかというのが気になるところです。
アメリカと中国
アメリカと中国の様々な意味での接近というのは非常に印象的であり、かつ今後しばらくは続くものと考えられます。アメリカで私が参加した様々な学会や研究会でも、中国をフォーカスしたパネルの数に比べて日本のパネルの数は少なく、また、中国といえば研究資金が付くけれど日本というと付かない、といった状況になっており、アメリカにおける日本と中国の位置関係を象徴する形になっていました。中国経済に関し簡単にまとめると、誰も説明できない社会主義型市場経済を標榜しつつ、WTO加盟によりアメリカ型モデルによる市場経済化と国営企業の改革へと大きく舵を切り、多国籍企業のサプライチェーンに入ることによる輸出セクター主導型の成長を農村部からの人口流出で支えている、ということができると思います。日本とはパターンの異なる成長モデルですが、あえて言うなら50年代から60年代始めの日本に近い側面があるというところかもしれません。しかし、サイズが大きいが故に世界経済へ与えるインパクトは、貿易面、通貨面、エネルギー面で70年代初頭の日本並みだと言えます。また、中国国内の制度面実態面での未成熟さと世界へ与える影響の大きさは、非常にアンバランスです。その意味で、今後の中国経済には、相当大きな試練やリスクがあります。目の前にはバブル問題、国営企業の不良債権の問題があり、通貨調整も避けられないと思われます。エネルギー政策でも、特に96年に石油の純輸入国になってからは、世界中で鉱区を買い漁るというパニック状態が続いています。現在のアメリカの中東政策、対テロ政策の結果引き起こされているサウジの不安定化とあいまって中国の行動は、第二次石油ショック以降築きあげてきた市場化と主要国の自衛と相互信頼によるシステムの維持を不安定なものとしています。また、究極的には、江沢民路線と新体制路線の間の緊張をはらみながら、社会主義的市場経済という本質的矛盾が、第二の天安門に導くのかあるいは体制の崩壊につながるのかという問題があります。これらに伴うショックをソフトなクッションを備えたような他の先進国経済のようにマネージすることは、若く有能な中国のテクノクラートにとっても極めて難しいことです。私は中国をIEAとG7に入れてしまうべきだと思います。日本を70年代初頭にサミットに参加させ、IEAを設立しそこに取り入れG7にも組み込んでいったように、いかに中国と対話し、移行期のリスクを助け、中国に不安心理を起こさせないようにするかということが大きな鍵になると思います。
アメリカの日本経済の評価と課題
アメリカから冷静にEU、日本、中国を並べて今後の世界経済を支えるパートナーを考えた場合、EUは拡大路線を取りながらも制度的な硬直性が残っており、20年に渡って世界経済におけるウエイトを下げ続けていることであまり期待できない、中国はまだリスクが大きいとすると、日本を再評価しようということになります。すなわち、世界経済の中ではウエイトが高く不良債権処理も進むなどようやく日本経済が離陸したと評価と期待が大きくなってきています。その一方で、労働市場にしても資本市場にしても、グローバルな市場経済が要求する柔軟性を持ちうるだろうかという疑問も根強く残っています。これに加えてGDPの140%という財政赤字を抱え、労働人口の減少・総人口の減少の問題もあります。しかしアメリカからみると、結局何も動かないと思っていた日本経済が、小泉流改革でそれなりに効果を発揮しつつあると見ており、最近の日本に対する評価は変化してきたと言えると思います。逆に言えば今回の選挙の結果、小泉政権が今後どうなるのかということが日本に対するアメリカのマーケットの評価を変えていき、それがまた実体を動かしていくという循環をしかねないという要素を抱えているとも言えます。一方で、グローバルな資金の流れが日本経済に対する世界の認識によって左右される状況にあって、日本側からの発信という点から見ると、サミットなどの場はあっても、コミュニケートをする能力が十分でなくコミュニケートをするための知的な投資も行われていない、ということは実は深刻な問題だと思います。
まとめ
アメリカは10年前に冷戦が終わった時、新たな世界秩序を模索することから始めました。その答えの1つがネオコンの言うところの「自由と民主主義を世界へ」というある種崇高で、ある種独りよがりとも思われるコンセプトです。それに9.11がカウンターになった形でテロとの戦いが中心に据えられ、経済外交は後方に下がっている、というのが現状かと思います。「自由と民主主義を世界へ」という思想自身はアメリカの中では実は疑われているわけではありません。現在論点となってきているのは、それを一国主義型、ブッシュスタイルで実施していくのか、それともジョセフ・ナイがいうところのソフトパワーにもう少しウエイトを置くのか、という違いです。ソフトパワーと言っても、力を背景にした強いアメリカとワンセットになっているソフトパワーであり、ソフトパワーだけでなんとかなるとは誰も思っていません。次の選挙でケリーが中心になったとしてもこの点は変わらないと思われます。
10年前と比べて世界の動きの中心はヨーロッパからアジアに移りました。アジアでは、中国は、アジア各国から警戒をされながらも、周辺国からの輸入の拡大と、進んで多国間取り決めにも入ることで経済面でも外交面でも存在感を増大させています。それに対し、アメリカは未だにアジアの中心ではあってもその力を赤裸々に示すことから反感も招いています。韓国における若年層の親中国、反米傾向がそのよい例です。また、台湾問題は米中両国を巻き込んで極めて緊迫した状況にあります。日本はアメリカからもアジアからも様々な活躍を期待されているのですが、政治的にも経済的にも知識層も内向きで弱気になっており、期待に応えようとしていないように見える事がもっとも気になるところです。
質疑応答
- Q:
日本はFTAに力を入れ、WTOの地位が相対的に落ちているように見えます。WTOの日本の通商政策における位置付けについてどうお考えですか?
- A:
中国がWTOに加盟したことから、今後WTO違反の問題は必ず出てくると思います。これに対し、WTOの原則に沿ってWTOの問題として処理していくというスタンスを変えてはいけないと思いますし、WTOの地位が下がっているとは思いません。日本は日米問題の後遺症としてWTOから離れることへの恐怖感と農業を守るという国内事情から、FTAから遠ざかりすぎたというのが私の印象です。しかし、先ほど述べた人口問題の解決を含めて考えても、FTAは避けて通れないプロセスであると思います。
- Q:
中国のG7加盟の実現性についてどうお考えですか?
- A:
ロシアの加盟によりG8となったサミットに中国を加えG9にするかどうかという議論は、加盟国間で抵抗のある話のようです。一方で、G7財相・中央銀行総裁会議では、中国抜きの議論は意味をなさなくなっており、中国を入れて議論しなければならないという認識はG7側でも中国側でも高まっているようですし、能力的にも可能だと思います。しかし、すぐにG7財相・中央銀行総裁会議に中国を入れてG8にするかというと、ロシアの抵抗や、中国国内でもグループの間の調整問題があるようで、形としては紆余曲折があると思います。
本意見は個人の意見であり、筆者が所属する組織のものではありません。
※本稿は7月14日に開催されたセミナーの内容に一部加筆したものです。
掲載されている内容の引用・転載を禁じます。(文責・RIETI編集部)


