はじめに
2001年から2006年までの国の科学技術政策の基本的方向性を示す第2次科学技術基本計画には企業のイノベーション活動を促進するためのイノベーションシステム改革の方向性が強く打ち出されている。産学連携の推進はその中核的なイシューであり、研究開発に関する大学や公的研究機関と企業の連携を促進するための制度改革が急速に進んでいるところである。たとえば1998年のTLO法の制定によって、大学や公的研究機関におけるTLOの設置が進み、また2000年に成立した産業技術力強化法には、大学における研究者の兼業規制緩和や国立大学における民間からの資金受け入れ円滑化措置が盛られている。
このような最近の政策的措置に対応して、大学、企業双方において産学連携を積極化させてきているが、1980年代に各種制度整備が進んだ米国と比較するとまだまだその動きは遅れている。その主な要因は20年近いタイムラグであるが、日米のイノベーションシステムの違いによる影響も大きいと考えられる。すなわち、米国においては、ベンチャーキャピタル等の直接金融市場が発達しており、また人材の流動性も高いことから、産学連携や大学発ベンチャーを含めた組織を超えた研究開発の連携が行われやすい。その一方で日本は、大企業それぞれが組織内で行う研究開発が中心で、このような「自前主義」が産学連携を阻害する一因となっているのではないかとの指摘がなされている。(元橋(2001))
このように最近動きが急になっている産学連携の実態を的確に捉えるため、経済産業研究所では昨年2月に「産学連携実態調査」を行った。その調査結果については、RIETIホームページで詳細に公表しているが(経済産業研究所(2003))、ここでは同調査のデータを用いてより詳細な計量分析を行った結果を紹介する。上記の日本のイノベーションシステムとの関係では、産学連携における研究開発型中小企業の役割に着目することが重要である。大企業に自前主義の傾向が強いのは日本に限られたことではなく、米国においても大企業のNIH(Not Invented Here)シンドロームの問題が指摘されることがある。日米のイノベーションシステムの大きな違いは、米国においてはベンチャー企業や研究開発型中小企業が大きな役割を担っていることである。ここでは、我が国の産学連携における研究開発型中小企業の位置づけについて大企業を比較しながら述べていきたい。
中小企業に裾野が広がる産学連携
「産学連携実態調査」は、経済産業省の企業活動基本調査の対象企業(従業員数50人以上でかつ資本金3000万円以上の製造業または卸小売業に属するすべての企業)のうち研究開発を行っている企業すべてを対象としている。調査の内容としては、(1)大学、公的研究機関の他、企業との連携も含めた研究開発に関する外部連携の状況、(2)大学との共同研究の件数、予算額等の産学連携の詳細、(3)産学連携に対する評価や課題に関する定性的な項目の大きく三本立てとなっている。ここでは、同調査と企業のパフォーマンスに関して有益な情報を与える企業活動基本調査を企業レベルで接続したデータを用いて分析を行っている。
まず、産学連携の決定要因(産学連携に取り組んでいる企業の特性)について分析した結果によると、これまでは産学連携を行っているのは大企業が中心であったが、ここ5年程度で中小企業に対して裾野が広がってきていることが分かった。産学連携の実態を詳細に見ると技術やノウハウの移転や特許のライセンシングといった形態をとるものは少なく、共同研究を行う場合が多いことが分かっている。すなわち、大学における科学的知見は、企業がそれをそのまま受け入れて活用するのではなく、企業においても大学の協力を得ながらさらに研究開発を進めていく必要があることを示している。目標とする技術について、「make(自社開発)or buy(他社から調達)」の判断をするものではなく、co・development(両者で開発)が必要なのである。つまり、産学連携を有効に進めるためには、自社内にも十分な研究リソースを有することが必要となり、そのような資源が豊富な大企業の方が産学連携をより効果的に活用できると考えられる。
今回の分析結果を見ると、特に5年前の状況については、研究開発に関する自社リソースが豊富な大企業において産学連携により積極的であるとの結果を得た。しかし、最近の状況を見ると産学連携の決定要因として、企業規模の影響は統計的に有意ではあるものの、やや弱まるという結果となっている。また、企業規模だけではなく、企業年齢も決定要因に加えた推計を行うと、企業規模による効果がなくなり、企業年齢が若くなるとより積極的に産学連携に取り組んでいるとの結果が得られた。このように、産学連携の決定要因として、企業規模効果は逓減してきている。
この点をより明確化するために、ここ5年間で産学連携に対する取り組みを始めた企業の特性をみてみると、まず企業規模の効果については統計的に有意な係数が得られなかった。その一方で自社研究所を持たない企業の影響が強く現れた。自社研究所を保有していることは、内部研究開発が充実していることを示していると同時に、比較的基礎的な研究まで自社のリソースで賄うという企業の研究戦略を表している。その際、基礎的な研究を行っている大学と自社研究所は競合する可能性があり、産学連携の決定要因として、このところ、この競合効果の影響が高まってきたと考えることができる。つまり、最近の傾向として、自社内の研究リソースが十分でない中小企業においても、産学連携を通じて基礎的な研究開発に積極的に取り組んできているといえる。
中小企業において大きな効果が見られる産学連携
ここでは、産学連携に対する取り組みと企業パフォーマンスへの影響について述べる。まず、企業のイノベーション活動に対して産学連携が与える影響について見た。イノベーションのアウトプットとしては、新製品の開発(プロダクトイノベーション)や新たな生産方法による効率性の向上(プロセスイノベーション)が考えられるが、ここでは特許数を用いた。インプットとしては、研究開発費とともに研究開発に関する外部委託の有無や産学連携の有無を入れて、産学連携のイノベーションの生産性に対する影響を評価した。結果としては、産学連携の実施はイノベーション生産性に対してポジティブな影響を与えていることが分かった。なお、この分析は企業年齢によって3つのグループを作成し、それぞれのグループ毎にも行った。その結果、企業年齢の若い企業において、産学連携の影響は特に強く現れることが示された。
また、企業の付加価値をアウトプットとして、労働や資本のほか、研究開発投資、産学連携の有無などをインプットとする生産関数を推計して、産学連携の生産活動における生産性に対する影響の評価も行った。結果としては、産学連携は生産関数で評価した生産性に対してもポジティブな影響を与えていることが示された。さらに、イノベーション活動における生産性への影響分析と同様に、産学連携の影響は年齢の若い企業でより強く現れているという結果となった。
このように、このところ産学連携の裾野が、企業規模が小さく年齢が比較的若い研究開発型中小企業に広がりつつあるが、イノベーションや生産活動に対する生産性への影響はこれらの企業においてより強く観察されるということが分かった。なお、イノベーションパフォーマンスが高い中小企業の台頭については、TAMA(注)における製品開発型中小企業を詳細に調査した児玉(2003)においても示されている。中小企業の産学連携においては、このようは地域的なネットワークの役割が重要であると考えられるが、この点についてのデータ分析は今後の課題として取り上げたいと考えている。
日本のイノベーションシステム 改革に対するインプリケーション
企業年齢が若く企業規模の小さい研究開発型中小企業は、産学連携を行うことによって研究開発活動や生産活動における高い生産性を確保している。これらの企業においては、大企業と比較して資金や人材などのリソースが豊富に存在しないことから、外部連携に積極的に取り組み、新商品の開発などのより製品化に近い産学連携を目指していることが考えられる。ただし、この生産性の高さは産学連携を行っていない同種の若い企業と比較して見られる相対的なものであるということに留意することが必要である。従って、中小企業はそのすべてが産学連携に成功しているのではなく、むしろ経営資源が豊富でない企業において、リスクに高い産学連携に取り組んだ結果として成功した企業は高いリターンを得ていると解釈するのが自然である。
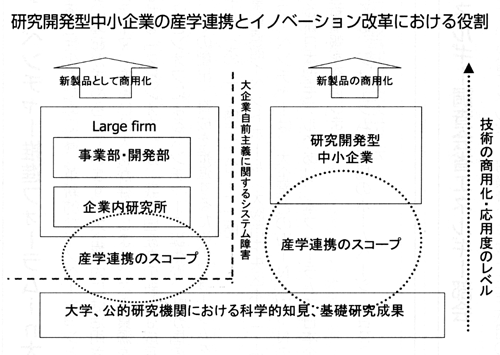
このようなリスクをとって産学連携などの研究開発に関する外部連携を進める研究開発型中小企業は、高い成長ポテンシャルを有しているとともに、大企業が中心の日本のイノベーションシステム変革の起爆剤となる可能性がある。左図は日本のイノベーションシステムの改革における研究開発型中小企業の位置づけについて模式的に示したものである。
日本のイノベーションシステムは、硬直的は労働市場や技術市場が未発達であることなどのシステム的な障害があることから、研究開発に関する外部連携が活発に行われてこず、大企業が自社の研究開発リソースを用いたイノベーションが中心的な役割を果たしてきた。しかし、このような自前主義では、IT革命に見るように技術進歩が急速に進む分野においては、イノベーション競争に乗り遅れる可能性がある。また、バイオ技術の進展によって医薬品の研究開発プロセスが大きく変わってきており、遺伝子機能解析などの科学的知見を有する大学等と有効に連携することが重要になっている。このようにITやバイオなどのハイテク分野においては、イノベーションにおける外部連携を重視したネットワーク型のシステムが比較優位をもつようになってきている。
研究開発型中小企業においては、大企業のように研究開発リソースに恵まれていないため、システム的な障害を乗り越えて、新製品の開発など具体的な成果に結びつく産学連携に乗り出すインセンティブが強い。また、大学サイドにおいても、基礎的な研究シーズを志向する大企業と比べて、中小企業と連携する方が研究成果の実用化というインセンティブが満たされる可能性が高い。このような、研究開発型中小企業によるシステム的な障害を乗り越えた産学連携が活発化することによって、システム全体をより流動的なものに変わって行く可能性が高い。このところ、規模が小さく、年齢が若い企業における産学連携に対する取り組みが進んできていることが観察されたが、このような研究開発型の産学連携に対する取り組みは社会的便益の面でもメリットの大きいものであり、政策的にも一層推進すべきであると考える。
詳細については、「産学連携の実態と効果に関する計量分析-日本のイノベーションシステム改革に対するインプリケーション」を参照されたい。


