この春、大学は1985年生まれの新入生を迎えた。日本のグローバル化元年とも言うべきプラザ合意はもはや歴史になりつつある。合意後、急速な円高進行に対応し、日本産業は海外生産を一気に増大させた。とりわけ東アジア対しては集中的な生産移管・再配置が行われ、工業化の版図は大きく塗り変わった。その後も日本のバブル崩壊、通貨金融危機、後発の巨人・中国の本格的台頭など、ドラマは続いているが、今になってみれば、すべてはその時、日本自身によって始まったのだ。それでは再び巨大な構造転換期を迎えた日本はグローバリズムにどう向き合い、東アジアとつきあっていくのか?
対外開放をめざす日本
日本では、失われた10年を経て、改革への機運が高まっており、中でも国際化をテコに経済の活性化を図る動きが盛んになっている。これまで、日本経済の国際化といえば、モノ、ヒト、カネが海外に流れることが中心だったが、白書では、これらが国内へ流れる逆方向の「対外開放」という側面が焦点となっている。
これまで低調であった対内直接投資が、近年、政府の奨励の対象となったこともあり、M&Aを中心に増えている。直接投資の流入が技術や経営ノウハウの導入、雇用創出やスキルの開発、競争の促進による生産性の上昇や消費者利益の拡大を通じて、日本経済の活性化につながることが期待されている。現に、白書で具体的に紹介されているように、フランスのルノーによる日産の買収をはじめ、大きな成果を収めつつある事例がたくさんある。しかし、日本の対内直接投資が近年増えているとは言え、残高ベースでGDPの1.2%にとどまっており、米国の25%には遠く及ばない。その一方で、国内の不況が長引くなかで、一部の外資企業が、業務を縮小し、また日本から撤退する動きも見られることを考えると、まだ楽観的な見通しは立てにくい。
外国人労働者、特に専門的・技術的労働者の受け入れについても、白書では「経済活動の高度化に資するものであり、基本的には経済の活性化が図られる」と積極的姿勢が打ち出されている。しかし、現状では、対内直接投資と同様、労働力の受け入れに関しても、日本は先進諸国の中で、最も低い水準に留まっている。ITなどの先端分野においては、国内の人材不足を補うために、インドなど海外の人材を活用することも一案だが、いつまで経っても、旧態依然の大学が、新しい産業を支える人材を提供できていない(提供しようともしていない)現状を改めなければならない。米国では、留学生の受け入れを通じて、世界中から優秀な人材を獲得しているが、日本の大学は国際競争力が欠如しているため、国内の人材を育成する機能も、海外から人材を集めてくる機能も十分に発揮していない。
一方、対外直接投資に関して、白書では、米系企業に比べ、日系企業の収益率は大幅に下回っており、中でも、現地市場参入型投資の収益率が低くなっていると指摘されている。この原因としては、日系企業には経営の現地化が遅れていることにより、優秀な人材が集まっていないことが大きいと見られる。実際、最近発表された中国の大学生を対象とするアンケート調査によると、外国企業の中で最も人気のある就職先として米系企業がその上位を独占し、トップテン入りを果たした日系企業は一社もない(表)。研究開発といったハイテク分野や、マーケティングにおいて、人材が事業の成功のカギを握っているだけに、現地化の推進は日系企業にとって緊急の課題になっている。
このように、白書では対外開放の進展をアピールしようというスタンスが随所に見られるが、実際には一部の分野における変化の兆しが見えただけで、大きい成果を上げるには至っていない。日本経済全体の活性化を達成するためには、さらなる対外開放と構造改革の加速の好循環を定着させなければならない。
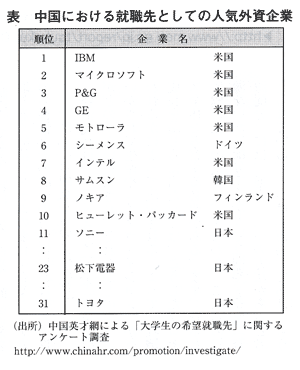
「東アジアビジネス圏」のカギとなる日中提携
その1つの方法として、白書では「東アジアビジネス圏」の形成が提案されている。現に、高成長が見込まれる東アジア各国間との連携を強化する実態としての相互依存から、制度化した経済統合に向けて、東アジア各国での動きが活発化しつつある。こうしたなかで、日本・シンガポール新時代経済連携協定や、日本・ASEAN、中国・ASEANなど、小さなFTAを積み上げて、いずれASEAN+3(日本、中国、韓国)自由貿易協定に収斂させるという暗黙の理解ができているようである。しかし、どういった国の組み合わせで、またどのような順序とスピードでこの目標に向けて進むべきかに関しては、試行錯誤の段階にとどまっており、説得力のある理論はまだ存在していない。
国際経済学の教科書に沿っていえば、FTAの経済効果としてはプラスの「貿易創出効果」とマイナスの「貿易転換効果」が挙げられる。競合関係ではなく補完関係にある国々の間では、貿易創出効果が貿易転換効果を上回る可能性が高く、FTAを結ぶことによって得られる利益が大きいとされている。一般的に、発展段階が離れている国ほど補完関係が強く、逆に発展段階の近い国ほど競合関係が強いことを考えれば、アジア諸国の場合、日本とNIEs諸国・地域が中国との補完関係が強く、ASEAN諸国と中国の間では競合関係が強いことになる。中でも、日本と中国の間における補完関係は特に強く、FTAの締結による経済的メリットも最も大きいと見られる。
しかし、現状では、日本とシンガポールの間で経済連携協定が先に調印されたように、経済効率の論理とは無関係に、できるだけ反対を避けるという政治的配慮が優先されている。ここでは2つのジレンマが生じてくる。まず、やりやすい順で進めると、いずれやり難い分だけが残り、広域の貿易自由化につなげていくという構想が途中で挫折しかねない。一方、政治的にやりやすい場合ほど経済的にメリットが少なく、逆に、経済的にメリットの大きい場合ほど、産業の調整とそれに伴う利益の衝突の規模が大きくなる。分業の利益という経済の観点からは、日中FTAが最も望ましいが、政治的には最も実行しにくい。なぜなら、政治的に敏感である農産品の問題を別にしても、繊維などの労働集約製品において日本の業界が反対し、逆に中国においては競争力を持たない技術集約産業が反対するからである。
こうした一部の国内産業の反対に加え、歴史認識の問題やそれに由来する両国の国民の相互不信も、日中FTAの妨げになっていることも事実であろう。しかし、ヨーロッパでは、20世紀前半に2度にわたって世界大戦を戦ったフランスとドイツが、まさに経済統合を通じて過去の歴史を乗り越えようとしている。こうした発想の転換と政治のリーダーシップが日中両国にも求められている。
日本と中国は2カ国で東アジアのGDPの8割を占める大国である。日中両国の間にFTAが先行して締結されれば、他のアジアの国々も乗り遅れまいと積極的に加わり、地域統合が一気に加速するだろう。


