グローバル化と少子高齢化の人口減少時代を迎え、将来とも国民・消費者に食料を安定的に供給できる"健全な農業"を実現するためには、消費者負担型農政を改め、価格を引き下げて対象農家を限定した直接支払いによる農業の構造改革を実施すべきである。
消費者負担型農政による農業衰退と食料自給力低下
過保護農政と言われながら、これまで高い関税に裏付けられた高い農産物価格で農業を保護してきた。それでも日本農業の衰退に歯止めがかからない。1960年から今日まで、GDPに占める農業の割合は9%から1%に減少する一方、65歳以上の高齢農業者の比率は1割から6割へ上昇した。フランスでは54歳未満の農業者が6割以上である。
農工間の所得格差を是正することを目的とした1961年の旧農業基本法は、規模拡大・生産性向上によるコストダウンによって農業構造を改革し、農業所得向上を目指した。価格が上がらなくても、コストが下がれば所得は上がる。消費者家計を圧迫する農産物価格の引上げは避けるべきであるという考えが、1900年に農商務省に入った柳田國男(後に民俗学者)から基本法を作った小倉武一(後に政府税制調査会会長)まで農政担当者に受け継がれていた。
しかし、その後の農政は農家所得向上のため米価を重点的に引き上げた。食生活の洋風化に加え、米価が上がったので、1人1年当たりの米消費量は62年118キログラムから半分の62キログラムまで減少した。逆に農家は収益の高い米を多く生産するようになり、米は過剰となった。このため36年も米の生産調整を実施している。生産を制限して価格を維持しようとしたのである。これまで生産調整に6兆円以上、それでも天候等でできてしまった過剰米処理に3兆円もの税金を投入した。
農林水産省の予算の太宗は公共予算である。農地の整備は私的な投資だが、コストダウンを通じた農産物価格の低下によりその効果が投資した農家ではなく消費者に帰属することが、これを農家負担わずか15%程度の公共事業で行う根拠だった。その一方で農産物価格を下げないための生産調整に助成するという矛盾した農政を展開してきた。
農業資源は収益の高い米から他の作物に向かわず、穀物の自給率は1960年の82%から28%に、食料自給率は79%から40%に低下した。(フランスでは99%から132%に上昇した。)食料の6割を海外に依存しているのである。約1400万トンの米の潜在生産力がある中で、約500万トン相当の生産調整(削減)を実施する一方、約600万トンにも及ぶ小麦を毎年輸入している。
しかも米が余っているだけなのに農地も余っているという認識が定着し、国民に食料を供給するために不可欠な農地資源が宅地等に転用されていくのに誰も危機感を持たなかった。農地改革で小作人に解放した193万ヘクタールを上回る240万ヘクタールがこの40年間で消滅してしまった。
農産物一単位のコストは面積当たりのコストを面積当たりの収穫量(単収)で割ったものだから、品種改良等による単収の向上は農産物のコストを低下させる。しかし、生産調整の強化につながるので米の単収向上への取組みは行なわれなかった。また、高米価のもとではコストの高い農家も米を買うより作るほうが安上がりとなるため、零細農家が滞留し農地は主業農家に集積せず、規模は拡大しなかった。こうして構造改革は進まず国際競争力は低下した。1953年まで国際価格より低かった米も、今では778%という信じられないほどの高い関税で保護されている。
米価引上げと兼業化(農外所得)によって農家は豊かになった。1965年以降農家所得は勤労者世帯の所得を上回るようになる。なかでも兼業比率の高い零細稲作副業農家の所得は801万円で勤労者世帯の646万円を上回る。他方で農業依存度の高い稲作主業農家の所得は642万円である。にもかかわらず、零細農家=貧農という戦前からのイメージが定着し、農業に専念しようとする大規模な主業農家を育成しようとする政策は貧農切り捨てと批判された。稲作では主業農家の割合は7%にすぎない。
1942年の食糧管理法は貧しい国民・消費者にも食料を安く公平に供給するための立法だったのに、高度経済成長後の農政はそれを米価引上げに使ったのである。しかし、こうして生まれた消費者負担型農政は食料自給率と国際競争力の低下、農業の衰退という大きな副作用を生じてしまった。
WTO交渉などのグローバル化が求める課題
アメリカは1960年代に関税や価格による保護から財政による保護(農家への補助金・直接支払い)に転換した。EUも、1992年以降穀物などの価格を大幅に引き下げ、農家に対する直接支払いによって補うという改革を行った。今ではアメリカ産小麦に関税ゼロでも対抗できるまでになっている。去る11月にも、EUは40年間手をつけられなかった砂糖の支持価格を36%引き下げ、直接支払いに転換した。関税で維持される高い農産物価格による消費者負担で農業を保護するという農政を続けている日本のみが世界から取り残され、関税引き下げに抵抗せざるを得ない。
WTO交渉では、2003年8月アメリカ、EUが一定以上の関税は認めないという上限関税率に合意し、今では主要国のほとんどが100%程度の上限関税率に合意している。また、高い関税の品目には高い削減率を課すという方式が合意されている。高関税品目が多い日本はできる限り多くの品目についてこの例外扱いを求めている。しかし、ウルグァイ・ラウンド交渉で米について関税化の例外を得る代償として、関税化すれば消費量の5%ですむ低税率の関税割当数量(ミニマム・アクセス)が8%となったように、例外を要求すれば必ず代償として輸入義務的なミニマム・アクセスの拡大が求められる。上限関税率にも関税引下げにも例外を求めれば、二重の代償が必要となろう。
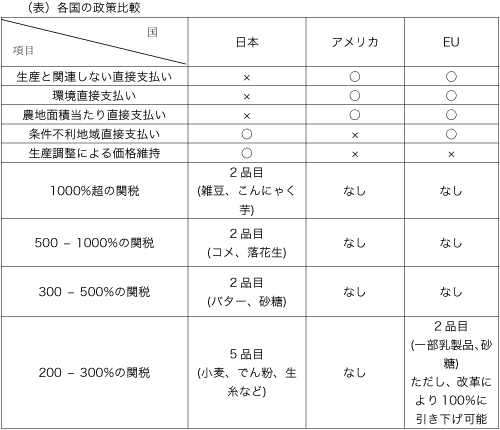
人口減少による需要低下と農業の未来
1人当たりの米消費は40年間で半分になった。人口が高齢化すると、さらに食べる量も減ってしまう。もし、2050年に1人当たりの米消費が現在の半分になり、人口が1億人になったとすると、米の総消費量は現在の900万トンから350万トンへ大幅に減る。2050年に今の米価水準を維持しようとすると、単収もわずかながら増加するので、270万ヘクタールの水田の8割にあたる220万ヘクタールの生産調整を行い、稲作面積を現在の3分の1以下の50万ヘクタール程度まで縮減しなければならない。大幅な農業の縮小である。
食料生産に不可欠の農地を潰し、農業を縮小しながら食料安全保障論を唱えるのは矛盾している。戦前米価を維持しようとした農林省の減反政策案に反対したのは食料自給を唱える陸軍省だった。大正時代米騒動を起こしたのも、戦後タケノコ生活を送ったのも、主婦・消費者であって農業者ではない。本来食料安全保障は消費者の主張である。消費者に対し、食料の供給を制限し、高い価格により家計を圧迫させる政策が食料安全保障と相容れるはずがない。
長年JA農協と共同歩調を取ってきた生協も、今では財政の支給対象となる担い手は一定の規模にあり生産性の向上に取り組んでいる農業者や農業法人等とするべきとし、高関税の削減による内外価格差の縮小を求めている。国民・消費者にとって望ましい"農業の担い手"は、低い関税の下でも、つまり安い農産物価格の下でも必要とする食料を供給してくれる農業者である。"国の本なるが故に農業を貴しとするのである。国の本たらざる農業は一顧の価値もない。"という戦前の偉大な農本主義者、石黒忠篤(農林次官、2度の農林大臣)の言葉を噛みしめる必要があろう。国民と消費者のために有益であってこそ"国の本"たる農業・農政といえるのだ。
米の需要は食用の米だけではない。米価を下げれば、米粉等輸入調製品、飼料用米、生分解性プラスティックやエタノール原料用等の新規需要、さらには人口の増加する海外の食用需要も取り込むことが可能となり、人口が減少して国内の主食用需要が減少しても米の需要は維持できる。水田はフルに活用され、40%に下がった食料自給率は向上する。いざ海外から食料が途絶しても十分国内生産で必要なカロリーが賄えるよう農地の維持が可能となる。
穀物価格を下げて直接支払いに転換したEUは、アメリカから輸入していた飼料用穀物を域内産穀物で代替した。価格を3割下げた92年からわずか3年で飼料用の穀物消費は21%増加、穀物消費全体も14%も増えた。現在我が国が飼料用に輸入している穀物は1600万トンにも及ぶ。価格を下げることは、人口減少時代における国内農業の市場の拡大、ひいては消費者にとっても食料安全保障に不可欠な農地・農業資源の維持にもつながる。日本とは逆に世界の人口は2000年の61億人から2050年には93億人に増加すると予想されている。食料危機の起こる確率は高まっていくのである。
国民と消費者のための農政改革を望む
関税引下げに対応するためには、EUのように直接支払いを導入し国内価格を引き下げればよい。しかし、内外価格差を残したままでのミニマム・アクセスの拡大は国内生産の縮小、食料自給率の低下をもたらす。だからミニマム・アクセスの拡大に耐えかねて1999年に米の関税化に踏み切ったのではないか。今では食料自給率の向上は閣議決定されている。WTO交渉で関税引下げとミニマム・アクセス拡大のいずれかを求められる場合は、迷わず関税引下げを選び直接支払いを導入すべきだ。関税の引下げは交渉の負けを意味しない。それによって必要となる価格引下げと主業農家に対する直接支払いは農業の構造改革と再生をもたらす。
稲作副業農家の米販売額104万円のうち農業所得はわずか10万円、これは1万5000円の米価が1400円低下しただけで消える。生産調整という価格維持カルテルを段階的に廃止し、米価を需給均衡価格9500円程度まで下げれば副業農家は耕作を中止する。一方、一定規模以上の主業農家に耕作面積に応じた直接支払いを交付し、地代支払能力を補強すれば、農地は主業農家に集まる。3ヘクタール未満層の農地の8割が流動化すれば3ヘクタールの農家規模は15ヘクタール以上に拡大しコストは大きく下がる。また、週末以外も農業に専念できる主業農家は農薬・化学肥料の投入を減らすので、環境にやさしい農業を実現できる。この原理は他の農産物についても同じである。
昨年の農政改革が、フランスが長年行なってきたように政策対象を主業農家等に限定したことは評価できる。しかし、麦、大豆などの畑作物についてWTO上削減を求められる直接支払いの一部を削減しなくても良い直接支払いに変更したのみで、米、麦,大豆、乳製品等どの農産物についても、EUのように関税や価格の引下げに対応するための直接支払いは実施されない。対象農家の限定という1つの要素は導入したが、価格引下げのための直接支払いというもう1つの要素は実現していない。消費者負担型農政という基本的性格に変化は見られないのである。だから、WTO交渉に対応できない。
日本の農業保護は消費者負担が5兆円、納税者負担が0.5兆円である。5兆円は消費税の2%に相当する。現在消費者は消費税の2%に相当する高い農産物価格という税金を払っているのである。直接支払いは全額農家所得となるのに対し、価格支持のうち農薬・肥料等へ支払ったあと農家の所得となるのは5分の1である。全ての農産物の国内価格を国際価格まで引き下げても、5兆円の5分の1に相当する1兆円の直接支払いで現在と同じ農家所得を維持できる。3兆円もある農業予算を見直して、これから直接支払いの財源を捻出すれば、5兆円にのぼる国民負担は消えてなくなる。農政の転換は国民にも大きな利益を生む。
農業を保護するかどうかが問題ではない。関税・価格による保護か直接支払いか、いずれの政策を採るかが問題なのである。グローバル化と人口減少時代の中では、前者の対応は農業の衰亡、国民への食料供給のさらなる脆弱化を招く。これまでどおりの農政を続け座して農業の衰亡を待つよりは、直接支払いによる構造改革に賭けてみてはどうだろうか。
2006年『公明』4月号に掲載


