わが国では1990年代半ば以降、消費者物価の下落が続き、デフレが進行している。先進国でのデフレの発生事例は極めて限られるが、有名なのは30年代の大恐慌期における米国だ。このときは消費者物価が年約7%の速度で下落し、3年間で20%の下落となった。これに対し、わが国の下落率は年1%前後、激しい時期でもせいぜい2%であり、比較的緩やかといえる。
大恐慌期との違いは、需給ギャップの大きさの違いを反映している。しかし日本のデフレの緩やかさはそれだけでは説明がつかない。90年代半ば以降、需給ギャップ悪化に対する消費者物価上昇率の反応の度合いは顕著に低下している。つまり需給ギャップの拡大幅との対比でもデフレ率は小さい。仮に反応の度合いが80年代並みであったとすれば、デフレ率は3%に達していたと考えられる。
デフレが緩やかであること自体は悪いことではないが、毎年のデフレ率が小さいために物価が底を打つまでに要する時間が長くなり、15年以上の長期にわたるデフレを生んでいるとの見方もできる。
◆◆◆
では、日本のデフレ率はなぜ低いのか。その理由を巡り様々な解説がされているが、日本の消費者物価が正確に計測されていないため、デフレ率が低くみえているにすぎないとの指摘も聞かれる。とりわけ海外の研究者や実務家の間でそうした疑念が根強い。
物価の計測方法を変えると数字はどの程度変わるのか。物価を経済の「体温」とすれば、消費者物価統計は「体温計」である。1つの体温計が頼りにならないとすれば、別の体温計を試してみて数値の違いを確認する必要がある。
筆者を含む研究チームは、体温計を取り換えて日本の体温を測り直す実験をした。具体的には、日本のスーパー約200店舗で販売されている全商品(食品や雑貨など約20万点の商品)について、2000~10年の日次価格データ(POSデータ)を、日経デジタルメディアの協力を得て収集した。そのうえでコンピューター上にある商品群の価格を日本の全価格と見立て、そこにバーチャルな価格調査員を派遣し、価格収集をさせるというシミュレーションで消費者物価を作成した。
その際、注意を払ったのはサンプル抽出の方法だ。日本の価格の動きを正確に知りたければ全店舗の全商品の価格を調べるのが一番だが、価格の全数調査は不可能だ。一部店舗の一部商品の価格を調べることで統計を作成せざるを得ない。これは日本だけでなく先進各国に共通するが、実際にどのような方法でサンプリングをするかについては国によりかなり違いがある。
筆者らの実験ではサンプル抽出方法として、(1)わが国の消費者物価統計を作成する総務省の方式に近い方法(2)総務省の方式に似ているが、特売価格の扱い方などいくつかの点で異なる方法(3)米国の消費者物価統計の作成機関である労働統計局が採用している方法――の3種類を試した。
総務省の方法は、価格収集の対象となる商品の範囲をあらかじめ絞り込む点に特徴があり、英国など主要各国で採用されている。例えば、POSデータでみるとバターには300点を超える種類があるが、「容量が200グラムのカルトンバターで食塩不使用」という条件を課すことで、約30点の商品に絞り込む。一方、米国の方法は事前の絞り込みをせず、商品全体を対象に抽出する。バターの例でいえば300点の全種類を対象として、各商品の販売実績に応じて抽出確率を定め、それをもとにランダムに商品を選ぶ。
売れ筋のバターが事前にわかっている場合は総務省方式が望ましい。しかし何が売れ筋かはっきりしない場合や、商品の新陳代謝が激しく売れ筋商品が頻繁に変化する場合は、米国方式が優れている。
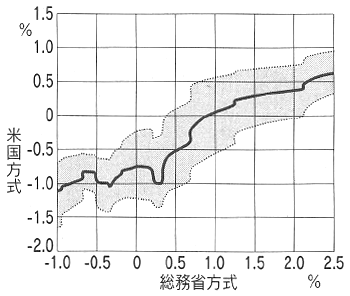
◆◆◆
実験の結果、総務省方式に近い方法でサンプル抽出した場合には、消費者物価の公表数字に近い数字が得られた。また、総務省の特売価格の扱い(1週間以内の短期間の特売を除外する)を変更してもさほど変わらなかった。しかし米国型サンプル抽出を採用した場合には、結果に大きな違いがみられた。
図の横軸は総務省方式で作成した物価指数の前年同月比を、縦軸は米国方式で作成した物価指数の前年同月比をそれぞれ示している。例えば、横軸の1%は総務省方式で前年比1%のインフレになった月を意味しており、縦軸はその月に米国方式ならばどういう数字になるかを表す。実線は中央値で、横軸1%に対応する縦軸の値は0.1%だから、総務省方式で1%のときには米国方式の中央値は0.1%ということを示す。横軸2%に対応する縦軸の値は0.4%であり、総務省方式に比べて米国方式の数字の方が低いという傾向がある。
つまり、仮に総務省が米国方式を採用していれば、消費者物価変化率の公表値は低かった可能性がある。ただし総務省方式と米国方式の差は1%程度なので、米国方式が採用されていても、大恐慌期の米国のような激しいデフレを表す数字にはならない。
米国方式は対象商品を確率的に抽出するので、商品は抽出のたびに異なり得る。それに伴うばらつきがどの程度かを示すため、図では80%信頼区間をシャドーで表した。例えば、横軸の1%に対応するシャドーはマイナス0.5%からプラス0.5%だ。これは、総務省方式で1%の数字が得られたときに米国方式の数字は80%の確率でこの範囲に収まることを示す。
この結果は政策運営にどのような意味合いを持つのだろうか。日銀は消費者物価上昇率1%を金融政策運営のめど(ゴール)としている。総務省方式で1%のインフレのときに米国方式の中央値はプラスなので、1%の「のりしろ」を確保しておけば安全という日銀の主張と合致する。ただし、これはあくまで「平均」の話だ。信頼区間をみるとマイナス区間が含まれており、米国方式ではデフレ脱却がまだ達成されていない可能性があることを示している。
信頼区間の下限がゼロを上回るのは総務省方式の数字が2.1%に達したときである。つまり、どの体温計で測ってもデフレ脱却を果たせたと自信を持って断言するには、そこまで待つ必要がある。
また財政面では、年金支給額がデフレにスライドしていないため、00年度以降に累計で7.5兆円の年金の過払いが発生しているとの指摘がある。仮に米国方式が採用されていたとすれば、デフレ率は大きく、過払いの規模はさらに膨らんだはずだ。
◆◆◆
精度の高い「体温計」の整備は金融・財政政策運営に不可欠だが、体温計により計測結果は大きく異なる。こうした現状を受け、物価指数の作成にデジタルデータを活用する試みが注目されている。スイスやスウェーデンなど欧州のいくつかの国では、流通業者と協力してPOSデータを収集し、それを消費者物価統計の作成に活用し始めている。POSデータは広い範囲の商品をカバーし、価格だけでなく販売量の情報も含まれるので、売れ筋商品の正確な把握などを通じ、統計精度を向上させることが期待できる。
一方、米グーグルなど内外の複数企業では、インターネットを活用して価格情報を収集し、高精度の物価指数を作成する試みが進んでいる。米国では試作段階だが、政府統計に先行して動くとの結果も得られている。これらの試みが成功すれば、政府統計のような月次ではなく日次で、しかも迅速に物価を知ることができる。こうした民間主導による物価指数構築も、精度向上につながると期待される。
2012年9月13日 日本経済新聞「経済教室」に掲載

