共著:Dale W. JORGENSON (ハーバード大学教授)
「失われた10年」といわれる1990年代、日本は情報技術(IT)で米国に遅れをとったとされるが、日米の統計を整合すると成長率に対するITの寄与は同等だ。成長率の差は供給効率化に見合う需要と労働投入の不足(雇用の減少)が主因であり、今後の日本経済にとっても課題だ。
米経済と何が違っていたか
90年代の日本の平均経済成長は1.4%と、80年代の4.1%と比べて大きく落ち込んだ。最近の動きを見ても今年1-3月期は実質ゼロ成長にとどまり、経済の足取りは依然として重い。このように低迷する日本経済と好対照に、米国経済は90年代に隆盛を見せた。特に90年代後半にかけて加速した経済成長は、情報化投資による生産性の伸びに支えられ、ニューエコノミーと呼ばれている。
世界的なIT産業の急激な落ち込みを受け、2000年に入って米国の成長率は低下したが、米国労働統計局による生産性の動向は依然、力強い。ITバブル崩壊でニューエコノミーへの懐疑的見方も広がったが、少なくともIT革命による生産性の上昇という側面では状況は変わっていない。
ITの技術革新のスピードを象徴するのが、18カ月で半導体の集積度が2倍になるという「ムーアの法則」である。コンピューターや通信機器はその技術革新に支えられて圧倒的な速度で高性能化が進んでいる。米国にみられる力強い生産性の上昇は、このような技術進歩と企業部門における旺盛なIT投資に支えられている。
その技術革新は、90年代後半にかけて加速した。半導体技術国際ロードマップ(ITRS)によると、集積度のスピードが95年以前は24カ月で2倍のペースであったのが18カ月で2倍のペースに上方修正された。インターネットの急激な普及が始まったのも90年代半ばである。
筆者らは、この90年代半ばを境に日米の生産性がどのように変化したかを分析した。米国における労働生産性について73-95年と95-2000年の平均年率を比べると、0.74%伸び率が高まっている。
労働生産性の動向は、労働者1人あたりの資本ストックの量(資本の深化)と全要素生産性(TFP=資本と労働の貢献分以外)の伸びに分解できる。資本の深化のうちIT資本(コンピューター、ソフトウエア、通信機器に関する資本ストック)は0.50%分の上昇寄与をもつ。これとTFPのうちIT部分である0.24%を足すと0.74%となり米国の90年代後半にかけての労働生産性の伸びはすべてがITで説明できる。
それでは日本においてはどうであろうか? ムーアの法則にみられるITの技術革新は日本においても見られるはずだ。そうであれば日本でも米国のようなニューエコノミー現象がみられてもおかしくなかった。しかし経済協力開発機構(OECD)のリポートによると、日本は米国と比べITの導入が遅れ、その影響も限られたものになっているといわれてきた。
OECDのリポートは各国の公式統計をベースにしたもので、統計の整合化は行われていない。そこで筆者らはITが経済成長に及ぼす影響の日米比較を行うため、まず比較可能なデータベースを開発した。日米のGDP統計はそれぞれ93SNA(93年に国連が勧告した国民経済計算体系)に従っているが、いくつかの概念の違いが存在する。中でもITに関する分析を行う上で重要なのは以下の2点である。
日本が過小にIT投資評価
まず、ソフトウエアの定義が異なる。日本のGDPでは受注ソフトのみを設備投資として取り扱っている。米国のGDPは受注ソフトのほかパッケージソフトや自社開発ソフトも設備投資として取り扱っているため、日本のGDP統計における設備投資は少なく見積もられている。筆者らの推計では、これらのソフトの投資額は2000年で約4兆円で、GDPの1%近くが過小推計されていることとなる。
また、コンピューターなどのIT投資にかかる価格の問題も大きい。IT品目は技術革新が激しくモデルチェンジが頻繁に行われるため、パソコンの卸売物価指数や消費者物価指数に品質変化分を回帰分析によって算出する指数(ヘドニック指数)が用いられる。日米とも同様の方法で推計しているが、同指数の結果は回帰モデルの内容によって大きな影響を受けることが分かっている。
日米のコンピューターに関する公式統計を比較すると95年から2000年にかけての価格低下率は米国の方が約2倍の速度で進んでいる。これは統計方法の違いが影響していると考えられる。価格の下落率が少ないと実質投資の伸び率が小さくなり、ITの寄与度が過小評価される。
筆者らはこれらの統計の違いを補正して日米の経済成長要因の比較を行った(グラフ参照)。ここでは労働生産性ではなく、労働投入の動向も比較するため、経済成長率の分解を行う。まずIT資本の成長に対する寄与度は90年代後半については約1%とほぼ同程度だ。つまり、日本は米国と比べてIT投資が遅れているという従来の見方は、統計の違いによるものである。
また、TFPも米国と同様、日本でも90年代後半にかけ伸び率の上昇がみられる。このように90年代の日米経済はマクロの成長率は大きな違いがあるが、IT資本による資本深化とTFPの伸びでは大きな差は見当たらない。
日米の格差を説明するのはIT以外の資本ストックと労働投入の状況である。特に労働投入は90年代を通してマイナスの寄与を示している。これはIT投資による供給構造の効率化は進んだが、それに対する需要が伸びなかったことに起因すると考えられる。
企業におけるリストラのように「縮小均衡」で効率化を進めるのではなく、新商品開発などのイノベーションによって付加価値増大による生産性向上を達成することが重要である。日本では今年から研究開発税制が拡充されたが、90年代を通じてこうした企業のイノベーションを推進する政策が不十分であったことの影響も考えられる。
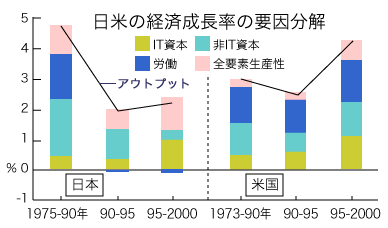
需要の喚起と少子化対策を
90年代後半の日本の成長率は米統計と整合性を行うと、年率約2.1%となるが、その約半分はIT投資の上昇分によって説明できる。つまり、日本における生産性上昇速度の加速はITにおける技術革新に支えられているところが大きい。
ただし、この生産性上昇はIT分野の技術革新への依存が大きく、その持続可能性が大きな焦点となる。同分野の技術革新を先導する半導体集積回路については各種要素技術の開発が難しくなってきており、95年以前の速度にペースダウンするという見方もある。通信技術についても通信帯域の拡大は幾何級数的に進むが、一方でコンテンツ(情報の内容)の開発がネックになるという指摘もある。IT分野の技術革新が減速すると、マクロ経済の生産性低下を通じて長期的な成長率の下支え効果が薄れる。
また、今後の日本の成長率を考える際に重要なのが労働投入の状況である。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、日本の労働人口は2005年の6870万人をピークに減少し2025年には6260万人となる。年率で約0.5%の人口減となり、成長率を約0.3%押し下げる。ちなみに米国において米商務省センサス局の推計をベースに推計を行うと、労働投入は年率約1%のGDP押し上げ効果を示す。
日本の労働人口の減少は50歳代半ばの「団塊の世代」がここ10-20年で労働人口からはずれるという特殊要因もあるが、長期的には少子化問題が大きい。労働供給の拡大を図るには、女性の社会進出と少子化対策という一見相反する課題に対して、総合的に対応していくことが必要だ。また、労働供給の構造的縮小を補うには生産性の向上が必要だが、そのためには供給構造の強化と同時に需要を喚起するイノベーションを促進していくことが重要である。
2003年7月3日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


