社外取締役の積極的な登用は日本の企業統治における最も重要な改革課題の1つだ。東証1部上場企業1445社(非金融)では、取締役全体に占める独立社外取締役(会社法定義の社外取締役から銀行出身者、15%以上の株式を保有する法人出身者を除く)の割合は、2010年度末に9.6%に達した。しかし米国で70%程度、英国で50%以上、韓国でも30%を超えることを考えれば、はるかに低い。
このため会社法改正案の中心論点の1つとして、社外取締役の義務化が提案されている。この点の当否を冷静に議論するには、取締役会構成の決定と社外取締役の導入効果を正確に理解することが不可欠であろう。本稿では、経済産業研究所の小川亮氏と試みた最近の分析結果を報告し、議論の素材を提供したい。
◆◆◆
義務化を推進する側の考え方はこうだ。上場企業では、常に経営者が株主の利害を十分に実現しないという利益相反の可能性がある。社外取締役は経営監視に対し、内部昇進の取締役と異なる知識とインセンティブ(誘因)を持つので、企業価値を引き上げられる。日本企業の社外取締役が少ないのは、事実上取締役の選任権を持つ経営者が監視を嫌うためだ。例えば昨年不祥事で注目された大王製紙には社外取締役がいなかった。
これに対し、社外取締役の監視機能そのものに懐疑的な見方から、義務化無用論も聞かれる。経営者は自らに友好的な人材を選任できるので、実質的効果を持たない。例えばオリンパス事件では、粉飾決算の処理に関連する買収決定の時点で3人の社外取締役が選任されていたが、有効な経営監視を果たさなかった。
3番目の見方は、義務化有害論とも呼ぶべきものだ。企業は事業特性に従って最適な取締役会構成を選択しているので、社外取締役の登用が常に企業価値を引き上げるわけではない。実際トヨタ自動車やキヤノンは、企業の意志決定には「現場の知識」が必要だとして、あえて社外取締役を登用していない。日本企業がすべて同様の行動をとっているのであれば、社外取締役の選任は企業の自由な選択に任せておくのが望ましい。
では、これら3つの見方を踏まえたうえで、日本の取締役会がどのように構成されているのかみていこう。
筆者らは05~10年の東証1部上場企業を対象に、取締役会構成の決定要因とその効果を分析した。決定要因については(1)助言を必要とする事業の複雑性(2)企業が直面する利益相反問題の深刻度(監視の必要性)(3)助言・監視に必要な情報獲得の困難さ(4)経営者の交渉力――の4点から分析した。各要因をとらえるために利用した変数は表の通りで、推計結果を符号で示した。正(負)の符号は、その変数の上昇が社外取締役を増加(減少)させることを意味する。
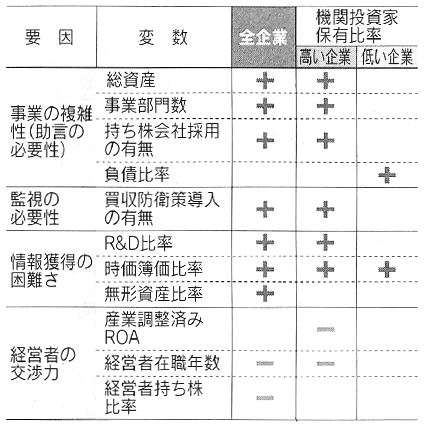
◆◆◆
まず、平均的に日本企業の取締役会の構成は、多角化、持ち株会社の進展といった事業の複雑性、買収防衛策の乱用防止といった監視の必要性、経営者の交渉力で決定される。企業が事業特性に応じて取締役会を選択する傾向が強まっていることは、前述の義務化を巡る3番目の見方とある程度まで整合的だ。
しかし注目すべきは、研究開発(R&D)比率が高い、無形資産の役割が大きいなど特殊な知識の重要性が高く、外部者による情報獲得の困難な企業ほど、むしろ社外取締役比率が高いことだ。本来、そうした企業では社外取締役の必要性は低いはずだ。実際、情報獲得の困難な企業群では高い社外取締役比率には総資産利益率(ROA)を向上させる効果がないか、場合によっては負の効果を持つ。この結果は、取締役会構成の選択にバイアス(ゆがみ)がある可能性を示唆する。
一方、外部者による情報獲得が容易な企業群だけでみると、高い社外取締役比率はROAを向上させる効果を明確に確認できる。ROAに影響を与える他の要因を考慮しても、また人数、新規選任に置き換えても、この結果は頑強だ。つまり情報獲得の容易な企業群では、社外取締役が選任されれば、明確な効果を期待できるのに、選任されていない。
また、近年日本企業の所有構造は、法人・銀行中心から内外の機関投資家中心に劇的に変化した。この変化は企業間で大きな格差を伴うため、所有構造の差も考慮した。
機関投資家保有率の高い企業群(サンプルの上位から25%以上)では、社外取締役比率が高い(平均11.5%)。こうした資本市場の強い圧力に直面する企業群では、事業構造の特性や、経営者の経営能力に対応して取締役会構成を選択している程度が高い。特に、取締役会の構成は、事業の複雑性や経営監視の必要性により規定される傾向が強い。また、業績が相対的に悪化した際に、社外取締役を登用する確立が高く、経営者の在職年数が長いと登用する確立が低くなる。
これに対し、機関投資家保有比率の低い企業群(下位から25%以下)では、社外取締役比率が低い(6.6%)。事業の複雑性や経営監視の必要性などの要因が取締役の構成に作用する程度も低い。また業績と社外取締役の選任の関係が乏しく、経営者の保有比率の高い企業で社外取締役の選任が遅れる。この意味で、資本市場の圧力の低い企業群では、社外取締役比率は過小である可能性が高い。この企業群では、経営者の私的利害を強調する義務化推進論者の見方は確実に当てはまる。
以上の実証結果は、社外取締役の促進措置の必要性を強く訴えている。事業特性からみて情報獲得が容易な企業群には、資本市場の圧力の低い企業を中心に、社外取締役の選任が企業価値を引き上げる可能性が高いのに、経営者の私的利益のために選任が遅れる企業が存在する。こうした企業では、市場に委ねておくだけでは改善は非常に難しく、外部から選任を促進する何らかの措置が不可欠だ。
慶応義塾大学の齋藤卓爾准教授、九州大学の内田交謹准教授の研究もほぼ同様の結論を得ている。実証分析は、社外取締役を促進する制度措置を支持している。
◆◆◆
ただ同時に、日本企業が近年ある程度まで企業特性に従って取締役会構成を選択し、また社外取締役導入の効果が企業の特性により異なる点も重要な実証結果だ。これは、すべての企業に一律に社外取締役の選任を課する義務化がベネフィット(便益)ばかりでなく、コストを伴うことを意味する。特に情報獲得の困難な企業群では、義務化は企業価値に負の効果を持つ可能性が高い。従って制度設計としては、すべての企業に対する義務化よりも、企業に選択の余地を残すことが望ましい。
会社法改正の中間試案に即していえば、義務化案はさらに慎重な検討を続け、企業が任意に選択可能な監査・監督委員会設置会社制度を推進することが期待される。補完的措置として、改革の目的が上場企業の少数株主保護にあるとすれば、東証の上場規則に社外取締役を望ましい制度と位置づけ、採用しない場合には企業側が説明責任を負う英国の方式が考慮に値する。
また、一部の市場関係者が提案するように、公的年金が運用委託の基準に規定する方法もある。「社外取締役を選任する企業」であることを、株式運用時の投資対象銘柄の1つの要件とすれば、ほぼ同様の効果が期待できよう。
2012年6月25日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


