生鮮食品を除く消費者物価は上昇に転じたが、賃金コストの大幅な低下を背景に、国内物価の下落傾向は変わらない。購買力平価を勘案すると、日米間の金利差縮小に伴う円高のリスクが高い。また、米国経済の減速、中国のインフレ加速、欧州の住宅価格下落懸念など、景気のリスク要因が増しており、金融政策のかじ取りは難しさを増している。
日銀は2006年3月に量的緩和政策、7月にはゼロ金利政策をそれぞれ解除し、07年2月には無担保コール翌日物金利を0.5%前後に促す政策変更を行った。しかし当センターは昨年3月の金融研究報告で、国内総生産(GDP)デフレーターの動向やGDPギャップの推計結果などからは日本経済がデフレから完全に脱却できたかどうかは判然としないことを指摘し、日銀の利上げ政策に疑問を呈した。
需給依然緩く国内物価安定
原油に加え輸入食料など一次産品価格の上昇で、生鮮食品を除く消費者物価(コアCPI)は上昇に転じ、国内物価への波及も徐々に見られ始めたが、食料とエネルギーを除いた消費者物価(コアコアCPI)や、付加価値の物価であるGDPデフレーターはマイナスが続いている(図1)。原油などの輸入物価の上昇にもかかわらず国内物価安定や、マイナスのGDPデフレーターが続くのはなぜか。
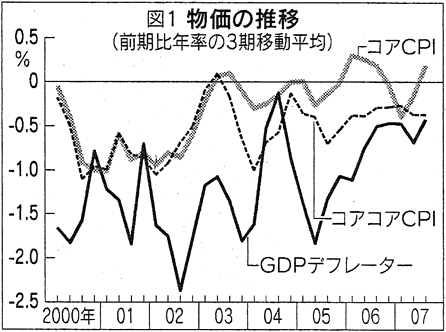
マクロ生産関数を用いて推計した潜在成長率は、少子高齢化に伴う労働年齢人口の減少により、03年ごろの年1.3%程度から07年後半には1.0%程度まで徐々に低下した。なお女性の労働参加率は上昇しているが、1人当たりの平均労働時間は減少傾向にあるため、全体として潜在成長率を押し上げる要因にはなっていない。またGDPデフレーターを説明する物価関数を推計し、これを用いてGDPギャップを推計すると、足元のギャップはインフレ率を加速も減速もしないゼロ近傍にある(図2)。このため1%前後の成長が達成できても日本経済の需給は引き締まらず、GDPデフレーターの低下傾向は止まらないと見込まれる。
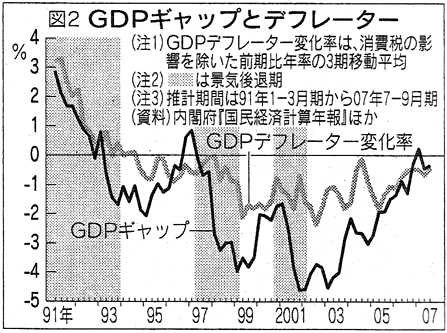
今回の原油価格上昇局面を第一次石油危機のあった70年代前半と比較してみよう。産業連関表で75年の国内企業物価の理論値(70年対比)を推計すると45%の上昇(実績は53%上昇)となったが、このうち原油価格上昇の国内物価押し上げ効果は4.5ポイント、輸入品全体でも9ポイントであった。残りの36ポイントの上昇幅のうち、賃金コストが33ポイント、利潤を含む資本コストが4ポイント、それぞれ物価を押し上げていた(図3)。
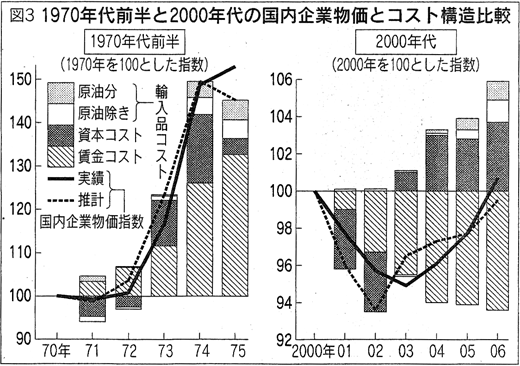
これに対し、2000年代では、70年代に比べて物価の変動はかなり小さく、06年の国内企業物価の推計値(2000年対比)はマイナス0.5%(実質は0.7%上昇)とほぼ横ばいで、このうち原油価格上昇の効果は1.0ポイント、輸入品全体でも2.2ポイントの寄与だった。この背景には、企業収益の回復で資本コストがプラス3.7ポイント上昇に寄与したものの、賃金コストが6.4ポイントも低下したことがある。
こうしたコスト構造が今後短期間で変化するとは考えにくく、国内要因によるインフレが進む可能性はきわめて低いとみられる。輸入価格の上昇で一般物価が上昇してもGDPデフレーターが低下している場合は、付加価値である雇用者報酬や営業余剰の単価が低下していることを意味し、景気にはマイナスに働く。07年6月の日銀の「通貨及び金融の調節に関する報告書」によると、同年2月の利上げの際、消費者物価について「より長い目でみると、マクロ的な需給ギャップが需要超過方向で推移していく中、プラス基調を続けていく」との見方を政策委員が共有したが、この見通しは甘かったといわざるをえない。
サブプライムの影響かなり深刻
輸入物価上昇要因を除いた国内物価についてデフレを払拭できない中で、これまで経済の好調が続いたのは、20年来の安値にあった円相場と、好調な海外経済による部分が大きい。だが、これら要因も今後その下支え効果がはげ落ちていくだろう。
サブプライムローン(信用力の低い個人向け住宅融資)問題の米国経済に与える影響は、かなり大きい。主要都市部の住宅価格は、過去数年、特にロサンゼルス、マイアミ、ニューヨークなどでの上昇が激しく、今後これらの地域での地価下落の影響が懸念される。特に証券化商品の元利金に広範な保証を行っていた米国の金融保証会社(モノライン)は資本規模が小さく、サブプライム関連商品の損失が発生すると、大幅な格下げや破綻のリスクがあり、それが証券価格の一段の低下を招くリスクがあるため、注視する必要がある。
欧州もサブプライム問題が金融面・実体面双方で経済に負の影響を与えている。特に英政府が英銀ノーザン・ロックの再建を民間に委ねることを断念、一時国有化したことは、住宅価格動向に対する懸念の強さを印象づけた。欧州でも住宅価格高騰が顕著で、07年上半期の住宅価格指数(2000年=100)は、ユーロ圏全体で157(スペイン235、フランス209、ドイツ95)、英国は228に達し、今後住宅市況の悪化と景気の減速が懸念される。
このような欧米経済の後退は、円の実質実効為替レートの上昇につながる恐れがある。今回当センターが行った試算によれば、この1年間のわが国の利上げと米国の相次ぐ利下げで日米間の実質金利差は急速に縮小し、これが4%程度の円高をもたらしている。
相対的購買力平価でみても現在の円は過小評価されており、今後米ドルに対して円高基調が続く可能性が高い(図4)。1ドル=100円を突破する可能性も十分にあり得るだろう。また、欧州の景気減速もユーロ安に働くだろう。
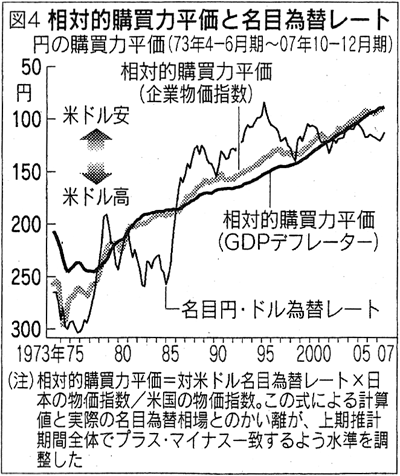
資本コスト上昇 海外の投資減少
中国では07年以降物価の上昇が続いており、08年1月の消費者物価は前年比で7.1%の上昇となった。中国の公式の消費者物価は実態を過小評価している可能性が高く、実際にはそれ以上のインフレが進んでいる懸念がある。
株価や不動産価格の高騰も懸念材料である。インフレ率が上昇すれば、それに伴う低所得層の預金の目減りなどで社会不安が悪化する可能性が高く、今後、人民銀行による一層の金融引き締めや、行政的な手法による強力な総需要抑制が必要となる可能性が高い。
中国のインフレ進行は、対人民元でみた日本円を実質的に切り下げることになり、その意味では日本の対中輸出競争力を高める。だが、引き締め政策に伴う反動的な不況に陥るリスクのインパクトの方が大きいだろう。現在は、日本に限らず米国や欧州も中国経済の高成長に支えられている。中国経済の動向次第では、今後世界的な景気後退局面に入っていく可能性も十分にありうる。
海外経済の減速は純輸出を押し下げることから、外需による下支え効果も今後期待しづらくなる。また、企業は輸入コストの上昇を販売価格に転嫁できず、それを雇用者報酬や営業利益の圧縮で補わざるをえない。その結果、GDPデフレーターベースで見た物価の低迷は継続するだろう。さらに内外金利差の縮小による一段の円高進行というリスクもあり、今後景気が悪化する可能性は十分にあると思われる。
金融市場の構造的問題として、日本企業の資本コストが最近上昇している可能性も指摘したい。外国人投資家は、日本の構造改革の後退に対する失望感から、日本への投資を控え始めている。外資系投資ファンドによるブルドックソース買収に対する裁判所の判決はポイズンピル(毒薬条項)の容認自体の判断は別にしても、判決文のトーンが株式市場の存在自体を否定しかねない内容であったことが、海外投資家に衝撃を与えた。
香港系投資ファンドによるJパワー株の買い増しに関する経産省判断の保留、経産省高官による株式投機一般に対する批判発言といった企業買収に対する日本社会の反感も、外国人投資家が日本市場から離れていく原因となっている。このような中で、足元のPER(株価収益率)は過去に比べても非常に低い水準(17.8倍)にあり、配当利回り(1.70%)は国債利回り(1.40%)を上回る状況が続いているため、企業の資本コストが高まっている。
今年3月下旬には、日銀の福井俊彦総裁が退任し、新総裁が着任する予定である。もっとも、日銀の切ることのできるカードはほとんどなく、非常に厳しい金融政策のかじ取りを強いられることになるだろう。
2008年2月27日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


