| 開催日 | 2015年10月23日 |
|---|---|
| スピーカー | 高橋 和夫 (放送大学教授) |
| モデレータ | 岡田 江平 (経済産業省貿易経済協力局通商金融・経済協力課長(併)戦略輸出室長) |
| ダウンロード/関連リンク | |
| 開催案内/講演概要 | 2015年7月にイラン・イスラム共和国がアメリカを中心とする6大国と核問題に関しての包括的な合意に達した。これはアメリカから見ればオバマ外交の大きな勝利である。イランにとっては国際社会への復帰と地域大国としての地位の確立への大きな一歩である。 さて1979年に成立した革命国家が、ようやく36年の時を経て超大国アメリカと外交上の妥協点を見出した。36年という歳月はイランという革命国家が国際政治の現実と折り合いをつけるのに要した時間であり、アメリカという覇権国家がイラン革命という地殻変動による揺らぎからバランスを取り戻すのにかけた時間でもある。 表面上の対立にもかかわらず、イランとアメリカは深い人間関係のネットワークで結ばれている。イラン・アメリカ関係の軌跡を振り返りながら、その手触りとニュアンスを伝えたい。それが、両国関係の将来を考える手助けとなるだろう。 |
議事録
イランという国
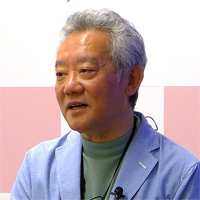 なぜ、中東のイスラムの国であるイランが核開発をしたり、米国に逆らって外交を展開したりするのか。一体、イランは何を考えてやっているのか、というお話をしたいと思います。イランという国は、地理的に大きな国で、国土面積は日本の数倍もあります。米国でいえば、おそらく東海岸からミシシッピ川辺りまでありますから、イラン人は自分たちが大国であるという意識を強烈に持っています。
なぜ、中東のイスラムの国であるイランが核開発をしたり、米国に逆らって外交を展開したりするのか。一体、イランは何を考えてやっているのか、というお話をしたいと思います。イランという国は、地理的に大きな国で、国土面積は日本の数倍もあります。米国でいえば、おそらく東海岸からミシシッピ川辺りまでありますから、イラン人は自分たちが大国であるという意識を強烈に持っています。
たとえば、イランの地図を欧州に移してみると、1国でドイツからギリシャまで届いてしまうような広さがあるわけです。大国である自分たちが国際政治で発言権を持つべきだと思うのは、イランの図体の大きさからみて、ある意味で当然といえるでしょう。
イランにとって一番重要なのは、民族という概念です。イランの地図をずっと眺めていると、何となくネコに見えてくるような気がします。ネコといえばペルシャ猫がいますが、ペルシャというのはアラブとは違うということで、それが非常に重要なのです。イランはペルシャであって、アラブではない。ですから、一方でイラン人に対して「お前らアラブ人はね...」と言うと、必ず怒ります。他方、イラン人と間違えられるのは、アラブ人にとっても侮辱です。今日の話のポイントとして、「イランはアラブではない」と覚えて帰れば、あとはもう寝てしまってもいいくらいです。
イランはかつて、もっと巨大でした。古代アケメネス朝ペルシャ帝国の時代は、パキスタンからトルコ、ギリシャ、今の地名でいうとエジプト、中央アジアまで広がる途方もない帝国を建設し、維持していたわけです。イラン人は、自分たちはその巨大なアケメネス朝ペルシャ帝国をつくった人々の子孫だという強烈な意識を持っています。
そういう連綿とした1つのアイデンティティを守り続けている民族は、世の中に2つあります。1つがイランで、もう1つは4000年の歴史を誇る中国です。ですから、世界の中心にいる自分たちは発言すべきと思っているわけです。自分たちが国際政治の主役であり、イランの首都ペルセポリスが宇宙の中心なのです。その意味では、中東版の中華意識といえます。
イランのイスラム宗派は、たまたまシーア派です。イスラム教徒のおよそ9割がスンニ派、1割がシーア派なので、自分たちの宗派がシーア派であるということが、ますますイラン人の「自分たちは違う」という意識を強めています。ですから、「世界の中心でイスラム革命を叫ぶ」というメンタリティを、もともと持っている人々だといえます。
イラン・米国関係の特殊性
そのイランが、核兵器をつくっていると皆が疑いました。イランは、そんなことはしていないと言い張るのですが、イランの西隣にはイラクがあり、その向こうにはイスラエルがあって核兵器を持っていることは、よく知られています。イランの東隣には核兵器をたくさん持っているパキスタンがあり、その隣にも核兵器を持っているインドがある。イランの北には、やはり核兵器をたくさん持っているロシアがいて、インド洋には米国の原子力潜水艦がうようよいて、核兵器を積んでいないとは誰も思っていません。つまりイランは、まわり中が核兵器なのです。そのイランが、核兵器を持つことは不思議ではありません。まわりが怖いから、用心棒の1人も雇いたいと思っても不思議ではないと、自らが核兵器を持っている周辺国も思うわけです。
では、何のために核開発をしているのかというと、イランが主張しているのは経済合理性です。イランの石油は、20世紀初めにペルシャ湾岸で最初に開発されました。もう100年以上も掘り続けて先が見えており、国内人口も増えている中で、電力は原発で起こし、石油は日本や欧州に高い価格で売りたいというわけです。
もう1つは、もちろんイラン人の民族としての誇りです。日本をはじめ先進諸国ではウラン濃縮が許されているのに、なぜイランだけやってはいけないのか。国民の識字率が半分に過ぎないような隣国のパキスタンが原子爆弾を持っているにもかかわらず、イランは平和開発といっているのに、それも駄目なのかという思いが、イラン国民の間にあると思います。
米国をはじめ世界がイランの核開発に対して神経質なのは、イランが普通の国ではないからです。1979年にイラン革命が起こった際、米国大使館はイランの学生によって乗っ取られ、外交官が人質になりました。イラン政府は大使館を守らず、学生がやったことをホメイニ師は非難もしませんでした。米国には、これが深い心の傷となって残ったと思います。ですから今回、オバマ大統領の米国民への説得が難航したことには、そういう背景があったわけです。
イランでは、米国の外交官を人質にして悪いことをしたと思っている人もいますが、大半の人はそうではなく、当たり前だと思っています。米国人にとってのイランとの歴史は1979年から始まりますが、イラン人にとっての米国との歴史は1953年に始まります。かつてイランでの石油生産を独占していた英国は、イランの石油生産によって莫大な利益をあげていました。そこでイランは、1951年に石油産業を国有化します。すると、イランで国有化が成功すれば他の国にも波及してしまうということで、世界の大手石油企業はイランの石油をボイコットして、経済的に締め殺そうとするわけです。
イランは、英国は当然締め付けてくるとしても、米国は助けてくれるだろうと期待していました。しかし米国からすると、モサデク首相(当時)が何をするかわからず、ソ連に取り込まれるかもしれないということで、1953年に米英の諜報機関が中心となってクーデターを起こしてモサデク政権を倒し、石油国有化は白紙となりました。そのときのクーデターの作戦本部は、米国大使館にあったわけです。ですからイラン人にしてみれば、米国大使館というのはイランに対する内政干渉の本部であり、そんなところを乗っ取るのは当たり前で、米国の外交官といえばスパイですから、人質に取ることもイラン人には「理解」できる面があります。
クーデターによってモサデク政権が倒れると、米国は経済軍事援助を注ぎ込んで、シャー(王)の体制をずっと支えました。そして、イランが共産化しないようにシャーのためにつくられた秘密警察は、共産主義者以外の反対派も捕まえて回りました。シャーが倒れるまでは多くの人々が秘密警察に捕まって拷問され、殺されたわけです。ハネメイ師やラフサンジャニ元大統領など、今の政権幹部は皆刑務所に入り、秘密警察に拷問された人たちばかりです。だから米国に対し、いい感情を持つわけがありません。
イランと米国関係は、米国人にとっては自分が被害者であり、イラン人にとっても自分が被害者ですから、加害者がおらず被害者しかいません。だから日韓関係や日中関係のように、謝るとか謝らないとかいう問題ではなく、双方が被害者だと思い込んでいるわけです。
さらにイラン革命政権が台頭すると、1980年にサダム・フセインが化学兵器まで使って攻めてきました。それに対して米国は非難の声もあげず、逆にサダム・フセイン側に衛星画像でイラン軍の配備を教えるなど、イラクを支援したのです。ですからイランは、革命が成就するまで秘密警察で邪魔をされ、革命が成就してからもひどい仕打ちをされたということで、米国に対する深い恨みを持っています。同様に、双方が深い恨みを持ってイランと米国の関係が転がり始めたわけです。
届かない手と手
しかしながら、イランの重要性は米国も認識し、米国と付き合ったほうがいいことはイランもよくわかっています。そこで、何度か両国を摺り合わせようという努力が行われましたが、その1つが、イラン・コントラ・ゲートです。レーガン政権時、米国がイランに兵器を売り、その兵器でイランはイラクと戦い、イランが支払った代金は米国の国庫へ入らずに、ニカラグアで左翼政権と戦う右翼ゲリラに回していたことが明らかになり、大騒ぎになりました。この背景には、米国が武器を売ることで、イランをソ連に取り込まれないようにしようという発想がありました。
その後、パパ・ブッシュは、大統領就任演説で「善意は善意を呼ぶ」というメッセージをイランに送ります。これは「レバノンで人質になっている米国人を助けてくれれば、イランとの関係を改善しましょう」という意味でした。そこで、実力者のラフサンジャニが国内の反発を押さえ込み、レバノンから米国の人質を救い出します。しかし、ラフサンジャニは報酬を待っていたものの、ブッシュ・ホワイトハウスはそれに答えません。イランにさんざん仕事をさせた後で、「そもそも人質をとるのが間違っているだろう」という米国の返事に、ラフサンジャニはしらけてしまい、大統領が代わるのを待つことになります。
すると米国では、クリントン大統領が就任します。ラフサンジャニは米国との関係改善を睨み、イランの油田開発の利権を米国のコノコという石油会社に渡す交渉を始めます。しかし、いよいよ契約の署名に近づいたときに、クリントンが大統領令を発令し、イランとの契約を白紙にしたのです。当時、米国はITバブルで景気がよかったため、共和党は与党を叩くイシューがありません。そこで共和党が、「イランに甘い」とクリントン政権を攻撃しようとしたため、先手を打つために大統領令を発令したわけです。つまり、米国の国内政治で駄目になったということです。
続いて発足したハタミ政権は「文明間の対話」を打ち出し、アフガン戦争をやる上でも、その後のアフガニスタンのカルザイ政権の誕生の際にも、とことん米国を支えました。しかし、それに対して米国が行ったのは、2002年1月のブッシュ大統領(当時)による「悪の枢軸(axis of evil)」発言です。北朝鮮、イラン、イラクの3カ国を名指しして「悪の枢軸」として批判したわけです。ハタミ政権の外交は、これによって破綻します。ハタミの笑顔が凍り付いた瞬間といえるでしょう。
オバマ政権の努力
2002年、イランに核施設があることが明らかになり、核問題が表面化しました。2003年には、米国がサダム・フセインの体制を倒します。イランでは、ハタミに代わってタカ派のアフマディネジャド大統領が誕生し、米国では、オバマ大統領が登場しました。オバマは演説の中で、「握りしめたこぶしを開くなら交渉しよう」と呼びかけます。
さらに3月の春分の日には、オバマがイラン国民にビデオメッセージを送り、毎年ペルシャ語で「新年おめでとう」とイラン国民に話しかけています。また国務省においても、ヒラリー・クリントンがペルシャ語のツイッターを始めます。イランのメディアが米国からのメッセージを取り上げない場合に備えて、ソーシャルメディアを通じて訴えているわけです。そしてイランのために、ペルシャ語専門の報道官も置いています。
ところが、イラン側の大統領選挙で大規模な不正があり、人権弾圧があったということで、さすがにその時期、アフマディネジャドと交渉するわけにはいかなくなります。アフマディネジャドは西側メディアに評判が悪い人物ですが、おそらくイラン庶民にとっては、それほど悪い人には見えないように思います。ムサビ元首相とのテレビ討論会において、アフマディネジャドは、ムサビの部下や支持者がボロ儲けしているではないかと畳みかけます。どう見ても、アフマディネジャドの勝ちなのです。アフマドネジャドは、あれほどの大規模な不正をせずとも、大統領選に勝てたのではないでしょうか。
ロー「ハニー」大統領の微笑
アフマディネジャドの次に出てきたのが、現・ロウハニ大統領です。自分は新しい時代を開く鍵であり、対外関係を改善して国民の生活を向上させるとし、まともな国としてまともにやろうという「微笑路線」の政権運営は、まさに名前通りのロー「ハニー」といえるでしょう。アフマディネジャド政権時はイランを悪者にしやすかったわけですが、ロウハニはまともに見えるため、イランの敵としては手ごわく感じると思います。
ロウハニ政権は、イランという国は評判が悪く、主要メディアがなかなか取り上げないため、ソーシャルメディアを使っています。有名なのは、ザリーフ外務大臣のツイッターです。最初に「世界のユダヤ教徒の皆様、新年おめでとうございます」というメッセージを出しました。これに対し、米国の民主党下院議長であったペロシ氏の娘が「イランが"ホロコーストはなかった"などと言うのをやめてくれたら、もっといい正月ですね」と返すと、ザリーフは「イランは国として、そんなことを言ったことはありません。そんなことを言った男はもういません」と返したのです。このやりとりは、大きな話題となりました。
人脈という名のソフト・パワー
ようやく、オバマとロウハニという双方が交渉できる組み合わせになり、国内をまとめるだけの力が動いたといえるでしょう。またイランと米国の関係は、争っていても常にバックチャネルがつながっており、プランBがある、ということが特徴だと思います。ですから両国の関係を考えるとき、米国のイラン人コミュニティは重要です。
では、イランと米国は、これですべてハッピーかというと、そうではありません。シリアの問題など、ぶつかるところもあるし、協力するところもあるわけです。比較の例としては、ニクソンの中国訪問が良いと思います。1972年にニクソンが北京を訪れ、すべて解決したわけではありません。米中間では戦争をせず、貿易や投資をしているにもかかわらず、南シナ海では対立しています。つまり、協調的対立関係なのです。イランとの関係も、おそらくそういうことだと思います。これからハネムーンが始まるわけではなく、ただ、殴り合いで相手が死ぬまで喧嘩をするのはやめようということでしょう。
モデレータ:
今回、イランが米国との交渉でここまで勝ち得たのは、それを支えるだけの人材がいることに加え、それを理解する国民がいるということだと思います。イランの選挙は、アフマディネジャドが大統領に当選した際は不正があったと言われていますが、最近はそれもできなくなり、民意とかけ離れた選択はできなくなっています。米国とイランの関係は、表面的にとらえると物事を見失う可能性があると思います。
質疑応答
- Q:
-
米国とイランの核合意に先立ち、そもそも米国とイスラエルが協力し、Stuxnet(スタックスネット)というコンピュータウィルスでイランの核施設を攻撃したことについて、どのように見ていらっしゃいますか。
- A:
-
9月にイスラエル、パレスチナを回り、今回の合意について現地の声を聞いてきましたが、意見は分かれていました。イスラエルの人口約834万人のうち、20~30万人はイランからの移民とその子孫です。近年、イスラエルではペルシャ語の歌が大ヒットしています。国民がペルシャ語の歌でうたい踊っている中で、イランと戦争できるだろうかというのが私の発想です。やはり、新聞の一面が伝えるのとは違う感情が抱かれていることを実感しました。
今回のイランとの核合意で注目されるべきは、米国でユダヤ・ロビーの意見が割れたことでしょう。アメリカに留学した人なら誰でも知っているアイスクリームの企業「ベン&ジェリー」のベンとジェリーは、いつもイスラエルのために寄付集めをしていることで有名ですが、今回はオバマ支持を打ち出し、核合意に反対した民主党議員には寄付しないという運動を始めたほどです。これまでのように、米国はこうだ、イスラエルはこうだ、イランはこうだ、と括りにくくなっていると思います。
- モデレータ:
-
イランにもユダヤ人はそれなりにいて、国会でユダヤ人の議席が確保されています。他国に比べて活動に制約はあるものの、ユダヤ教の祈りもできます。イランにユダヤ人の存在が認められているという点も、日本人の考えるイランのイメージとは違うように思います。
- Q:
-
今後の米国とイランの関係について、どのようなことがポイントになるでしょうか。
- A:
-
基本的に、イランはこの合意を粛々と履行していくと思っています。それが利益だと認識したからこそ、合意に至ったためです。おそらく問題はシリアで、妥協が難しいところでしょう。しかし、それは最初からわかっていることで、この核合意によって世の中すべてハッピーになるとは誰も思っていません。ただし、次の米国大統領が誰になるかが心配なところです。付言すれば、過激なことを言っているヒラリー・クリントンも、イラン人の富豪から寄付を受けているところは知られていますので、楽観視しています。
- Q:
-
米国とイランが政治的に協調路線になったわけですが、コノコの件を踏まえて、経済面ではどのような動きになると思われますか。
- A:
-
米国企業のイランへの進出は進むでしょうが、どちらの国にもそれに否定的な人も多いため、おそらく米国企業よりは欧州企業、日本企業のほうが入りやすいように思います。
- モデレータ:
-
今回の経済制裁解除は、日本や欧州の企業は対象となっていますが、米国企業は対象になっていません。石油、ガスについては、90年代初めにコノコが投資をしようとした頃から制裁が厳しくなっています。つまり2002年に核疑惑が浮上する10年以上早く、制裁されているわけです。
ですから理屈で考えると、核疑惑が生じる前からあった石油やガスに対する制裁は、核合意に至っても解除されないと思う人が多かったのですが、実際にはそこまで解除されたわけです。ただし、実際にどこまで外資が進出できるかを考えると、石油の開発には膨大なコストがかかる一方でリスクが高く、原油価格も低下していますので、すぐに動くという状態ではないと思います。
またイランは、かつて国の宝である石油を外国人にほしいままにされているとして革命を起こし、それが米国に潰され、再び革命をして今の政治体制になっています。当然、石油はイラン国民のものだという発想が強いため、外国人に利権を売り渡すことには抵抗があると思われます。そこで、国民が納得するやり方で、どういう仕組みをつくっていけるかが、今のイラン政府の悩ましいところでしょう。
この議事録はRIETI編集部の責任でまとめたものです。

