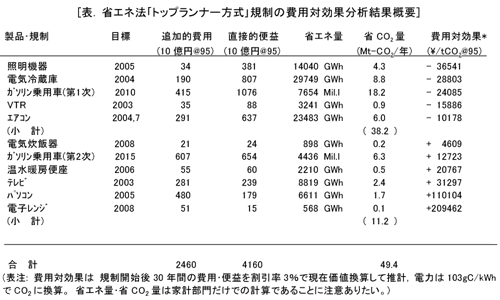トップランナー方式省エネルギー規制の費用対効果
従来、省エネルギー政策の効果はその省エネルギー量や温室効果ガス削減量の大きさで評価されてきた。今次、経済産業省によるプロジェクトにおいて、その費用対効果を推定し「省エネルギー対策に一体いくら掛かっているのか?」を定量的に政策評価しようという試みが行われている。
筆者は、当該プロジェクトにおいて省エネルギー法に基づく家電製品やガソリン乗用車のトップランナー方式規制の分析を担当した。その詳細は本研究所の2つのディスカッションペーパーとして一般公開しているが、分析結果の概要を下の表にまとめて示す(表)。
当該分析には相応の誤差が存在すると考えられるが、それを差し引いたとしても注目すべき点が2点ある。
1) マイナスの費用対効果: ガソリン乗用車(第1次)、冷蔵庫・エアコンなど主要な規制対象製品の多くでマイナスの費用対効果が観察される。
2) 極端なプラスの費用対効果: パソコン、電子レンジなど一部の製品で 10万円/tCO2 を超える極端に大きいプラスの費用対効果が観察される。
費用対効果がマイナスということは、企業側での省エネ技術開発や設備投資などの追加的費用による製品価格の値上がり分よりも、家計側での電気代やガソリン代の低減による直接的便益の方が大きく、何らかの原因により効率や燃費の改善が妨げられていたことを意味している。
一方、費用対効果が極端に大きいプラスの値ということは、企業側での追加的費用が家計での直接的便益を大きく上回っており、技術的に困難な対策を選んでしまったか無理な目標が設定されたことを意味している。
以下、本稿ではこの2つの対照的な結果について考察してみたい。
マイナスの費用対効果と省エネ製品への投資リスク
仮に家計も企業も「合理的」に行動しているのならば、家計は電気代やガソリン代を考えた上で相応に効率や燃費の高い製品を購入したはずであり、企業はそれを見越してより効率や燃費の高い製品をより多く提供して「自然淘汰」が生じたはずである。従って、「合理的」な家計と企業の行動の下では効率や燃費は自律的に改善が行われて費用対効果はゼロの状態にあり、政府が規制により効率や燃費を無理に引上げた場合には費用対効果はプラスの値になるはずである。
ところが、ガソリン乗用車で最も典型的であるが、省エネルギー法による規制が行われていない期間の燃費は殆ど改善しておらず、こうした「自然淘汰」の形跡は見られないのである。
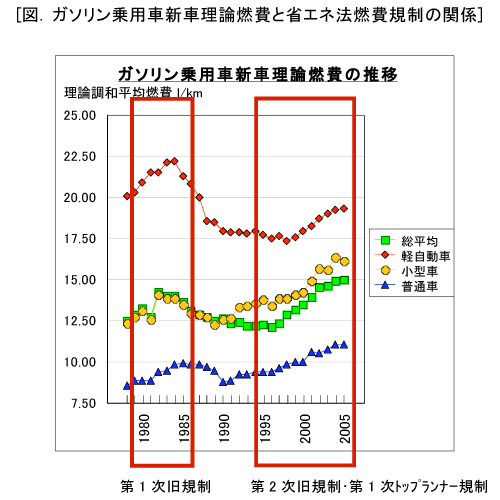
このような一見「不合理」な現象は、ガソリン乗用車を例として以下のように説明される。
消費者のガソリン乗用車の選好は必ずしも燃費や費用だけを考えたものではなく、家族構成や住んでいる地域の交通事情、あるいは美学や趣味趣向などの「総合点」で買う車が選択され、燃費の高い車が確実に売れるとは限らない。
一方、自動車会社側は、自社が巨額の研究開発・設備投資を行って燃費の高いガソリン乗用車を開発したとしても、消費者が燃費の高い車を選ばないリスクや、他社が室内空間の広さや快適な走りなど燃費以外の訴求点で競争を仕掛けてくるリスクがある以上、費用増加や売上低減により自社が損失を受ける事態を考えて投資を躊躇するはずである。
この結果、消費者と自動車会社の双方が長期的に見てガソリン代低減という利得が生じることを潜在的に認識していながら、消費者が燃費に対し確実に反応する保証がないため、企業間の競争の過程でリスクの大きい燃費向上への大規模な投資が後回しにされていたと考えられるのである。
省エネルギー法トップランナー方式規制は、効率や燃費の目標値の遵守を輸入・製造企業全部に義務づけることにより、消費者が効率・燃費の高い製品に反応しないリスクをなくし、効率・燃費の向上技術を開発している間に他の訴求点で他社から競争を挑まれるリスクを低減させた。
このため、「省エネ製品への投資リスク」により本来の「自然淘汰」の水準を下回っていた効率・燃費が規制により回復し、規制の費用対効果がマイナスとなったものと考えられる。
極端に大きなプラスの費用対効果と「政府の失敗のリスク」
では、政府による効率・燃費規制は「省エネ製品への投資リスク」を必ず断切り、優れた費用対便益をもたらす「魔法の杖」なのであろうか?
残念ながら、最初の表の下の方の製品を見る限り、必ずしもそうではないようである。
多くの規制緩和の議論で主張されているとおり「政府部門も失敗を犯す」ものであり、真摯に取組んでおられる関係者には申し訳ない限りであるが、このような極端に大きなプラスの費用対効果の省エネルギー対策を義務づけることは明らかに経済厚生を下げていると考えられる。
通常、省エネルギー対策の考え方ではエネルギー消費量の大きい製品・行為を対象として対策が検討されるのであるが、ある目標を達成するための技術的困難性を、実際に取組んでみる前から客観的に認識することは非常に難しい。また、当該困難性を企業側が正しく認識していたとしても、それが政府に正しく伝わるとは限らない。その結果、政府担当者が最善の注意を払ったとしても、技術的に困難な製品が規制対象に選定されたり、過度に高い目標値が設定されてしまう懸念は常に存在することになる。
あるいは、その逆に「まんまと政府担当者の目をすり抜けた」のであるが、実は費用対効果が大きなマイナスになるはずの製品もまだ残っていると推察される。
省エネルギー法トップランナー方式規制については、一般には優れた政策であると認識されており、事実、全体としての費用対効果を見た場合には優れた制度であることが再確認されたが、それでもなお部分的には改めるべき点が少なくないと思われる。
最適な家計部門の省エネルギー対策の制度とは
では、「政府の失敗のリスク」や「省エネ製品への投資リスク」を取除き、「環境と経済の両立」を実現させる有効な家計部門での省エネルギー対策の制度とは何であろうか?
制度の選択においては、現実の「省エネ製品への投資リスク」と「政府の失敗のリスク」の大きさや制度の実現可能性を見極めなければならないが、以下の2つの制度が考えられる。
制度A. 課税や割当規制制度を採択し「政府の失敗のリスク」を排除する。
制度B. 燃費・効率規制制度を採択し「省エネ製品への投資リスク」を排除する。
制度A. については、費用対効果の尺度が税率や排出権市場価格で明示されるので「政府の失敗のリスク」は生じにくい。しかし、"マイナスの費用対効果と省エネ製品への投資リスク"で論じたような「省エネ製品への投資リスク」を緩和させることは容易ではないと考えられる。
家計の所得水準が十分高く、かつ課税措置や割当規制措置が電気代やガソリン代を激変させないような穏和な水準であったならば、家計は課税や割当規制に伴う値上がり分を何事もなかったように支払い今までどおりの消費を続けるかも知れず、企業側は依然として「省エネ製品への投資リスク」にさらされ続けることになるからである。事実、世界有数の高率なガソリン税が課されているにもかかわらず、省エネ規制が行われていなかった1990年頃の日本のガソリン乗用車の燃費は一方的に悪化していたのである。
一方、制度B. については「省エネ製品への投資リスク」は回避され低減するが、その反面、費用対効果の悪い省エネルギー対策を義務づけてしまう「政府の失敗のリスク」が残ることとなる。
日本での家電機器やガソリン乗用車に関する分析結果から判断する限り、「政府の失敗のリスク」よりも「省エネ製品への投資リスク」の方が大きいようであり、従って規制緩和の流れに反することは十分承知した上でなお、日本においては費用対効果に注意しながら制度B. による効率・燃費規制を続けていくことが合理的な選択であると考えられる。