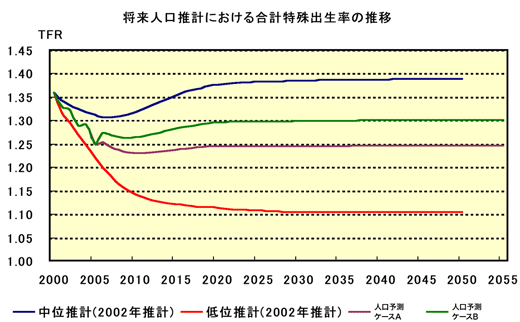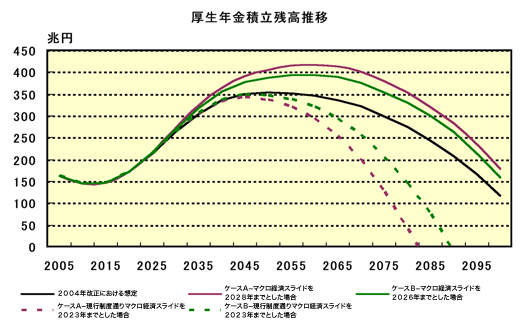新人口推計はどうなるのか?
来月(2006年12月)にも、新しい将来人口推計が国立社会保障・人口問題研究所(社人研)から発表される予定だという。前回の推計(2002年)から5年経ての定期的な推計の改訂であるが、社会保障政策のみならず公共事業の需要予測にも用いられるなどわが国の政策立案に利用されることの多い推計だけに人々の関心も高い。ここ最近の大手新聞などの各メディアは厚生労働省社会保障審議会人口部会における議事などを通してさまざまな「将来人口予測の予測」を行っている。それらの報道を見ていると、やはり今回も前回推計に比して下方改訂となる見通しであるという。
過去の推計においても社人研の将来人口推計は下方改訂を繰り返してきた。そのたびに社会保障制度などの見直しの必要性が生じ、社人研の将来人口推計は世論の強烈な批判の的になってきた。確かに事後的に見れば、もう少し正確に予測できなかったものかと思いたくもなる。社人研推計は人口学のスタンダードな推計手法を用いて可能な限りの科学的客観性をもって将来人口を予測しようとするものである。これに対して経済的要因を明示的に組み込むべきだとの経済学者からの批判は多いが、社人研側は恣意的な推計になる可能性を拒み、人口学的な推計にこだわってきた。別に社人研推計を擁護するわけではないが、確かに社人研の主張にも傾聴すべき点は多い。過去の推計における下方改訂は、人々の出生行動がいかにダイナミックに変動してきたかを示していると逆説的に捉えることもできよう。
しかし、勿論、何度も推計を下方に修正し続けることは推計の信頼性のみならず、諸政策の信頼性をも危うくするものであるから、社人研推計に望まれる改善すべき課題は多い。各種報道や人口部会の議事を見る限り、新しく発表される新将来人口推計もこれまでの批判のいくつかには応えるものになっていると推察される。ただ、筆者としては、「高位・中位・低位」といったシナリオ別の人口推計を示すのではなく、中位を中心に確率的幅を明示的に持った将来の人口推計を示してくれればより説得力が増すと思うのだが、今回の推計では従来通りにシナリオ別の推計が示されるようである。
いずれにせよ、新推計は非婚化・晩婚化・晩産化などの影響を考慮して前回推計よりも下方に改定されることは間違いなさそうであるが、具体的にどのような推計になるかは、まだ明らかにはされていない。しかし、前回推計とこれまでの実現値を比べると実現値は概ね前回推計の中位推計と低位推計の中間を取っていると指摘されことが多い。たとえば2005年の合計特殊出生率(TFR)は前回推計の中位推計では1.31076、低位推計では1.22074と仮定されていたが実現値では1.25(暫定値)となっていた。そのため、今回の新推計における中位推計は前回推計の低位と中位の中間程度になるのではないかと推測する向きも多い。
新人口推計で年金はどうなる?
将来人口推計の下方改訂で最も影響を危惧されるのが社会保障、とりわけ公的年金制度である。年金制度の持続可能性は扶養率(受給者数/被保険者数)の変動に大きく左右されることを考えれば、人口推計の下方改訂は年金制度にとって明らかな負の要因である。特に2004年の年金制度改正は「保険料負担の上限設定」「モデル世帯の所得代替率50%維持」を掲げていたが、これは当然ながら前回の将来人口推計(平成14年)の中位推計を前提としたものであって、人口想定が異なる場合は結果が異なってくる。特に、保険料率の上限を維持する限りモデル世帯所得代替率50%維持は非常に困難になる。このことをより具体的に考察するために「新将来人口予測を予測」して次のようなシナリオ想定をおいて仮の人口推計を計算する。
人口予測ケースA
2006年以降の各歳別出生率が2002年人口推計の中位推計と低位推計の中間を取るものと仮定。2055年時点のTFRは1.24532であり、2055年以降は2105年に向けて人口置換水準2.07へ回帰するものと仮定。
人口予測ケースB
ケースAよりも若干楽観的に2055年時点のTFRが1.30になると仮定。2006年から2049年にかけては2004年推計の中位と低位を2055年のTFR1.30に対する比率で案分。2055年以降はケースAと同じく2105年に人口置換水準2.07へ回帰するものと仮定。
但し、ここでは社人研の2002年推計を利用して、少々荒っぽく人口を計算しているため、予想される生命表の改訂(平均余命の変化)などは考慮されていないことには注意されたい。
この仮の人口推計(ケースAおよびケースB)のもとで年金財政がどうなるかを、筆者らが開発した年金財政シミュレーションモデル(RIETIモデル)を用いて推計してみよう。ここでは厚生年金の積立残高の推移がどうなるかを以下に示す。積立残高の推移を示すのは次の理由による。2004年改正では今後年金財政の均衡期間をおおよそ100年間と定め、均衡期間の最終年次に当該年度の給付額1年分を確保するものとされた(有限均衡方式)。よって均衡期間における積立残高の水準は年金財政の持続可能性の重要な指標となるからである。ただし、ここで2004年年金制度改正との比較を明確にするために人口以外の諸想定は全て2004年財政再計算の基準ケースに合わせるものとし(名目賃金上昇率2.1%、名目運用利回り3.2%、物価上昇率1.0%)、計算期間も2100年まで(2009年の次期年金改正のことを考えれば2105年を最終年度にしてもよいが比較のために2100年まで)とした。
2004年改正では年金財政維持のためにマクロ経済スライド制度と呼ばれる財政調整機能が導入された。これは均衡期間の財政維持が確保される見通しがつくまで(おおよそ100年後の積立残高が給付1年分確保される見通しがつくまで)給付のスライド率(新規裁定:賃金上昇率・既裁定:物価上昇率)から被保険者減少率と高齢化率0.3%の和を時限的に差し引くものである。これは時限的に年金給付総額の伸びをGDP成長の範囲内に自動的に抑えることを意味する重要な財政調整機能であり、2004年改正における最重要の改正内容である。2002年人口推計を前提とする2004年改正ではこのマクロ経済スライドは2023年まで導入されるものとされた。
さて、2004年財政再計算の諸前提のうち、人口想定だけを上記のケースA・ケースBに差し替えた場合、つまりマクロ経済スライドの適用は2023年までとし、人口推計のみケースA・ケースBに差し替えられた場合はそれぞれ2080年、2090年あたりで積立金が底をついてしまい財政の持続可能性は維持されないとの結果となった(上図の緑破線・紫破線)。この財政悪化に対してマクロ経済スライドの適用期間延長で対処した場合、ケースA人口の場合は2028年まで、ケースB人口の場合は2026年までそれぞれマクロ経済スライドの適用期間を延長することで積立残高給付1年分以上を確保できると推計された(上図の緑実線と紫実線)。
しかし、マクロ経済スライドの適用延長は給付水準の減額を意味している。2002年人口推計を前提として2023年までマクロ経済スライドを適用すれば2023年以降のモデル世帯新規受給時(65歳)所得代替率は50.2%だが、ケースB人口を前提として2026年までマクロ経済スライドを適用すれば2026年以降のモデル世帯所得代替率は48.06%、ケースA人口を前提として2028までマクロ経済スライドを適用すれば2028以降のモデル世帯所得代替率は47.18%になるものと推計された。
所得代替率50%はどれだけ重要か?
以上見たように、人口推計が下方改訂されるならば年金財政の見通しも変化し、特に保険料負担の上限を2004年改正通りに抑えながら現行制度のまま年金財政を維持していくためにはマクロ経済スライドの適用期間を延ばして給付水準を押さえる必要性が生じる可能性が高い。しかしその際には所得代替率50%維持(モデル世帯)の再検討が課題となる。
そもそも給付水準を所得代替率で50%に保証する根拠とは何なのだろうか? おそらくは相対貧困の定義(所得分布の中央値の50%以下)と関連して議論されてきたのかもしれないが、公的年金でこの水準を維持できたからといって、国民の年金に対する信用が高まる(維持される)保証はどこにもない。現に将来水準よりもずっと所得代替率の高い今現在の年金給付に対しても不満をもつ人々が決して少なく無いことは示唆的である。給付に偏りがあったり、制度の原理原則に不透明さがある場合には、たとえ所得代替率が高くとも年金に対する人々の信用は高まることは無い。
勿論、給付水準は低いより高いほうが良いに決まってはいるが、人口減少で制度の支え手が少なくなる以上、家計や企業が耐えられないような財政的実現可能性のない負担水準を前提にして議論しても意味が無い。むしろ限られた財源の中で、最も人々が安心でき、かつ納得できる給付体系はどのようなものなのかを議論するほうが遥かに重要である。
建設的な議論のためにデータ整備は不可欠
上記ではマクロ経済スライドの延長だけを考えたが、他にも重要な課題はいくつもある。たとえば、給付開始年齢の再引き上げ(67歳・70歳)、遺族年金給付の見直し、さらには消費税の目的税化などが挙げられよう。給付開始年齢の引き上げに関してはすでにドイツが前倒しで実施することを決定しており、日本という長寿化が最も進んだ国で65歳という給付開始年齢がはたして適切なのかも議論すべきだろう。また遺族年金給付については、現在は厚生年金加入者の場合、妻が夫の報酬比例年金の75%を受給できる制度になっているが、諸外国の水準は、制度はまちまちなので簡単な比較はできないが、概ね50%前後といったところだろう。この水準が今後のわが国で適切かどうかも広く議論する必要がある。
但し、もし給付開始年齢の引き上げや遺族年金の見直し、もしくは国民年金納付率の低水準持続などで保護率が国民の負担の許容できる水準以上に急増することが予測されるなら、むしろ年金の持つ所得再分配機能をより強化する方向で議論することも望まれるだろう。しかし、これらを詳細に議論することがわが国では非常に難しい。なぜならば、中高齢者を対象とした統計データ、特に信頼できるパネルデータの整備が著しく遅れているからである。ある年金制度の変更がその他の経済変数にどのような影響をもたらすかという事を、事前にデータを基に検討するという欧米では当たり前のプロセスが、我が国では絶望的に難しいのである。
そこで経済産業研究所では、清水谷諭氏 (一橋大学経済研究所助教授)、市村英彦氏 (東京大学公共政策大学院、大学院経済学研究科教授)、野口晴子氏 (東洋英和女学院大学国際社会学部国際社会学科助教授)、橋本英樹氏 (東京大学大学院医学系研究科客員教授)らを中心として、わが国を代表する経済学、公衆衛生・医療の専門家に集まっていただいてプロジェクトを結成し、中高齢者を対象とした大規模なパネル調査を実施している。これはアメリカのHRS、大陸ヨーロッパのSHARE、イギリスのELSAといった既に世界標準で確立されている中高齢者パネル調査と同等の調査であり、相互の比較も可能なデータとなっている。調査票も非常に緻密に計画されているため単年のデータだけでも貴重な情報が集まるが、数年蓄積するだけでもパネルデータとしての威力が相当に発揮されることになる。今後この調査が蓄積されていくたびに、わが国の社会保障政策を巡る議論がより緻密に、より建設的になっていくことを筆者は確信している。
最も危惧すべきは…
今後の公的年金をより良きものとするために議論すべき課題はいくつもある。これらに関する議論をより深めることができれば、限られた財源の中で人々の厚生を十分に維持・改善できる可能性もある。しかし、危惧されるのは2004年改正の時のように年金制度改正が極めて政治的な課題として取り扱われて本質的な議論が全く進まなくなってしまうことである。特に所得代替率50%云々といった、1つの重要な目安ではあっても、指標群の1つだけが取り上げられて政治的な攻防戦が繰り広げられることだけは避けなければならない。そういったところで議論が行われても国民の利益にはつながらないことは明記しておかねばならない。
新しい人口推計が発表されることで人々の年金、ひいては社会保障政策全般に対する関心は再び高まりを見せるであろう。そしてこれを契機に、無意味な魔女狩りではなく、より建設的な議論が繰り広げられることを期待したい。