知識集約型経済への移行に伴い、日本においても産学連携の推進が1つの重要な政策課題として認識されるようになった。この背景には、新企業・新産業創出による景気低迷からの打破・雇用創出という考えもあり、大学に教育・研究という従来の役割の他に技術移転という新しいミッションが課せられることとなった。このように社会的認識を獲得した「産学連携」ではあるが、このコンセプトには多種多様な解釈がなされており、また政府主導で産学連携を推進するべきか、という論点もある。すでに総合科学技術会議、産業構造審議会、科学技術・学術審議会においても「産学連携」に関する議論がなされているが、本論では産学連携のフレームワークを形成するにあたって留意すべきであると思われる幾つかの基本点を示唆することとしたい。
大学と産業ーそれぞれ固有の「アイデンティティ」
まず「産学連携」の定義として、『大学と産業という2つの異なるドメイン(領域)に所属するアクターの相互作用を通ずる相乗効果によって、大学と産業の持つポテンシャルがそれぞれ高められていくプロセスである』としよう。このプロセスは、人的資産の質のレベルアップ、イノベーション能力の向上、経済生産性の向上といったマクロレベルでの効果を誘発するポテンシャルを内包しているため、日本経済の沈滞を克服する1つの手段として高い期待が寄せられている。このプロセスにおいては、大学が1つのアクターとして自ら意思決定を行使する条件の整うことが必須だが、国立大学の非公務員型法人化により、条件整備の一歩が踏み出されることになるだろう。
この定義の根底にあるのが「2つの異なるドメイン」の存在である。産業は製品開発を最終目的とするが、大学には「知識の創造」とそのバイ・プロダクトとしての教育、また応用研究と基礎研究の間のフィード・バックを可能にするような研究環境が想定されるだろう。この2つの補完的なドメインの間を人とアイデアがそれぞれの成熟のレベルに適した研究環境を求めて移動し、そこでさらに成熟度を増していき、その結果としてホストである組織にプロセス・イノベーション、プロダクト・イノベーション、資源支配力、社会評価といった形でのリターンが生じていく。だが社会のイノベーション能力と生産性を高めるような産学連携は、産業と大学の機能の境界を限りなく曖昧なものにすることによって得られるものではない。大学に起業のノウハウがもともと存在するわけではなく、また大学が産業の下請け機関となっても強い革新力は生まれない。アメリカのMITやスタンフォード大学などをみると、大学と産業とがそれぞれ固有の「アイデンティティ」を維持することをその基本的思想としていることがわかる。大学の「企業化」をターゲットとする産学連携推進は、大学の本来の機能を低下させるリスクを多分に含むものであることに留意したい。
ますます重要な仲介者の役割
さて、大学と産業の連携において媒体となる人とアイデアの動きであるが、大学から企業へと一方向にではなく、双方向の流れが存在することによって、より相乗効果が高まることを認識すべきだ。産業が大学をアウトソーシング先として活用することが「産学連携」であると思われがちであるが、企業から大学にも人・アイデアが流れることにより、社会全体のイノベーション能力が向上し、個々の企業に正の外部効果が生まれてくる。その一例が、企業の研究者と大学人がアイデアを出し合い、共に研究し、明日の技術パラダイムを摸索していくという構想のもとにつくられたスタンフォード大学のCenter for Integrated System (CIS)である。
日本ではこれまで、卒業生の就職割り当て、共同・委託研究、奨学寄附金、特許手続きの企業代行などをチャネルとして、特定の企業と特定の研究室の間の貸し借り関係を通じた継続的な繋がりが形成されてきた。企業の自前主義と補完的にこうしたタイプの「産学連携」は過去にはある程度うまく機能してきたが、継続的な関係から排除された中小企業や新企業はイノベーションに必要な知識へのアクセスにおいて、明らかに不利な立場におかれていた。TLO(技術移転機構)という制度が導入された背景にはこのような状況があった。また国立大学「教官」という制約のもとでは、教授が自ら起業する、或いは大学院卒業生による起業を非常勤役員として援助する、などということは法制的なルール上無理だった。大学側にとっても見返りのない特許取得にはインセンティブが働かず、特許公開を通じて研究成果が広く産業界に移転されるということはなかった。兼業許可の見直し、大学研究者の職務発明を大学へ帰属化させるという動きは、これらの問題の解決に貢献するであろう。
投資家と企業の間に仲介組織が存在するように、産と学の2つのドメインのインターフェイスとして機能しうるのがTLO、インキュベータ、ベンチャー・キャピタルといった専門的サービスを供給する半自律的な組織である。これらは、技術が産と学の間を移転する際、その橋渡しをサポートする役割を担っているが、技術の成熟度、市場との距離によって提供するサービスの内容も異なってくる。技術シーズと企業ニーズのマッチングを主に行うリエゾン・オフィス、大学の研究成果の特許化・ライセンシングを業務とするTLO、技術の事業化を技術面・ビジネス面でサポートするインキュベータ、ベンチャー企業を含むハイテク企業に操業の場とビジネス・ファシリティーを提供するサイエンス・パーク、ベンチャー企業のスクリーニング・投資・育成を行い、リターンを上げることを目的とするベンチャー・キャピタリスト、人的資産のマッチングを役割とするヘッド・ハンター、契約・知的財産権に関わる法務サービスを行う弁理士などがある。スペシャリストであるこれらの仲介者(intermediary)が多様なサービスを提供することにより、大学と企業の間でスムーズな技術移転が可能になる。
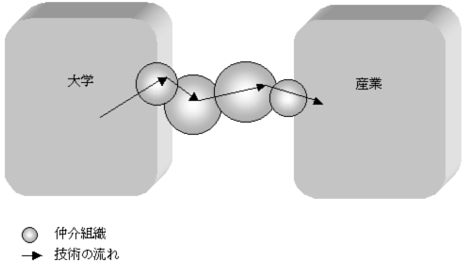
各仲介組織においては、1つの機能に特化するケース、機能を拡充・分化していくケースが存在する。後者の一例を挙げると、スイスのローザンヌ連邦工科大学では、80年代に産業とのインターフェイスとして学内にリエゾン・オフィスが設置され、その後、技術移転の業務が増加するに従いTLOを独立させた。90年代はじめ、当時の学長の発意により、産学連携を目的としたPSE財団 が学外組織として設立され、連邦政府所有の土地を借り入れ、キャンパス内にサイエンス・パークが建設された。インフラ面と併行して、サービスにおいても事業が充実し、基本的なオフィス・サービスに加えて、スピンオフを対象とするコーチング・サービス、インキュベーション・サービスの提供が行われるようになった。またスタートアップへの融資を目的とする技術革新財団も設立された。このような仲介組織の発展は当初から計画されたものではなく、現場のニーズへの対応として打ち出されていった。また大学とPSE財団(注)の間に明白な役割分担がなされていることも特筆に価する。
人材流動化への視点を
日本においても、このような仲介組織の意義が認識されはじめ、技術の事業化に向けてTLOのみならず、インキュベータさらには技術のマネジメントの必要性が謳われるようになってきた。国立大学の中にもTLOを独立の法人として学外に設置し、学外からも専門家をリクルートし、さらにはインキュベーション業務を行う会社をも設立したところがある。しかし、現在27ある承認TLOの大部分は、今後大学人と企業とのマッチングに重点をおかなくてはならないとの認識は共有しているが、ベースとなる業務の遂行に手一杯であるというのが現状のようである。従って、インキュベーション事業を包括する技術マネジメントまで機能を拡充する余力のあるTLOは数少なく、またTLOという外生的に導入された組織にこれらの機能を集中させることによって、範囲の経済が働くという保証もない。TLOはプラットフォーム的な役割と本来の特許化、ライセンシング、マーケティングといった業務に特化し、マッチングの結果として登場する新事業の技術面・ビジネス面でのサポートはインキュベーションに特化した組織に任せるべきであろう。TLOのデパートメント化は、ますます複雑化する世界において、複雑性を処理する組織デザインとして進化しつつある「モジュール化」の思想と真っ向から対立するものである。
最後に、これらの仲介組織を人材の面から考察しよう。アメリカの場合、ここに産業界と大学の双方から、多様な専門的人材が流動的に供給され、よりオープンで、専門化したアーキテクチャーが構築された。今日シリコンバレーなどで活躍するベンチャー・キャピタリストやコンサルタントや成功した企業家には、元IBMの技術者などが数多くいるのである。日本においても、ベンチャー・キャピタルなどを含めた仲介組織が大学周辺に族生し、競争を通じてその能力を高めていくには、産業と大学の双方からの人材の流入が必要である。国立大学教官の兼業規制の緩和はまさにこの方向に沿った施策である。専門家の流動性を促すという観点からも、国立大学の独立行政法人化とそれに伴う大学教官・職員の非公務員化は評価に値するといえるだろう。しかし、一方で、企業による兼業制約の規定などが、ワークシェアリング、セカンド・ジョブというような形態での漸進的な人的資産の流動化のバリアとなっている。また有期雇用契約を結ぶ際、専門的知識を有するものに対しては、1999年の労働基準法改正により、契約を1年以上延長することが可能となったが、それでも3年という上限付きである。大学から産業へ知識を移転する際最も必要とされるのが、技術の評価能力と将来イノベーション・システムが進化する道筋についてのマップを描く能力であることを考えれば、企業に囲い込まれたまま有効利用されていない人材を産業界から仲介組織へ、あるいは大学へと、円滑に流動させるための枠組み作りがこれからの大きな課題となるであろう。そのためにも、労働基準法などの雇用契約期限の規制緩和が必要である。ベンチャー・キャピタルといった仲介組織の育成に関しては、リスク・キャピタルの供給促進などという視点からの規制緩和が、ほどほどなされてきたが、「仏作って魂入れず」という状態にとどまっているのは、産業と大学の間のインターフェイスへの人的資産の流動化という視点がこれまで欠如してきたからであるともいえるだろう。



